土地家屋調査士試験で使う関数電卓とは?使い方と選び方
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります
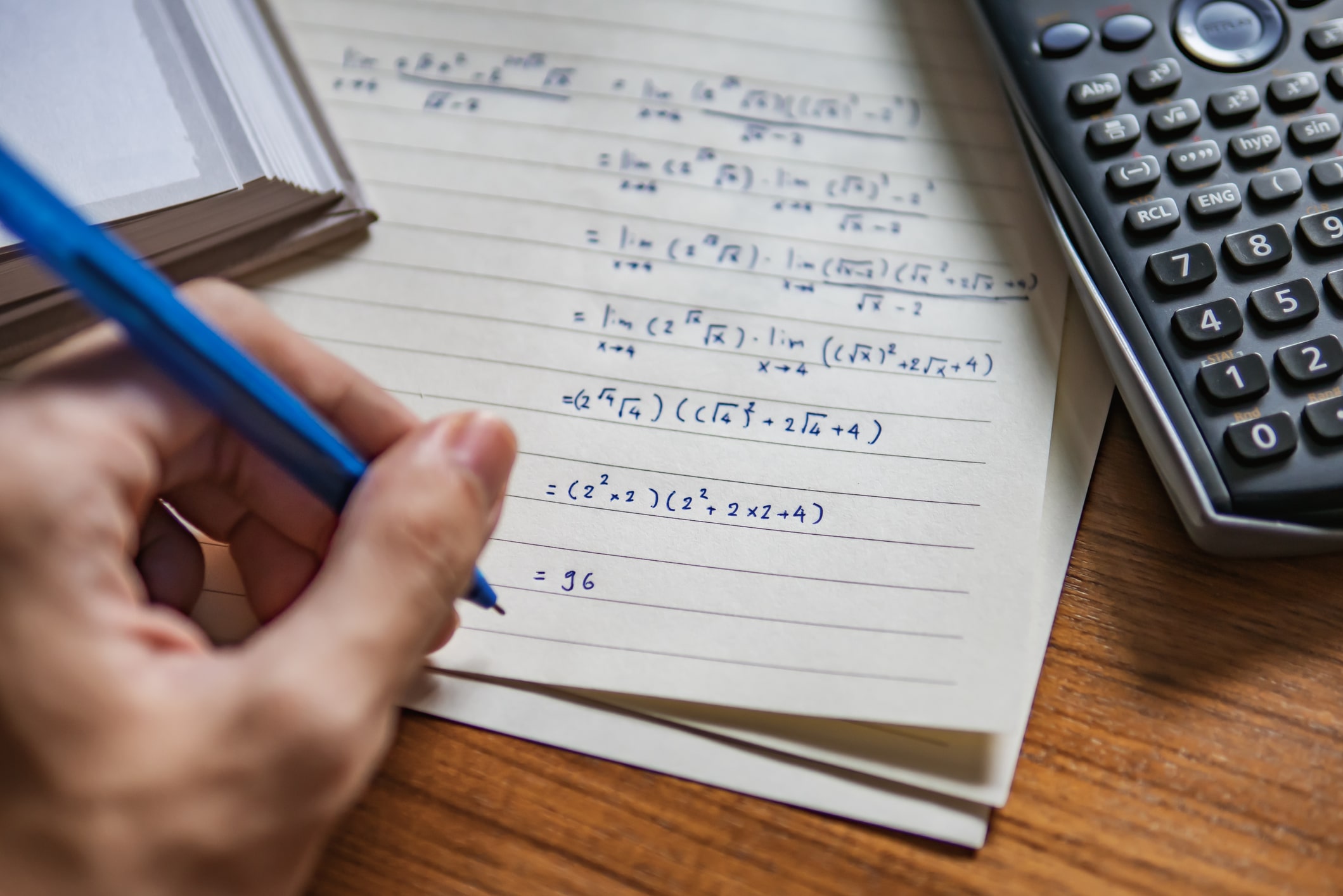
土地家屋調査士は、法務省管轄の国家試験であり、法律を扱う試験ではありますが、関数電卓を使った計算や、三角定規等を活用した作図が試験内容になっているという特徴があります。
ここでは、土地家屋調査士試験になぜ関数電卓が必要なのか?を解説しながら、土地家屋調査士試験にもっとも適した関数電卓を紹介いたします。
土地家屋調査士・測量士補試験合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 土地家屋調査士・測量士補試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの土地家屋調査士・測量士補試験講座を
無料体験してみませんか?
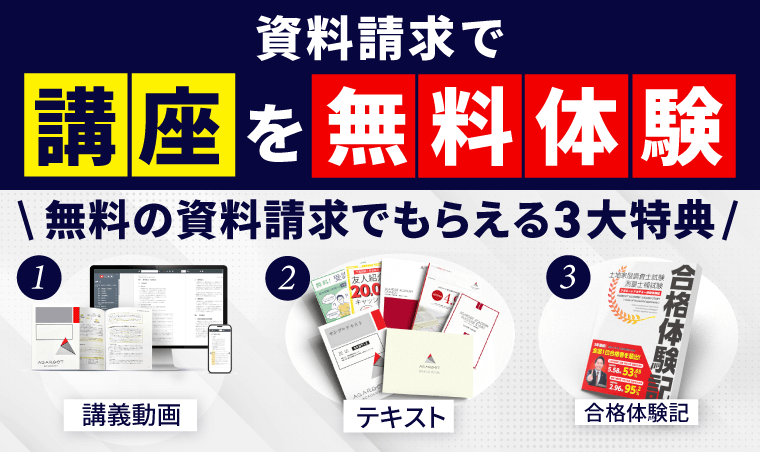

約10.5時間分の土地家屋調査士&約2時間分の測量士補の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!土地家屋調査士・測量士補試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
土地家屋調査士試験で使用する関数電卓とは?

そもそも関数電卓とは何でしょうか?通常の電卓とは、見た目から異なります。
左が通常の電卓で、右が関数電卓です。
関数電卓のほうがボタンの数が多いですね。
しかも、このボタンの多くは「ファンクション機能」を備えていて、特定のボタンと組み合わせることで、1つのボタンで3つ4つの入力をすることができます。土地家屋調査士試験では、ほぼすべてのボタンを使うことになります。
さらに、「sin」や「cos」などの三角関数が表示されたボタンもあります。
電卓の中には三角関数が内蔵されており、三角関数表を見なくても三角関数を入力することができます。
「°′″」ボタンとあわせて使うことにより、高度な図形計算も可能です。
方向キーが付いているのも特徴ですね。
方向キーを操作することで、入力中の計算式の特定の部分を修正したりすることもできますし、今まで入力した計算式を再利用したりすることもできます。
土地家屋調査士試験では、制限時間内に多数の計算をしなければならないため、計算式の再利用を上手く使いこなすことも必要なテクニックです。
また、関数電卓の多くは通常の電卓よりもはるかに多くの「メモリ」を備えています。
例えば、「-50731.24」という座標値を、計算の度に毎回入力していたら時間がかかってしまいます。
このような何度も使うことになる数値は、個別のメモリに記憶させることで、より早く計算ができるようになります。
何度も入力することがなくなるので、ミスも減ります。
通常の電卓でできることは全部できて、さらに便利になったのが関数電卓です。
多くは携帯しやすいサイズになっていますし、関数電卓の便利さを知ってしまったら、通常の電卓が物足りなくなるでしょう。
電卓はどの問題で使用する?
土地家屋調査士試験は、50点分の択一式問題と、50点分の記述式問題に大きく分けることができます。
択一式問題は20問が出題され、記述式問題は、「土地」と「建物」の2問が出題されます。
記述式問題は、実際の土地家屋調査士の実務に沿った内容が出題されることが特徴で、特に、問21である「土地」の問題で、関数電卓の機能をフルに使うことになります。
土地家屋調査士は、不動産の現況を公示するという役割がありますので、不動産の「大きさ」などを正確に計算する必要があります。
土地の大きさ・面積のことを「地積」と言いますが、この地積を求めるために、土地を構成する境界標の座標値を使って面積を計算していきます。
他にも、座標値を求める過程で、多くの測量を行いますから、測量の結果から、最終的な座標値も求めなければなりません。
土地を分ける(分筆と言います。)登記を申請するのであれば、依頼者の希望通りの分割点を計算で求めなければなりませんし、法律で定められた境界があるのであれば、法律知識に加え、計算能力まで要求されます。
もっとも基礎的な座標計算は、特定の点から、距離と角度が決まっている新点の座標値を求めることです。
ここでも、「メモリ」を使って特定の点の座標値を入力し、角度を「°′″」ボタンを使って入力し、「sin」や「cos」などの三角関数を使うことで、新点の座標値を求めることになります。
まさに、関数電卓の機能をフル活用です。
関数電卓の選び方
「複素数モード」がある関数電卓を選ぶ
実は、土地家屋調査士試験では、より早く正確に計算することができる「複素数モード」を使用するのがもはや主流です。
制限時間ギリギリまで戦い抜くほど、土地家屋調査士試験は時間にシビアな試験です。
計算を早くすることができれば、余裕が生まれ、全体の点数を高くすることができます。
複素数モードに関する詳細についてこの記事では言及しませんが、関数電卓には複素数モードが搭載されているものが多く、この機能を使うことで、より少ないメモリ数とより少ない入力式で結果を出すことが出来ます。
土地家屋調査士試験にベストな関数電卓は?
では、土地家屋調査士試験にベストな関数電卓はどれでしょうか。
土地家屋調査士試験では、試験に携行できる(持ち込んで使用することができる)関数電卓の一覧を法務省が公開しています。
その中で、日本国内で普通に流通しているものとなると、カシオとキヤノンの2社のものになります。
どちらも複素数モードを搭載しています。
カシオは「fx-JP500」、キヤノンは「F-789SG」で比較します。
「fx-JP500」、「F-789SG」は、どちらも土地家屋調査士試験の受験会場で多く目にする機種で、一般的です。
なお、カシオにはより上位機種となるfx-JP900や700がありますが、土地家屋調査士試験で使う機能についてはfx-JP500と差がありません。
カシオ「fx-JP500」キヤノン「F-789SG」どちらがおすすめ?
土地家屋調査士試験に携行すると良い関数電卓を選ぶための基準は、
(1)機能へのストローク数(特定の機能に行きつくまでの関数電卓のボタンを押す数・階層)
(2)メモリの数
(3)表示の見やすさ
の3点です。
以上の3点を比較することが、良い関数電卓の基準となります。
(1)機能へのストローク数
これは、カシオ「fx-JP500」に軍配があがります。
2社とも同じ機能が用意されていますが、そこに行きつくまでに押すボタンの数には違いがあります。
カシオの方が、特に複素数モードでのストローク数で優れています。
機能を使わない問題はありませんので、この違いはどのような本試験問題であっても現れてくるでしょう。
(2)メモリの数
何度も使う数値を記憶することができるメモリの数は、キヤノン「F-789SG」の方が圧倒しています。
カシオが全9メモリに対し、キヤノンは全19メモリもあります。土地家屋調査士試験の過去問では、扱う座標値が非常に多い年度のものもあります。
近年の出題傾向から、座標値は少なくなってきていますが、メモリ数を気にしなくてよいというのは利点です。
ただし、必ずしもこの利点が活きてくるとは限りません。
(3)表示の見やすさ
これは大きいです。
実際に使ってみるとよく分かりますが、キヤノン「F-789SG」だと、桁数が多くなると後ろにスクロールしていってしまって、先頭あたりの数値が確認しづらくなってしまいます。
一方、カシオ「fx-JP500」だと、常に画面に先頭まで表示されるため、値を確認しやすいです。
入力ミスは絶対に避けなければならず、入力ミスに気付く可能性が高いカシオ「fx-JP500」の勝ちです。
よって、総合的にはカシオ「fx-JP500」の勝ちです。
上記の理由でアガルートの[中山式]複素数計算をはじめとする各種講義でも、カシオ「fx-JP500」を使用しています。
練習問題を使って,関数電卓の準備・複素数モードのセットアップ・座標値の入出力方法・座標計算・基準点測量・面積計算を解説している『[中山式]複素数計算』のガイダンス動画も参考にしてみてください。
関連コラム:土地家屋調査士試験における「複素数」使用のメリット
関連コラム:土地家屋調査士試験「記述式」の勉強法と理想的な学習時間の配分
土地家屋調査士・測量士補試験の合格を
目指している方へ
- 土地家屋調査士・測量士補試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの土地家屋調査士・測量士補試験講座を
無料体験してみませんか?
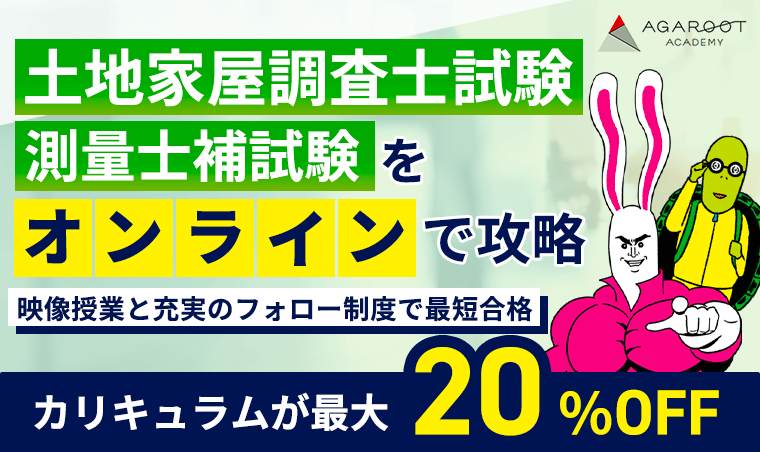
豊富な合格実績!
令和5年土地家屋調査士講座のアガルート受講生の合格率63.41%!全国平均の6.56倍!
追加購入不要!これだけで合格できる
カリキュラム
充実のサポート体制だから安心
合格特典付き!
10月14日までの申込で10%OFF!
▶土地家屋調査士・測量士補試験講座を見る※2024年合格目標
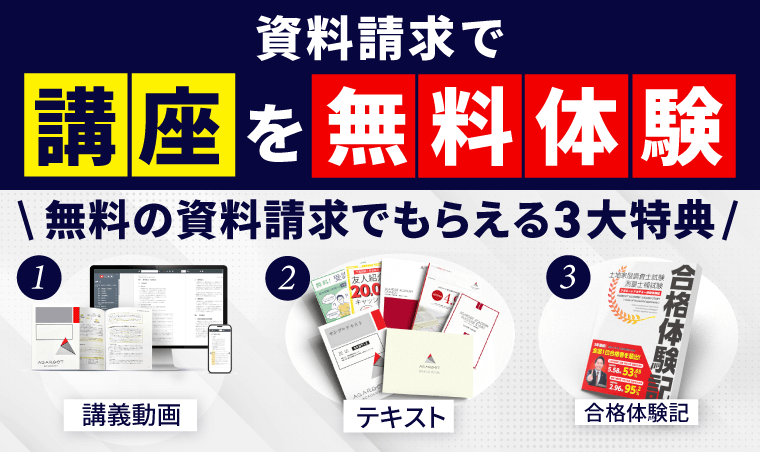
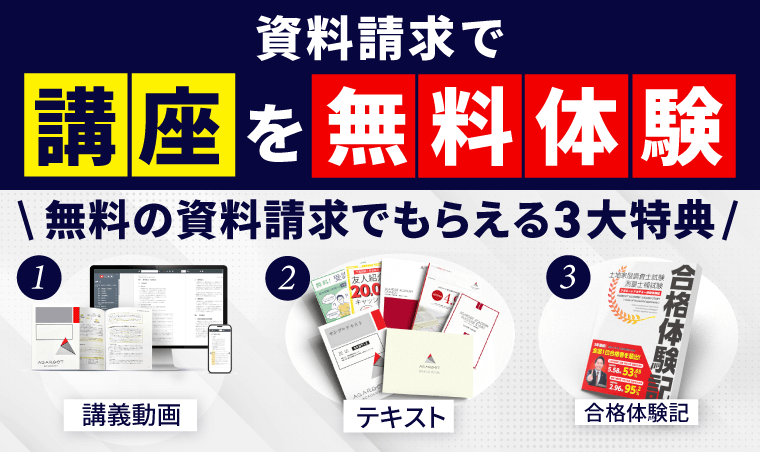
約10.5時間分の土地家屋調査士&約2時間分の測量士補の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!土地家屋調査士・測量士補試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る



