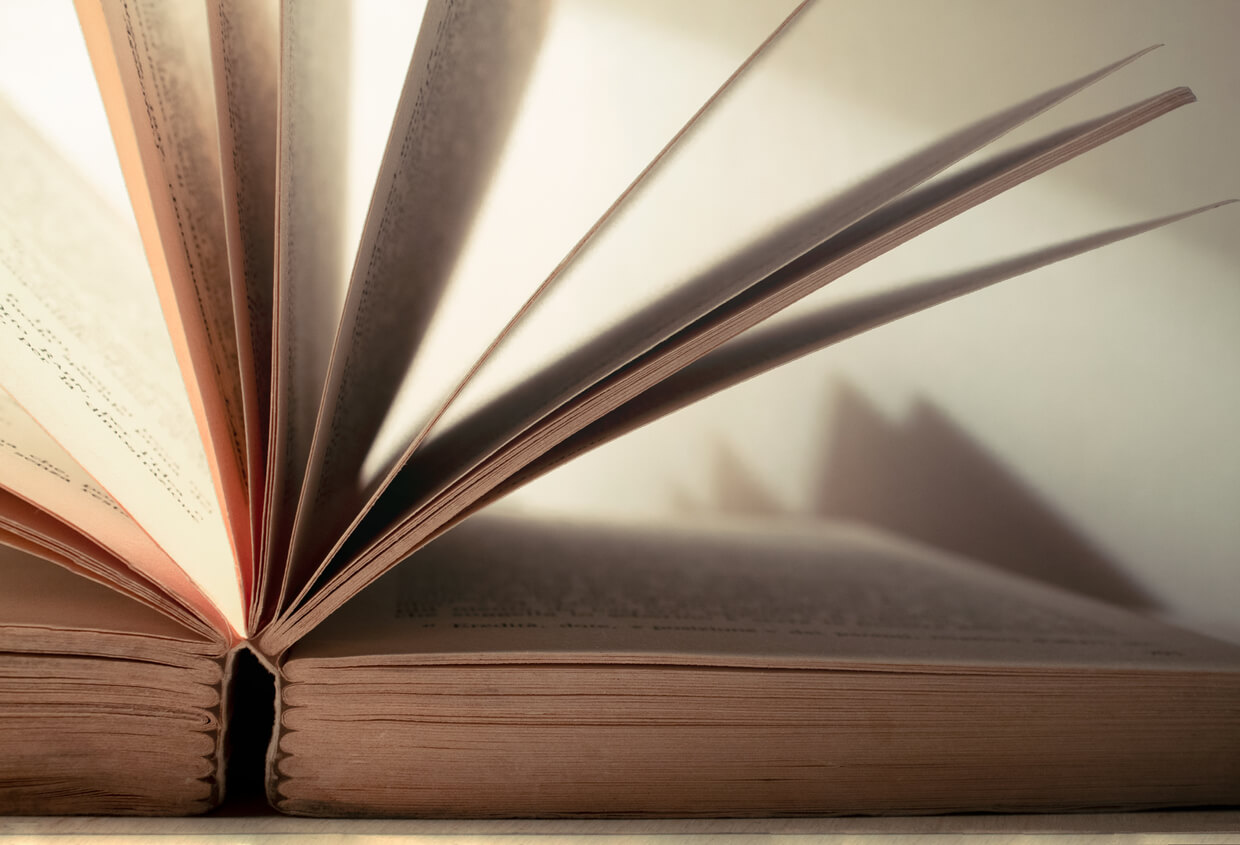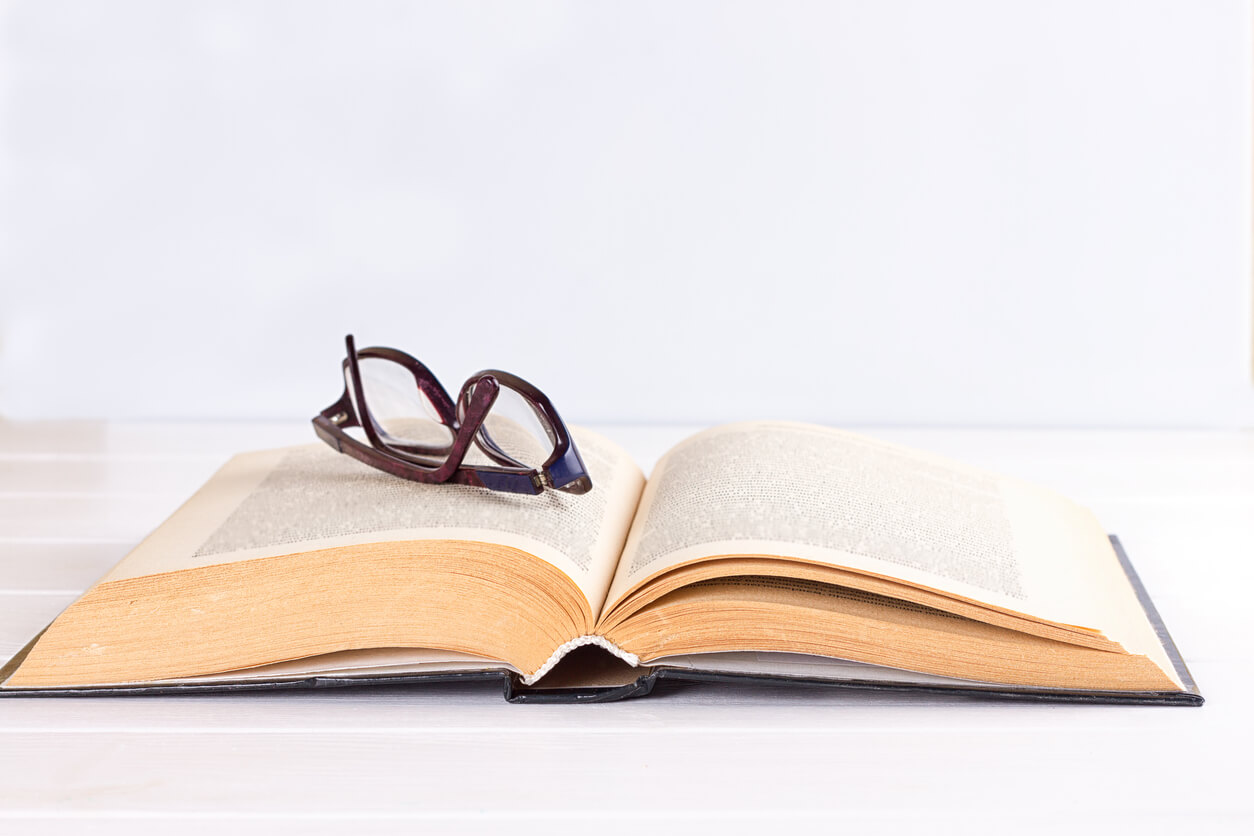社会保険労務士(社労士)試験の勉強方法~傾向と対策~
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

目次
社労士試験合格に向けた基本戦略
社会保険労務士試験の合格戦略を図表を用いながらわかりやすく説明します。
苦手科目を作らない

社労士試験では,全ての科目に科目別必要最低得点(択一式が4点,選択式が3点)が設定されているため,1科目でもこれに届かなければ不合格となってしまいます。
そのため,得意科目で逃げ切るという戦略をとることはできず,全ての科目で満遍なく実力をつけなければなりません。
穴を作らないようにすることが社労士試験の基本的な学習方針になります。
特に選択式は,5点満点中3点が科目別必要最低得点ですので,多くの受験生が苦心しています。
しかし,例年,問題が難しい場合には,科目別必要最低得点を3点から引き下げる救済措置も講じられています。
実務的な話題にアンテナを広げたり,業界で注目の集まっている内容を理解したり,基本的な用語をしっかりと理解するなど,+αの勉強も必要になってきています。
多くの受験生が分かることは漏れなく押さえるように意識して学習しましょう。
効率的な順序でインプットを進める

試験科目とされている8つの法律と2つの一般常識は,全く無関係な法律ではなく,つながりが強いものがあったり,基礎・応用の関係にあるものもあります。
そのため,適切な順序で行えば,効率的に学習を進めていくことができます。
労働分野では,基本となる労働基準法と労働安全衛生法から入りましょう。
労働安全衛生法は元々労働基準法の中にあったものですから,一緒に学習をした方が理解が早いでしょう。
その後,労災保険法,雇用保険法を学んでから,両者の徴収手続について定めた労働保険料徴収法と学習すると,スムーズに進めることができます。
社会保険の分野では,身近でイメージしやすい健康保険法から入ります。
その後,厚生年金保険法の基礎となる国民年金法,応用である厚生年金保険法と進むと効率的です。
理解と記憶の融合を図る
社労士試験は,範囲が広く,細かい数字や紛らわしい語句が多いため,暗記のウエートが高い試験です。
しかし,闇雲に暗記に走っては,覚えきれないですし,最近増えている事例問題などの応用的な問題に対応することもできません。
そこで,基本となる考え方は理解しながら暗記していくことが重要です。
理解は暗記を助けてくれますので,覚えやすく忘れにくい知識になりますし,一つ一つの知識がつながっていくと,学習が楽しくなっていきます。
最後まで続けるためにも,理解しながら暗記するように心がけましょう。
社労士試験の択一式と選択式について
社労士試験では,2つの出題形式が存在します。
「択一式と選択式」です。
「択一式」とは,1問あたり,5つある選択肢から「正しいもの」や「誤っているもの」を1つ解答することを基本とする出題形式です(中には「組み合わせ問題」や「個数問題」も出現しています)。
「知識の深い理解や正確な記憶を心がける」「過去問学習を早い段階で取り入れて,出題傾向に沿った勉強を心がける」必要があります。
「選択式」とは,1問あたり,5つの空欄について20個の選択肢の語句・数値から解答する出題形式です(空欄補充問題)。
基本的には,1つの空欄について4個の選択肢が用意されています。
「基礎・基本的な内容をしっかりと勉強する」「まずはテキストや択一式の勉強から始めて,知識の理解・記憶を進め,専門的な文章を読み慣れておく」ことが重要です。
また,最近では労一,社一などで,奇問・難問と呼ばれる問題が増え,実務寄りの問題,業界の中で話題になっている箇所からの出題など,テキストに記載のない分野からの出題が増えていますので,積極的に情報を得る等,アンテナを広げた勉強も大切になってきています。
社労士試験における科目ごとの勉強方法
初めて学習される方を対象として,社会保険労務士試験の科目ごとの学習方法を端的にわかりやすく説明します。
労働基準法
通達・判例からの出題,条文についての出題が多い分野です。
暗記ではなく条文の内容をよく理解しましょう。
労働安全衛生法
配点は低めなのですが,出題範囲が広く暗記色の強い,厄介な科目です。
出題頻度の高い分野を集中学習して,全体の足をひっぱらない程度の得点を狙って下さい。
ただし,選択式では重要度が増しますので,選択式を意識しながら学習しましょう。
労災保険法
労働者のケガや病気など保険給付に関する出題が中心であり,基本的には,過去問題集を繰り返すことで得点源となる科目です。
事故が起こった際の対応についてしっかりとイメージしながら学習すれば,理解が進んでいきます。
ただし,最近は法的センスが問われるような問題も出題されるため,注意が必要です。
雇用保険法
雇用保険の給付の仕組みの全体像を理解し,給付手続の流れを意識しながら学習することが重要です。
給付の種類がとにかく多いので,一つ一つ丁寧に内容を理解し,その上で,給付日数や金額などの具体的な数値を法改正後の最新の数字で暗記していきましょう。
また,近年は,高齢者の労働雇用も増えており,出題もその点にウエイトが置かれるようになってきています。
労働保険徴収法
徴収の仕組みや方法を理解した上で,計算問題に慣れることが重要です。
数字がよく出てくるので,アレルギーを持たないように学習を進めていくことが大切です。
試験でよく出題される「年度更新」は,社会保険労務士になったら毎年必ず行わなければならない主要な業務ですので,合格後も見据えてしっかりマスターしておきましょう。
労働に関する一般常識(労一)
内容は「労働関係法令」「労働経済」「人事労務管理」の3つに分かれており,最近は特に各種統計資料からの出題が多くなっています。
高得点を狙うよりも,労務管理用語や法令など,比較的対処しやすい出題を取りこぼさないという姿勢で学習するのがよいでしょう。
健康保険法
今までは基礎的な部分を問われることが多く,内容も年金に比べて平易で得点源にできる科目だったのですが,最近は事例問題なども出現するようになっており,難化傾向にあります。
保険料や療養費の計算問題も含めて,全般的にバランスよく出題されていますので,穴を作らないように学習しましょう。
国民年金法
年金法はたびたび改正がなされており,基本的な事項にさまざまな「例外部分」が付いているため,理解するまでに時間がかかる科目です。
しかも,かなり細かい分野からの出題がなされ,また,計算問題も出題されるため,なかなか高得点をとるのは難しい科目です。
厚生年金保険法とも比較しながら腰を据えてじっくりと取り組みましょう。
厚生年金保険法
国民年金法や健康保険法とよく似た法律なので,違いを意識しながら理解していくと効率的です。
国民年金にはない厚生年金独自の給付について押さえておくことがポイントになります。
健康保険法,国民年金法が曖昧なまま,手を付けると混乱して余計に分からなくなりますので,しっかりとマスターしてから始めるのがよいでしょう。
社会保険に関する一般常識(社一)
法令と社会保障の2つの分野に分かれます。
法令分野では,介護保険法,国民健康保険法,児童手当法,社会保険労務士法,確定拠出年金法など,幅広い法令から出題されますが,聞かれる内容は基本的なことも多いので,得点源にしておきたい分野です。
一方,社会保障の分野は,現代社会や政治経済で学ぶような,まさに一般常識といえるような問題が出題されますので,対策がしにくい分野です。
そのため,法令を中心に学習しましょう。
社会保険労務士試験の合格を
目指している方へ
- 社会保険労務士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの社会保険労務士試験講座を
無料体験してみませんか?
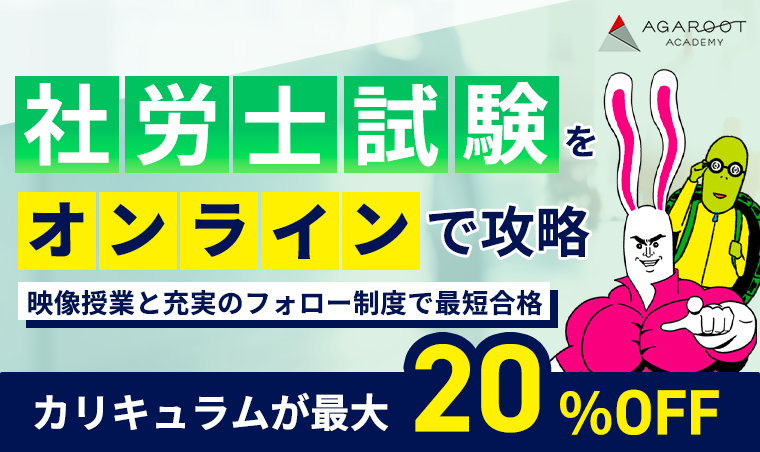
令和5年度のアガルート受講生の合格率28.57%!全国平均の4.46倍
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!


約6.5時間分の労働基準法講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!社会保険労務士のフルカラーテキスト
一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!
1分で簡単!無料!
▶資料請求して特典を受け取る
この記事の監修者 池田 光兵講師
広告代理店で、自らデザインやコピーも考えるマルチな営業を経験後、大手人材紹介会社で長年キャリアアドバイザーを経験、転職サポートを行う。
面接対策のノウハウや数々の自作資料は現在でも使用されている。
その後、研修講師や社外セミナーの講師などを数多く経験。
相手が何に困って何を聞きたがっているのかをすばやく察知し、ユニークに分かりやすく講義をすることが得意。
社会保険労務士試験は、ほぼ独学で就業しながらも毎日コツコツと勉強し、三度目の挑戦で合格した苦労談も面白く、また、三度やったからこそ教えられる「やっていいことと駄目なこと」も熟知している。
合格のノウハウをより多くの受講生に提供するため,株式会社アガルートへ入社。
自らの受験経験で培った合格のノウハウを余すところなく提供する。
池田講師の紹介はこちら