【2024年最新】司法試験・予備試験の短答式試験勉強法&対策まとめ
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

このページでは司法試験・予備試験の短答式試験の勉強法について解説します。
司法試験・予備試験のいずれにおいても一番のヤマは論文式試験です。
そのため , 短答式試験については , なかなか時間を割くことができませんが , 司法試験でも予備試験でも短答式試験をクリアしなければ最終合格はできません。
そこで,短答対策を効率良く行う方法を紹介します。
司法試験・予備試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 司法試験・予備試験・法科大学院の情報収集が大変
- 司法試験・予備試験・法科大学院に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を
無料体験してみませんか?

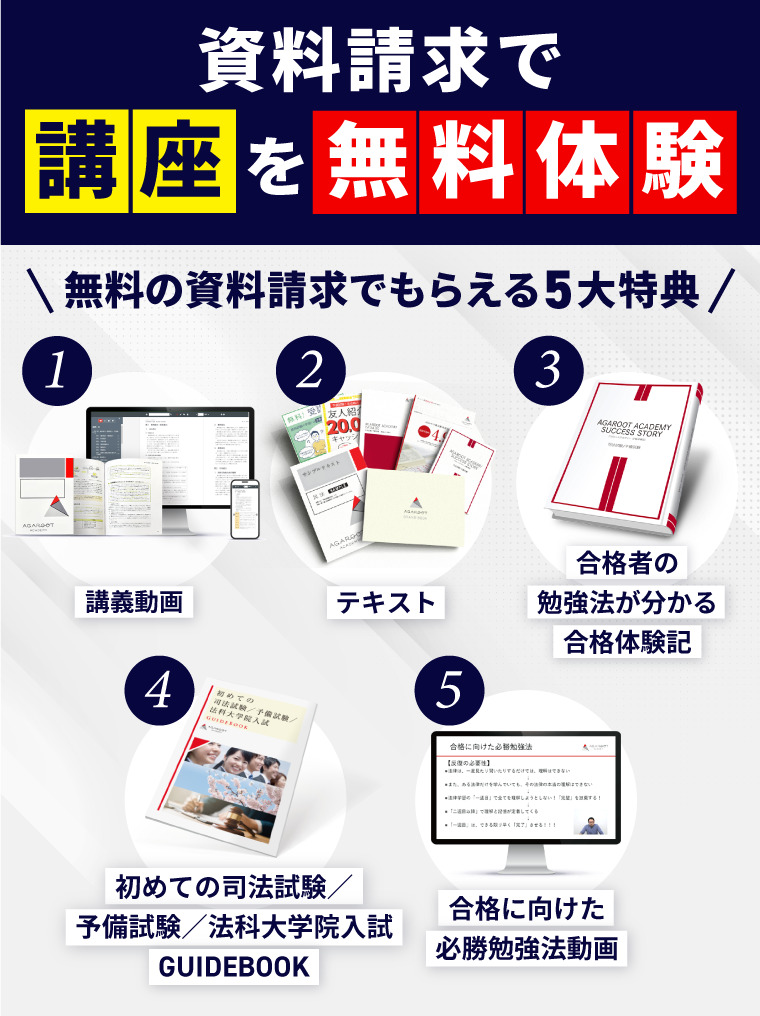
約13時間分の民法講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!
司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック
合格の近道!司法試験のテクニック動画
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
【司法試験・予備試験】短答式試験はどう攻略すべき?「量」と「質」両方の対策法を紹介!
【司法試験・予備試験】短答式試験で問われるもの
マークシート方式の選択問題
短答式試験は,司法試験と予備試験のいずれの試験でも問われます。
短答式試験は , マークシート方式の試験による選択問題です。
短答式試験では , 論文式試験で問われる知識と重なっている知識が出題されることもありますが , 論文式試験では直接問われないような細かい条文知識等が出題されることも多いです。
そのため , 論文式試験に出題されない細かい知識については , 論文式試験とは別個に対策をする必要があります。
短答式試験の内容
司法試験では,民法・憲法・刑法の3科目から出題されます。
試験時間は、民法が1時間15分、憲法及び刑法は50分です。
論文式試験の合計点が1,400点であるのに対して,短答式試験の合計点は175点であり , 論文式試験と短答式試験の点数の合計により合否が決まります。
そのため、短答式試験の勉強を疎かにする人が少なくありませんが,短答式試験に合格しなければ論文式試験を採点してもらえないため,しっかり対策をする必要があります。
関連コラム:司法試験の難易度・合格率をアガルート講師がお答えします
予備試験では,司法試験で問われる3科目に加えて,商法・民事訴訟法・行政法・刑事訴訟法・一般教養科目の計8科目から出題されます。
試験時間は、民事系(民法・商法・民事訴訟法)及び一般教養科目は1時間30分、公法系(憲法・行政法)及び刑事系(刑法・刑事訴訟法)は1時間です。
司法試験と比べて科目数が多く,出題範囲が膨大であるため,効率良く勉強をする必要があります。
関連コラム:予備試験の難易度は?現役予備校講師が正直に解説します
総論
司法試験・司法試験予備試験の短答式試験においては,記述の正誤を問い,正確な法律知識を備えているのかを試す問題が多く出題されています。
短答式試験では、論文式試験で問われる知識と,短答式試験でしか問われない独自の細かい知識(これを司法試験受験界では,「短答プロパー知識」と呼んでいます)を問う問題が出題されています。
そのため,論文式試験と共通する基本的な知識の他,短答プロパー知識についてもしっかりとマスターしていく必要があります。
一方で,短答式試験では,論文式試験ほどの高度な思考力は要求されず,また,解答の形式もマークシート式なので,知識のインプットさえしっかりとなされていれば,一定程度の得点を取ることはできます。
ただし,科目によっては , 少なからず論理操作を求める問題が出題されています。
また,人間の記憶力には限界がありますので,どうしても記述の正誤が分からない場合に,文章を読み、国語力を駆使して判断しなければならない場面や、直感や常識に頼って判断すべき場面にも遭遇します。
そのため,知識を中心として問う出題傾向だからといって,知識だけで押し切ろうとするのではなく,インプットしなければならない知識の範囲をある程度絞り込んだ上で,後は論理的思考力を養成し、過去問を中心とした問題演習を繰り返し、「現場の感覚」を常に意識しつつ、得点を伸ばしていくという方法がベストです。

【司法試験・予備試験】短答式試験の具体的な勉強の指針
8割を取れるようにしよう
司法試験にせよ予備試験にせよ,短答式試験ではコンスタントに8割を取れるようになることが理想です(予備試験の場合は一般教養科目を除いた法律科目に限る)。
司法試験の短答式試験に合格するためには、全体の概ね60~70%正解できれば足りるのですが,司法試験では短答式試験の点数が最終合格の点数に反映されるため,短答式試験で高得点を取ればそれだけでアドバンテージになります。
また,予備試験の短答式試験においては、8割を取ることができれば,法律科目だけで合格点に達することがほぼ可能であるため,一般教養科目に勉強時間を充てる必要がなくなります。
実際にも、一般教養科目に勉強時間を充てている方は極めて少ないです。
予備試験の場合には、その後に控えている論文式試験において一般教養科目は出題されないため、やはりそのような戦略は正しいものといえます。
過去問を潰す
先ほども述べたように,短答式試験では条文の細かい知識等,幅広い範囲から出題されます。
このような場合に、六法や、インプットテキストを読み込むだけでは、やはり頭の中に記憶されにく、膨大な時間が失われてしまう恐れがあります。
したがって、常に問題演習(アウトプット)と並行したインプットをしていく必要があります。
また,短答式試験では,過去問が同じように問われるような場合も少なくありません。
そこで,過去問を潰すことをお勧めします。具体的な過去問の使い方については後ほど説明します。
条文を素読する
短答式試験では,条文に直接書いてあることがそのまま問われることが少なくありません。そこで,条文を素読することをお勧めします。
ここで大切なことは,漫然と読むのではなく,
①条文の制度趣旨(この条文がなかったら誰が困るのか)
②「要件」と「効果」(要件が何個あるか、具体的な要件か、抽象的な要件か)
③関連判例(当該条文の要件に関連する判例・他の論点があるか)
を意識しながら丁寧に読むということです。
なぜなら,このように目的意識を持って呼んだ方が頭に定着しやすい上,論文式試験の勉強にもなるからです。
関連コラム:司法試験予備試験に1年で合格する勉強法
【司法試験・予備試験】短答式試験における過去問の使い方
選択肢ごとにマークをつける
過去問を解く際に,選択肢ごとに自分の理解度を示すマークをつけることをお勧めします。
例として,
正解に至るまでの理由を含めて理解できている場合は◎,
間違えたけれども、解説等を読んで理由を理解できている場合は△ ,
間違えた場合や、たまたま勘で正解した場合で、かつ、解説等を読んでも理由が理解できない場合は× ,
などと選択肢の横に印をつけていきます。
イメージとしては,過去問を何度も解き,×を△に、△を◎にして、最終的にはすべての選択肢が◎になるのが理想です。
△と×の選択肢は正解に至るまでの理由を含めて理解する
過去問を解いてみて△と×だった選択肢は,解説や基本書等でしっかり確認をしましょう。
ここで大切なことは,なぜ間違えたのかを把握した上で,どのように考えれば正解にたどり着くことができたかを確認することです。
なぜなら,理由付けまで理解してないと,同じ問題が出ても記憶頼みになるだけでなく,類似問題や応用問題に対応できないからです。
2周目からは△と×だけを解く
先ほど述べたように,1周目はマークをつけながら過去問を解いていきますが,2周目からは△と×に絞って解いていきます。
そして,2周目も同じようにマークをつけていきます。
ここでも,上述のルールに従い,正解に至るまでの理由を含めて理解できた場合のみに◎を付け,それ以外は△と×をつけていきます。
ここで大切なことは,1周目を終わらせてから,2周目を始めるまでの期間を空けすぎないということです。
なぜなら,知識とは,壁にペンキを何層も塗っていくように,繰り返しを積み重ねていくことで定着するものですが,期間が空きすぎると,せっかく最初に作った土台がゼロになってしまうからです。
△と×が多い分野に絞って基本書を通読する
過去問を解いていくと,「この分野は△と×が多い」ということに気がつくことがあると思いますが,この分野は基本的知識が不十分であることが考えられ,自分の苦手分野にあたると考えていいでしょう。
このような分野については,基本書を通読して,基本的な知識を再確認しましょう。
関連コラム:司法試験・予備試験におすすめ基本書32冊【7科目・目的別】
予備試験対策は過去問だけだとキケン!周辺知識もさらっと確認する
短答式試験で安定して合格点をとるためには,すべての選択肢が◎になるまで過去問を解きつつ,周辺知識も確認する必要があります。
例えば,平成29年度の司法試験の短答式試験(民法)では,「受寄者は,無償で寄託を受けた場合には,自己の財産に対するのと同一の注意をもって,寄託物を保管すれば足りる。」という選択肢が出題されていますが,この問題は「無報酬の受寄者は,自己の財産に対するのと同一の注意をもって,寄託物を保管する義務を負う」と定めている民法659条の存在を知っていれば解ける問題です。
しかし,実際に過去問を回す際には,民法659条を確認するだけで終わらせるのではなく,
「有償の場合はどうなるのか」
「他に自己の財産に対するのと同一の注意義務を負う場合はどのような場合か」
「寄託契約の基本的内容はどのようなものか」
というように,周辺知識を確認しながら,知識の幅を広げていく勉強を心がけるようにしましょう。
科目ごとの短答式試験の勉強法
以下では各科目の勉強法について説明します。
こちらはある程度学習が進んでいる方を対象としているので,これから学習を始める方は飛ばしてしまってください。
憲法(司法試験・予備試験)
憲法は,例年,判例知識の正確な理解が問われています。
特に人権分野ではその傾向が顕著で,百選掲載判例については,結論だけではなく,判旨の論理や理由まで理解することは最低限必要であるといえます。
もっとも,判例の細部にわたる理解が問われることがあること,4つの選択肢すべての正誤を判定しなければ正解に至ることができないものもあることから,人権分野において高得点を望むことはなかなか難しいものと思われます。
そこで,対策としては,過去問で繰り返し問われている判例を素材とする選択肢・問題は必ず正解し,その他の細かい知識を問う肢は部分点狙いで得点していくことをおすすめします。
これに対して,統治分野においては,重要判例の理解を問う問題に加え,単純な条文問題も出題されます。
そのような問題で確実に得点することで,安定した得点を取ることが出来るでしょう。
憲法の短答式試験対策としては,人権分野では,判例知識を問われることがほとんどであるため,まずは重要判例の判旨を正確に理解することが挙げられます。
また,細かい知識を問う問題については,あまり時間をかけ過ぎないよう注意しつつ,部分点を狙っていくことで十分でしょう。
細かい知識については、上記のように、国語力や、常識力で判断していくことになります。
統治分野では,過去問で繰り返し問われている重要判例を理解しつつ,単純な条文問題で確実に得点することが必要になります。
行政法(予備試験)
行政法も,憲法と同じく判例の知識を中心に聞かれることが多いといえます。
そのため,有名判例については,判旨の結論部分だけではなく,どのような論理によりどのような結論を導いたのかについて正確に理解することが重要です。
もっとも,憲法とは異なり,深く理解する必要のある判例の数はそこまで多くありません。
よって,効率よく得点するためには,過去問で繰り返し聞かれている重要判例については論理や理由まで理解し,その他の判例については結論部分だけ暗記することでも十分対処することができるといえます。
また,行政法では,特に行政救済法分野の条文知識も問われることが多いです。
これらの条文は,数もそこまで多くないため,確実に得点する必要があります。
そこで,条文の素読に加え,行政上の救済措置としていかなる手段があるのか,また,訴訟要件や本案勝訴要件は何か等について自分のまとめノート等に事前に整理しておくことをおすすめします。
これは,短答式試験だけではなく論文式試験で出題される訴訟選択の問題においても役立つ知識になります。
民法(司法試験・予備試験)
民法は,特定の分野に偏ることなく,全分野から万遍なく出題されます。
また,最も多い出題は条文知識ですが、民法の条文は1000条以上あります。
これに加え,判例の理解を問う問題,実際の事例が与えられ,条文や判例を当てはめた場合の結論を問う問題といったように,様々な形式で出題されるため,対策が非常に難しい科目です。
よって,民法の短答の勉強を始めた頃は,その量の多さに戸惑ってしまう方も少なくありません。
もっとも,確かに出題範囲は広いですが,問題自体は基本的なものが多いため,一度知識を定着させてしまえば点数が安定しやすい科目です。
そのため,過去問を繰り返し回すことで知識を定着させ,何度も聞かれている肢については確実に得点していくことが必要です。
また,民法で高得点を狙うためには,家族法についてもしっかりとした勉強を行う必要があります。
もっとも,短答式試験に割くことができる時間的制約もあるため,細かい知識にまでは手が回らない方も多いと思います。
そこで,最低限の対策としては,家族法については,過去問で聞かれた肢の正誤の判断のみ出来るようになる程度に止めておき,総則,物権,債権の分野で確実に得点していくという方法でも,合格点を狙うことは十分に可能です。
商法(予備試験)
商法は,会社法を中心として,手形・小切手法,商法総則の分野から出題されます。
商法で合格点を狙うためには,まずは会社法をしっかりと勉強する必要があります。
会社法では条文知識が中心に出題されるため,過去問での演習が不可欠となります。
もっとも,会社法は,条文一つ一つが非常に長かったり,規定の仕方が複雑であったりするため,闇雲に暗記しようとするのは限界があります。
そこで,おすすめの勉強法は,ある規制や手続きが規定されている場合に,なぜそのような規制や手続きが要求されているのか(例えば,なぜ株主総会普通決議ではなく特別決議が必要なのか等)について,自分なりに理由をつけつつ暗記することです。
理由をつけて暗記するだけでも定着率は格段に上がるため,普段の勉強から,常に理由を考える癖を付けておくことが重要であると言えます。
また、条文の勉強をする際には、「目次」も利用するとよいと思います。
こうすることによって、関連条文の学習も効率的になりますし、論文式試験で求められる条文の検索能力も飛躍的に向上します。
とはいえ,商法の短答式試験対策に割くことができる時間は限られているので,過去問で問われた知識についてだけ上記の対策をし,他はある程度捨てるということでも止むを得ません。
また,論文式試験対策としてはマイナー分野として位置付けられる手形法・小切手法,商法総則・商行為法からも一定数の問題が出題されます。
そのため,商法で高得点を望む場合には,これらの分野でも点数を稼がなければなりません。
もっとも,出題数の多い会社法分野の対策がメインとなることは間違いありませんので,手形法・小切手法,商法総則・商行為法については,過去問で問われた知識のみ正確に理解し,得点するということで十分だと考えるべきでしょう。
結局,商法は最も高得点を狙いにくい科目なので,ある程度の割り切りは必要ということです。
なお,会社法は近時何度かの改正があった影響で,過去問の中には正解が存在しないものもあります。過去問集等は必ず改正会社法に対応したものを使うことが必要です。
民事訴訟法(予備試験)
民事訴訟法は,判例知識・条文知識が万遍なく問われます。
条文知識を勉強する際に意識すべきことは,手続きの流れを想像しながら勉強することです。
自分が解いている問題が,訴訟の開始に必要とされる手続きなのか,審理過程において必要とされる手続きなのか,それとも訴訟の終了において必要とされる手続きなのかを常に意識しながら,条文に立ち返りつつ勉強する必要があります。
また,なぜそのような制度・条文となっているのか理由を考えつつ知識を覚えていくことも重要です。
判例知識は主に百選掲載の重要判例を素材として問われており,事例問題として判例の結論を問う問題も出題されています。
百選掲載判例については,他の科目と同様,結論だけではなく,その理由等,論理の流れもしっかりと理解しておくようにしましょう。
刑法(司法試験・予備試験)
刑法では,主に判例知識を問う問題が出題されます。
判例知識を問う問題では,具体的な事例が与えられ,判例の立場からの結論や正誤を問う問題が多く,論文式試験と類似の出題がなされています。
そのため,論文式試験対策をしっかりと行うことが,そのまま短答式試験対策に繋がります。
論文式試験用の知識・理解で例年6割~7割程度得点することが可能です。
もっとも,短答式試験では,論文式試験では出題されない細かい構成要件の理解を問う問題も出題されていますので,高得点を狙うためにはこのような問題でもしっかりと得点できなければなりません。
その対策としては,その構成要件が適用される典型的な事例を押さえると共に,判例を中心に個別の構成要件要素の解釈を理解することが重要です。
また,最近の傾向として,複数の学説が示され,それぞれの見解からの結論を問う論理問題が出題されることが多くなっています。
旧司法試験においてよく出題されていたタイプの問題です。
このタイプの問題は,事前の知識がなくても現場思考で解くことが出来るため確実に得点したいところです。
もっとも,知識問題とは異なり,現場での処理時間が必要になるため,解くのに時間がかかります。
そこで,知識問題を解き終わった後に,時間をかけて確実に正解することがおすすめです。
ただし、最近は、『罪責を論ぜよ』という出題のほか、ある分野に関しての学説を問う問題であったり、一定の結論に向けた論述が求められる問題が出題されたりすることもあります。
刑法は,論文式試験対策をこなすだけである程度の得点が望めるだけでなく,難解な問題が出題されることが少ないため,確実に得点源にしていきたい科目です。
もっとも,上記のように,解答に時間がかかる問題があり,時間不足に陥りがちですので,時間配分には十分注意する必要があります。
刑事訴訟法(予備試験)
刑事訴訟法は,捜査法の分野において判例知識が,公訴提起以降の分野においては条文知識が主に問われる傾向にあります。
前者においては,刑法と同様に論文式試験対策が短答式試験対策に直結するため,特別な対策は不要です。
後者においては,特定の知識が繰り返し問われる傾向にありますので,過去問で問われた条文知識を理解し,暗記すれば十分高得点をとることが出来ます。
ただし、最近は、『罪責を論ぜよ』という出題のほか、ある分野に関しての学説を問う問題であったり、一定の結論に向けた論述が求められる問題が出題されたりすることもあります。
刑事訴訟法も,刑法と同様に比較的解きやすい問題が出題されるため,得点源としたい科目です。
一般教養科目(予備試験)
一般教養科目は,人文科学,社会科学,自然科学及び英語が出題範囲となっています。
どの範囲の問題も難易度が高く,付け焼刃的な対策では歯が立ちません。
例えば,自然科学の中には,物理が含まれるのですが,理系出身で高校生の頃に物理を選択していた方であれば,何とか対応できるといったレベルの問題が出題されます。
その上,範囲が広く,司法試験では出題されない分野です。
そのため,多くの受験生がほとんど何も対策をせずに試験に臨みます。
そこで,ほとんど事前の対策をせずに,一般教養科目の平均点である24点~30点程度(60点満点)を目指すというのが,多くの受験生にとっての現実的な目標になります。
ちなみに,合格点が170点の場合,24~30点を一般教養科目で稼げるとすると,残り140~146点(7割弱)を法律基本科目で得点すればよいということになります。これはそこまで難しい話ではありません。
では,その24点~30点を稼ぎだすためにどうすればいいのかということになります。
まず,マークシートで解答する形式なので,適当にマークをするだけでも,20問中3,4問は正解になります。1問3点なので,これだけで9点~12点になります。
残り12点~21点(3問~7問)ですが,上記のように,実は事前知識が無くても,時間さえかければ解ける問題が数問出題されています。
それらの問題は,多少処理に時間がかかってもいいので,確実に正解できるようにしましょう。
過去問だけで構いませんので,それらの問題を解いて,訓練を積んでおいてください。
他にも,英語がある程度できるということであれば,英語の問題を選択して点数を稼ぐことも可能です。
もちろん,日本史や物理など,その他の科目ができるのであれば,そこから点数をもぎ取るという戦略でも構いません。
ちなみに,司法試験予備試験の短答式試験には,いわゆる「足切り」がありません。
そのため,仮に10点前後しか採れなかったとしても,法律科目で+10点,15点稼げば合格点に達することが可能です。
一般教養科目は「点数が採れればラッキー」くらいに気楽に考え,その分法律基本科目で8割,9割の得点を目指していきましょう。
短答式試験で問われる法律基本科目7科目については、論文式試験の科目になっています。
そして、短答式試験の知識は、論文式試験を包摂する関係にあります。
つまり、短答式試験の学習をしていると、その一部は、論文式試験で求められる知識の確認にもなっているのです。
したがって、論文式試験対策にならない一般教養科目の対策を講じるよりも,法律基本科目の対策に集中した方が合理的であるといえます。
短答式試験の対策はいつから始める?おすすめ勉強スケジュール

短答式試験の対策をいつから始めるか?については、人それぞれ学習スタイルが違うため、一概にこれがベストと言えるものではありません。
ただし、目安としては、試験前年の12月まで、論文対策を中心に進めながら、短答式の対策も進め、年明けから本格的に短答式対策に取り組むことがおすすめです。
具体的なスケジュール例は、以下の通りです。
〜12月まで(年内)の勉強スケジュール
この時期は、論文の勉強を中心に行いながら、進行度合いに応じて短答の学習も段階的に導入していくことをおすすめします。
論文の勉強が進んだ科目から、短答の問題も解いてみるといいでしょう。
最終的には、95%ほど正解できるようになることを目指しますが、この時点では各科目、一通り問題集を解くことを目標としておいて問題ありません。
あくまで、論文重視で対策を進めておきましょう。
年明け〜4月の勉強スケジュール
7 月の短答式試験に向けて、短答式対策の比重を上げていく必要があります。
主な勉強法は過去問を繰り返し解いて、理解することです。
年内に解けなかった問題は、必ず解けるようにし、過去問での学習は正解できるまで何度も繰り返し行いましょう。
正確な知識をインプットし、誤答した場合は、その部分の学習を強化しましょう。
また、過去問は限られた時間で解けるよう時間管理についても意識しておきましょう。
短答に合格しなければ論文式試験を受験できませんが、論文式試験に合格しなければ、予備試験の最終合格は果たせません。
そのため、論文式試験の勉強も並行していく必要があります。
そこで、年明けからの論文式試験との勉強の比率を決定する目安として、「週1回、単年度の過去問を解く」という方法をおススメします。
例えば、日曜日(短答式試験本試験も日曜日に実施されます)に、ある年度の過去問(法律基本科目7科目)を解いてみて、合計210点満点のうち、180点以上取れるようであれば、論文の勉強の比率をさほど下げなくてよいと言えます。
他方、100点以下なのであれば、論文の勉強の比率を下げて、短答:論文=9:1程度に学習時間を調整する必要が出てきます。
このように、こまめに、現在の自分の立ち位置を把握し、「今、何をどの程度学習すべきか」をその都度確認し、実行していく必要があります。
短答式試験直前の勉強スケジュール
この時期に、各予備校で、短答式試験の公開模試が行われます。
本番に近い環境で実力を発揮できるよう、受験しておきましょう。
また、過去問を総復習し、知識が定着しているか確認しておくといいでしょう。
答えを丸暗記するのではなく、きちんと中身を理解できているか、意識してチェックしておいてください。
短答式試験の対策におすすめの講座

短答式試験の対策講座をお探しの方には、アガルートの「短答知識講座」がおすすめです。
短答式対策が手薄になっていて不安な方、効率的に短答式の勉強をしたい方には特に適した講座となっています。
講座には、以下の2つがあります。
・「短答式知識完成講座Ⅰ憲法・民法・刑法」
・「短答式知識完成講座Ⅱ行政法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法」
サンプル講義も視聴できますので、気になる方は確認してみてください。
短答式試験対策におすすめの問題集
ここからは、短答式試験対策におすすめの問題集を紹介します。
短答過去問パーフェクト|辰巳法律研究所
現在の制度となった平成18年~令和3年までの司法試験短答式試験の全過去問と、予備試験短答式試験の全過去問(平成23~令和3年)を完全収録した問題集となっています。
難易度や正答率も把握できる点も特徴といえます。
解説も丁寧でわかりやすい内容となっています。
肢別本|辰巳法律研究所
予備試験の短答式試験では、多くの問題が「5肢選択一式」となっています。
『肢別本』では、5つの中から正解を選ぶのではなく、それぞれの選択肢をバラバラにして、1問ずつ〇×形式で出題されますので、より正確な知識を身に着けることができます。
過去問集を一通り勉強した後に、本当に知識が付いているか確認する上でも、有益な問題集といえるでしょう。
司法試験・予備試験の合格を
目指している方へ
- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を
無料体験してみませんか?

合格者の声の累計641名!
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
予備試験合格で全額返金あり!

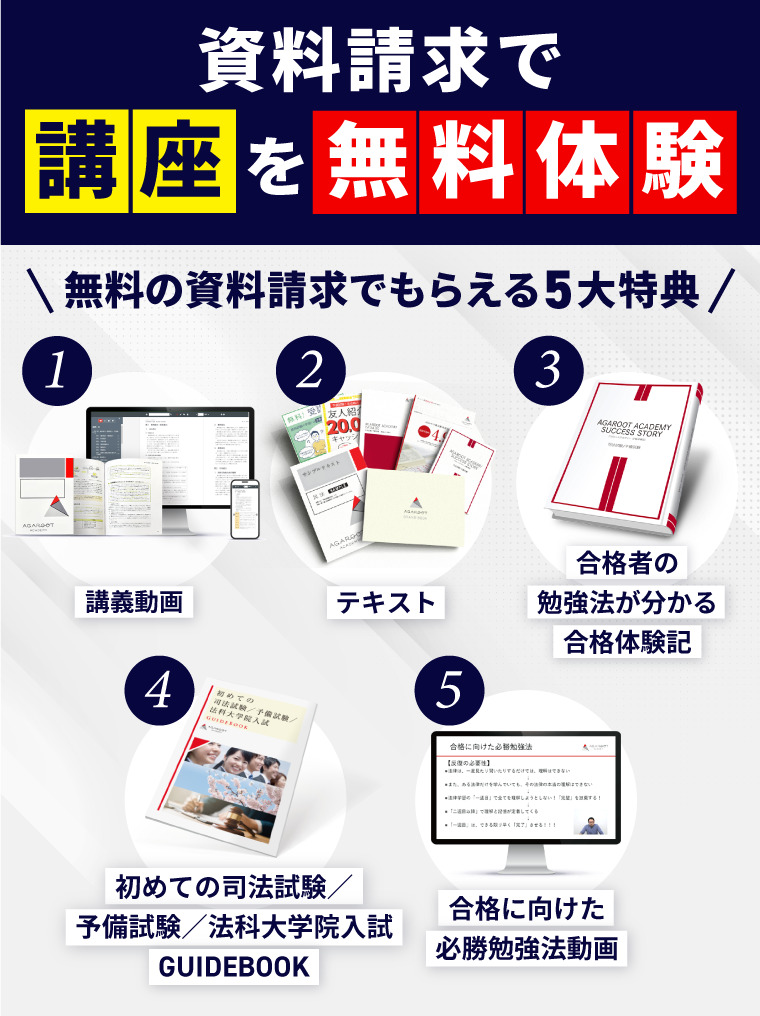
約13時間分の民法講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!
司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック
合格の近道!司法試験のテクニック動画
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る
この記事の監修者 谷山 政司 講師
平成23年度に(新)司法試験に合格後、伊藤塾にて主に予備試験ゼミを中心とした受験指導業務を担当。
谷山ゼミ受講者のうち、およそ70名ほどが予備試験に合格。谷山ゼミ出身者で、最終的な予備試験の合格率は7割を超える。
自身の受験経験だけでなく、答案の徹底的な分析やゼミ生への丁寧なカウンセリングの結果確立した論文作成ノウハウをもとに、アウトプットの仕方はもちろん、インプットの仕方までをも指導するスタイルは、ゼミ生の圧倒的支持を受けた。
また、期をまたいだゼミ生の交流会等を定期的に行うなど、実務に出た後のフォローも積極的に行っている。
谷山講師の紹介はこちら
ブログ:「谷山政司のブログ」
Twitter:@taniyan0924



