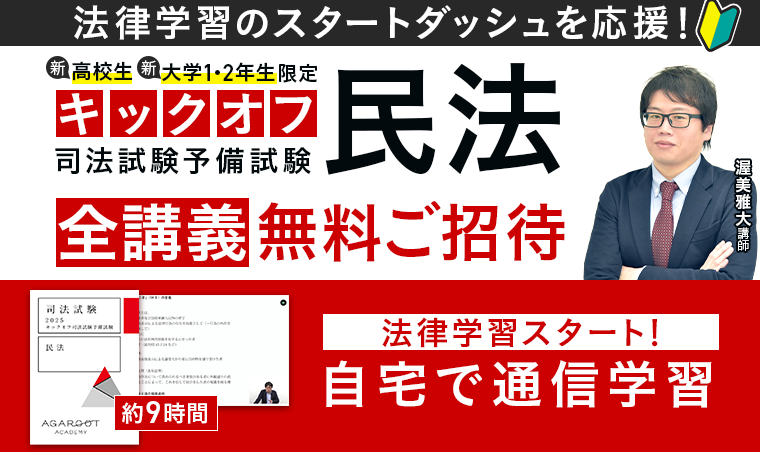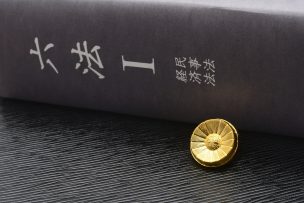予備試験に独学で合格するのが難しい4つの理由。勉強法は?
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

司法試験に独学でチャレンジしようとする方は一定数いらっしゃいますが,一般に独学で司法試験・予備試験に合格することは極めて難しいと言われています。
その4つの理由を解説します。
司法試験・予備試験の受験を
検討されている方へ
- 司法試験の勉強についていけるか不安
- 司法試験に関する情報を漏れなく手に入れたい
- 司法試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
このような悩みをお持ちでしたら
アガルートの無料体験を
ご活用ください

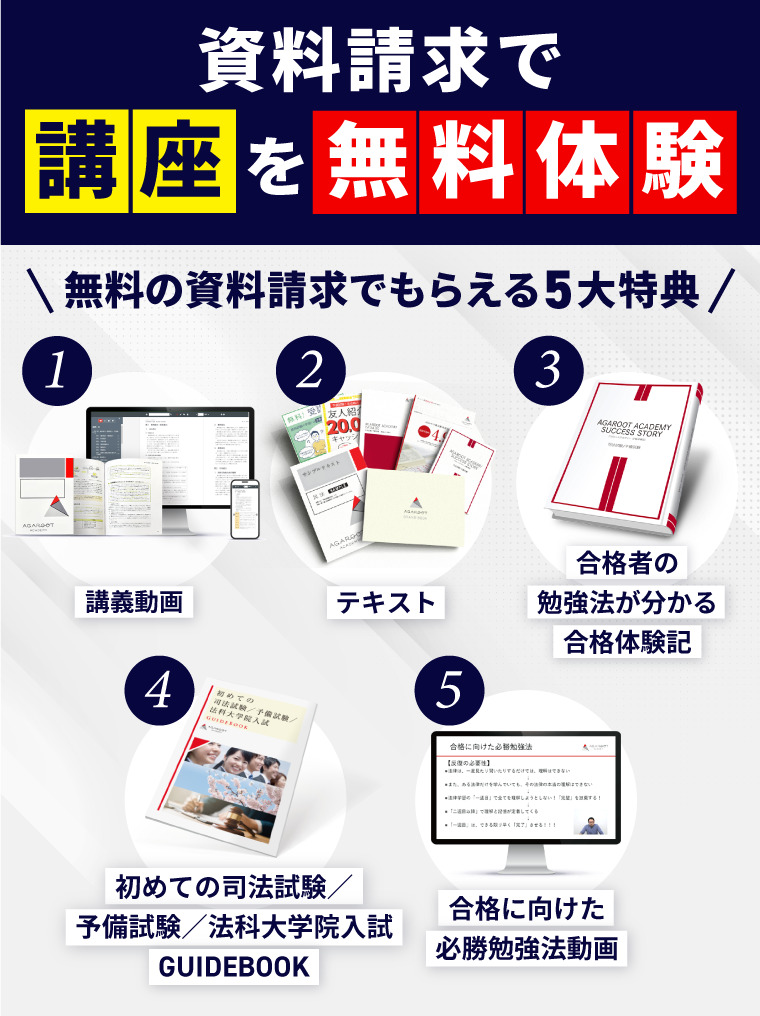
サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、
司法試験の勉強についていけるかを試せる!
「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、司法試験のすべてがわかる!
600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!
司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
【谷山政司講師が動画で解説!】
アガルートアカデミー司法試験の谷山政司講師が、司法試験・予備試験に独学で合格するのが難しい理由を丁寧に解説します。
確かに独学で合格した方は確かにいます。ただ、かなり難しいことも事実です。上手に予備校を利用していきましょう!
関連コラム:司法試験の難易度・合格率をアガルート講師がお答えします
なぜ独学で司法試験・予備試験に合格することが難しいのか
一般に独学で司法試験・予備試験に合格することは極めて難しいと言われていますが,その理由は,大きく分けて以下の4点にあります。
①法律そのものが難しい
専門用語が難しい
独学で予備試験の合格を目指す場合,大学教授(学者)が執筆した基本書と呼ばれる本や予備校が出版しているテキスト(学者が執筆した基本書等を受験向けにまとめたもの)を利用することになります。
しかし,それらを手に取って読んでみるとわかりますが,専門用語が羅列されており,大変難解です。
最近の基本書には,専門用語の説明が丁寧になされているものも出てきてはいますが,そうはいっても,これを独力で理解するのは容易ではありません。
例えば,民法における「善意」は通常の用語法(「好意,親切」といった意味)と異なる意味で用いられますが,文脈によって,「知らない」という意味で用いる場合もあれば,「積極的に信頼する」という意味で用いる場合もあります。
また,言い回しも独特で難しいので,おそらく一読しただけでは,そこに何が書いてあるのかすら分からないという場合もあると思います。
まず,この点が法律そのものの難しさの1つです。
ちなみに,予備校のテキストは,基本書に比べればわかりやすいものの,これをまとめたものにすぎませんので,結局難解な用語が並べ立てられていることには変わりがありません。
「行間を読む」ことが難しい
仮に,そこに書いてある内容が何となく分かったとしても,それではまだ足りません。
どうしてかというと,法律の世界では,「行間を読む」ことが必要だと言われているからです。
「行間を読む」とは,主に議論の蓄積を読み解くことをいいます。
基本書は,その著者の先生が,自分の学問の体系に沿って,自分の研究やこれまでの法律の議論をコンパクトにまとめたものです。
ある事項についてのその先生の研究の過程では,他の先生の研究の成果や諸外国における研究の成果が参考にされています。
ある一つの事項をとってみても,何十何百という論文が参照され,議論が蓄積されているのですが,基本書ではそれが数行,数ページに収められているのです。
当然基本書の記述だけでは,語りつくせません(ほとんどの基本書には,脚注で参照文献が挙げられているのもそのためです)。
そのため,基本書には,ある事項についてA説はこう考える,B説はこう考えると書かれているのですが,それだけを読んでもなぜそれが議論されているのか,見解の対立点はどこなのか,よくわからないことがあります。
そこで,その議論の背景を知るために,また別の基本書なり,専門論文なりを読み込む必要があるのです。
しかし,いずれにしても,法律学習を開始して間もない方にそんな高度な芸当などできるはずもありません。
文字通りの「行間」には空白しかないからです。
人によって言っていることが違う
法律の世界では,同じ事柄であっても,基本書によって説明の仕方が異なることがあります(特に,刑法総論など理論面で学説の対立が多い科目)。
例えば,ある事項について,「○○説が通説だ」と書いてある本もあれば,「○○説は有力説だ」と書いてある本もあります。
そもそも○○説がある基本書には書かれていてある基本書には書かれていない,書かれてはいるものの○○説の呼び方や整理分類の仕方が基本書によって異なるといったこともあります。
実際に,説明や分類の仕方によって,具体的な事件の結論が異なることはあまり多くはないのですが,その結論に至る説明の仕方がいくつもあるので(そして,そのどれも誤りではないので),人によって言っていることが違う,ということがあるのが法律の世界です。
学習が進むにつれて,「だいたいこの辺りの考え方が相場なのだな」,と肌感覚でつかめてくるものなのですが,学習を始めて間もない頃は戸惑うことも多くあると思います。
②試験範囲に対応した「教科書」がない
上記のように,基本書は,司法試験のために書かれたものではなく,著者の研究の成果をまとめるために書かれたものです。
そのため,司法試験や予備試験の問題はその中からだけ出題されるというわけではありません。
では,どうするかといえば,複数の基本書を読み比べたり,最高裁判所の判例を解説した判例集,学者の先生が執筆した論文,法学雑誌など,司法試験や予備試験に関係のありそうな文献を読み漁ったりすることになります。
当然ながら,すべて読むことはできませんので,試験に出題されそうな範囲や分野を特定し,優先度をつけていきます。
どうやって優先度をつけるのかといえば,一番の素材は過去問です。
論文式試験,短答式試験で出題された過去問を分析し,出題頻度を割り出して,優先度をつけていきます。
しかし,過去問を分析するといっても,それを独力で行うのは非常に手間がかかります。
過去問は,問題だけであれば法務省のホームページからすぐに手に入るのですが,解答がついているわけではありません。
短答式試験では,法務省から「正解」が発表されますので,分析はそこまで難しくありません。
法務省から発表された「正解」をもとに,各予備校から,解説付きの過去問集が市販されていますから,それを用いれば短答式試験で問われている知識が何なのかを知ることができます。
これに対して,論文式試験は,下記のように「正解」がありません。
論文式試験でも,解説・解答付きの過去問集は出版されているのですが,その解説・解答が正しいのかは自分の力で判断するしかありません。
過去問の分析一つをとっても難しいのが,司法試験や予備試験なのです。
その上で,さらにその過去問の分析を踏まえて,司法試験で問われることだけに特化した「教科書」を作ろうとなると,これはもう大変な作業です。
特に,講義と異なり,文字だけで説明しつくそうと思うと,何倍ものボリュームが必要となるので,なおさら難しくなります。
そのようなわけで,司法試験で出題されることだけに特化した「教科書」は,市販されていないのが現状です。
関連コラム:司法試験・予備試験におすすめ基本書32冊【7科目・目的別】
③論文式試験に対応できない
論文式試験には「正解」がない
実は,法律の論文式試験には「正解」がありません。
「六法があるのだからそれを見ればいいじゃないか。」と思われるかもしれませんが,条文に書いていないけれども重要だとされている事項はたくさんありますし,条文があったとしても,その条文がどういう意味なのか,意見が分かれることもよくあります。
ちなみに,短答式試験では,見解に対立がある場合,最高裁判所の判例が「正解」であるとされています。
しかし,判例にも様々な読み方がある場合があり,またそれに対して批判的な学者の意見がある場合もあるので,論文式試験の場合,一概にそれが「正解」だということもできません。
仮に,判例が「正解」だとしても,実は司法試験や予備試験の論文式試験では,「正解」が直接問われることは多くありません。
最高裁判所の判例が出された事件と似たような事例が出題されることもありますが,出題者も巧妙で,その事件とは,微妙に問題をズラしてきているので,判例が述べたことをそのまま書けば「正解」ということにはなりません。
もっとも,全く「正解」がないのだとすると採点のしようがありません。
そこで,こういう考え方が成り立つだろうというある一定の筋道があり,それのどれかにヒットすればひとまず「正解」とみなされる,そういう形で採点されています。
例えば,最高裁判所の判例が判断した事件と似たような事例が出題された場合,「判例はあの事件でこういう風に述べていたな。
だったら,最高裁判所なら,目の前の問題では,こういう風に述べるんじゃないかな?」といったように,論理でストーリーを作っていきます。
そのストーリーの作り方は人によって違う場合があるのですが,「まぁそういうストーリーもあるよね」というものであれば,ひとまず「正解」とされるというわけです(もちろんストーリーの出来不出来によって点数には差が出るでしょう)。
論文式試験は知識だけでは解けない
論文式試験は,条文や判例という知識を法学の身に着けただけでは,問題を解くことはできません。
司法試験をはじめとする各種試験では,条文や判例をそのまま使うだけで解ける問題はまず出題されません。
多くの問題では,身に着けた知識を何らかの形で応用しなければなりません。
司法試験や予備試験で出題されるような難しい問題になればなるほど,応用の度合いも高くなってきます。言葉を換えていえば,インプット(身につけた知識)とアウトプット(論文式試験への解答)の距離が広がっていくのです。
具体例を1つ挙げましょう,以下の問題は,平成23年度の予備試験で出題された民法の問題です。
Aは,平成20年3月5日,自己の所有する甲土地について税金の滞納による差押えを免れるため,息子Bの承諾を得て,AからBへの甲土地の売買契約を仮装し,売買を原因とするB名義の所有権移転登記をした。次いで,Bは,Aに無断で,甲土地の上に乙建物を建築し,同年11月7日,乙建物についてB名義の保存登記をし,同日から乙建物に居住するようになった。
Bは,自己の経営する会社の業績が悪化したため,その資金を調達するために,平成21年5月23日,乙建物を700万円でCに売却し,C名義の所有権移転登記をするとともに,同日,Cとの間で,甲土地について建物の所有を目的とする賃貸借契約(賃料月額12万円)を締結し,乙建物をCに引き渡した。この賃貸借契約の締結に際して,Cは,甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知っていた。
その後,さらに資金を必要としたBは,同年10月9日,甲土地をDに代金1000万円で売却し,D名義の所有権移転登記をした。この売買契約の締結に際して,Dは,甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知らず,それを知らないことについて過失もなかった。
同年12月16日,Aが急死し,その唯一の相続人であるBがAの一切の権利義務を相続した。
この場合において,Dは,Cに対し,甲土地の所有権に基づいて,甲土地の明渡しを求めることができるかを論ぜよ。
この記事を読んでいる方のほとんどは法律学習経験がないか,まだ始めたばかりという方だと思いますので,内容的な部分は無視してください。
この問題で問われている事項の1つは,「他人物賃貸借と相続」という事項なのですが,通常,これはそのままの形では学習しません。
これは基本書でも予備校の入門講座・基礎講座でもそうです。
では,どうするのかというと,自分が知っている似た事項からヒントを得て応用するのです。
上記の「他人物賃貸借と相続」と似た事項に「他人物売買と相続」というものがあります。
これは,基本書にも書かれていますし,予備校の入門講座・基礎講座でも講義がされています。
そこで,この問題を解く際には,その知識を応用する必要があります。
これが,論文式試験の難しさなのです。
自分が身に着けてきた知識をその場でアレンジすることが求められます。
そのためには,「ああ,あれに似てるな」「こう考えたらいいんじゃないかな」という気づきの力,思考の瞬発力が必要です。
このような力を鍛えるには,論文式試験の解き方を学んだ上で,問題をたくさん解いて,身に着けた知識と目の前にある問題を結びつける訓練をしなければなりません。
これらが,独学の受験生にとっての高いハードルとなります。
市販されている本で,「正解」らしいストーリーを紡ぎだす力,応用問題に対応するための思考の瞬発力の鍛え方を解説したものがないからです。
④学習が続かない
上記のような理由で,独学の受験生にとっては,司法試験・予備試験の合格のために何を勉強してよいかがわからない,自分が勉強していることが合格のために役に立っているのかがわからないという,いわば迷いの森をさ迷い歩く様な状態,五里霧中といった状態となります。
そのため,モチベーションが維持できず,途中で学習を止めてしまうという方が大勢いらっしゃいます。
そのような場合は,改めて予備校の入門講座からやり直すか,受験そのものを止めてしまうかの2択になります。
後者だとしたら法曹への夢を諦めるという非常に残念な結果に終わってしまいますし,前者だとしても独学で悪戦苦闘している時間は無駄だったとしか言いようがありません。
関連コラム:司法試験予備試験に1年で合格する勉強法
司法試験の入門講座・基礎講座を受講するメリット
今までお話した独学のデメリットをカバーするために開発されたのが司法試験予備校の入門講座・基礎講座です。
入門講座・基礎講座の特長は予備校によりますが,上記の独学のデメリットをカバーしているという点では共通しているといえます。
①法律用語をかみ砕いて説明してくれる
入門講座・基礎講座を担当する予備校の講師は,「教育」のプロです。
受験生がどういうところで躓きやすいのか,どういうことを疑問に思いやすいのかを熟知しているため,自力で基本書を読んでいてはわからないような難解な法律用語もかみ砕いて説明します。
例えば,「善意」の意味は,この場合には「知らない」という意味で,この場合には「積極的な信頼」という意味だ,その理由は○○だ,「積極的な信頼」の有無が問題となる事案はこういう事案だと説明するわけです。
これによって,理解が進むだけでなく,圧倒的な時間の短縮につながります。
②試験で出題される知識(主に論文式試験用の知識)だけに絞って講義をしてくれる
司法試験予備校の講師は,過去の司法試験((新)司法試験・旧司法試験)や予備試験の論文式試験の問題を全て研究した上で,どのような知識がどのような形で問われているのかを把握しています。
そのため,テキストに掲載する知識,講義で扱う知識は,試験で出題されるものに限定しています。
受講生は,テキストや講義という明確な羅針盤があるため,非常に効率よく知識を習得することができます。
③思考の瞬発力を培うことができる
それだけでなく,司法試験予備校の講師は,その知識がどのような形で試験に問われるのか,問われた場合にはどう対処すればいいのかという点まで踏み込んで解説します。
単に知識を身につけることができるだけでなく,自然と論文式試験に対応できる思考の瞬発力を培うことができるのです。
④学習を続けることができる
入門講座・基礎講座は大きく分けて,通学クラスと通信クラスの2種類があります。
通学クラスでは,定期的に講義が行われるため,それが学習継続の大きな助けになります。
一方で,通信クラスでは,講義がインターネット上で配信されるため,自分の都合のいい時間に受講することができる反面,サボりがちになってしまいます。
もっとも,最近の通信講座では,その点を克服するような仕組みが設けられていることが通常ですので,通学クラスとそん色なく学習を継続することができます。
アガルートアカデミーの入門講座・基礎講座「総合講義300」
アガルートアカデミーでは,入門講座・基礎講座として「総合講義300」を開講しています。
「総合講義300」は,法律を学習されたことがない方・法律知識が全くないという方を主な対象として,予備試験・法科大学院入試はもちろんのこと,司法試験合格までに必要な全ての知識を,300時間で習得する法律の入門講座・基礎講座です。
オリジナルフルカラーテキストは,工藤北斗講師が,新旧司法試験の過去問,予備試験の過去問を全て研究しつくした上で,司法試験合格のために必要な知識だけで構成したものです。
講義では,テキスト掲載の知識を全て解説するのはもちろんのこと,実際に過去に出題された新旧司法試験や予備試験の論文式試験の問題を使って,どのような形で知識が問われているのか,どう対処すればいいのかという点まで解説します。
また,学習継続の仕組みとしてプロ講師による月1回の定期カウンセリングを設けています。
分からないこと,不安なことは何でも講師に質問することができます。
これから司法試験の合格を目指して学習を開始しようという方は,ぜひ「総合講義300」をご検討ください。
それでも独学合格を目指したい人への勉強法アドバイス
以上のように、独学で予備試験に合格することは難しく、合格者の大半が予備校を利用しているというのが実情ではあります。しかし、独学で合格することが決して不可能というわけではありません。
そこで、以下では、独学合格を目指す場合のいくつかのポイントを紹介いたします。
ポイント①「対象の限定と反復」
独学の方に特におすすめしたい学習のポイントは「対象の限定と反復」です。
法律学習の範囲はその性質上無限に拡げる事ができますが、予備試験には、出題可能性が高い分野とそうでない分野が存在します。したがって、試験に出題される可能性がある部分に対象を「限定」する必要があります。また、人間は、「思い出す」回数が多ければ多いほど、理解と記憶の精度が上がると言われています。そして、「思い出す」回数を増やすということは、「反復」を増やすということです。短期合格者であればあるほど、短期間で「反復」を行っています。
ポイント②「アウトプット」をおろそかにしない
独学で学習をされている方の特徴として、「実際に論文答案の作成を始める時期が遅い」という点が挙げられます。
そのような方は、まずは、インプットテキストをじっくりと読み込んでからでないと答案が書けない、あるいは、答案を書いてはいけないと思い込んでいることが多いです。
しかし、インプットの目的はアウトプットのためであり、すなわち、論文式試験でいえば、合格答案を作成するためなのです。そのためには、学習開始の段階から、できる限り論文答案の作成を行うべきです。もちろん、学習開始時点では、思った通りには答案を作成できないことでしょう。
しかし、その経験を経ることにより、「合格答案を書けるようになるためには、今何が足りていないのか」を把握することができ「その足りていないものを埋めるためには、何をどのようにインプットすればよいのか」が分かるのです。つまり、本当のインプットは、アウトプットを経た後に始まるのです。スポーツでも、例えば野球がうまくなりたかったら、まず最初にバットとボールを握って、実際に野球をやってみて、足りないものを把握して、それを埋めるトレーニングをするでしょう。
これと構造は全く同じなのです。
ポイント③「適切な」情報収集と現状把握
上記のように、予備試験は「試験」である以上、試験に出やすい部分を重点的に押さえていくことが正しい戦略と言えます。
そのためには、まず情報を収集し、皆が使っているテキストや問題集が何であるかを学習開始前に徹底的にリサーチをして、学習の対象を限定する作業が必要です。
また、法律の試験である以上、法改正や、新判例についてもアップデートすべきです。
これらの情報については、インターネットがこれだけ普及した昨今においては、すぐに検索可能ですし、SNSの発達により、受験生や合格者に質問・確認をすることもできますから、これは積極的に利用しましょう。
ただし、情報収集を積極的に行うことと、そこから得られた情報を無条件に取り入れるということは別の問題です。特に、適切なテキストを用いて、適切な勉強方法で学習できていたにもかかわらず、SNSの情報に流されすぎてしまって、新しいテキストや学習方法を何の疑いもなく取り入れてしまった結果、いつまでたっても試験で使える知識が定着しない、論文が欠けるようにならないという方を非常に多く見かけます。
情報収集は、常に自己の現状を把握して、試験合格の観点から不足している部分を補う形で行うべきです。敵を知ることと、己を知ることを常に並行しながら学習を続けることが極めて重要です。
司法試験・予備試験の受験を
検討されている方へ
- 司法試験の勉強についていけるか不安
- 司法試験に関する情報を漏れなく手に入れたい
- 司法試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
このような悩みをお持ちでしたら
アガルートの無料体験を
ご活用ください

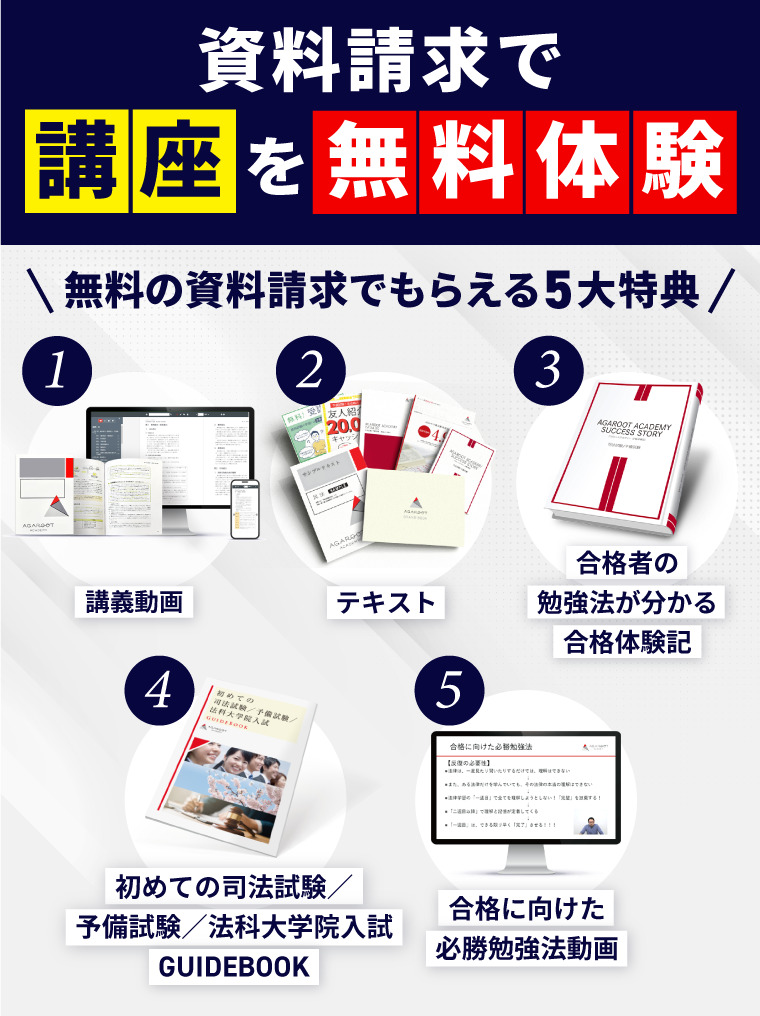
サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、
司法試験の勉強についていけるかを試せる!
「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、司法試験のすべてがわかる!
600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!
司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る
この記事の著者 谷山 政司 講師
平成23年度に(新)司法試験に合格後、伊藤塾にて主に予備試験ゼミを中心とした受験指導業務を担当。
谷山ゼミ受講者のうち、およそ70名ほどが予備試験に合格。谷山ゼミ出身者で、最終的な予備試験の合格率は7割を超える。
自身の受験経験だけでなく、答案の徹底的な分析やゼミ生への丁寧なカウンセリングの結果確立した論文作成ノウハウをもとに、アウトプットの仕方はもちろん、インプットの仕方までをも指導するスタイルは、ゼミ生の圧倒的支持を受けた。
また、期をまたいだゼミ生の交流会等を定期的に行うなど、実務に出た後のフォローも積極的に行っている。
谷山講師の紹介はこちら
ブログ:「谷山政司のブログ」
Twitter:@taniyan0924