労働基準監督官とは?仕事内容・試験科目・難易度等を解説します
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

「労働基準監督官試験の難易度はどの程度なの?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。
労働基準監督官試験は、県庁や市役所などの一般的な公務員試験よりも難易度が高いため、かなりの勉強量が求められます。
こちらの記事では、労働基準監督官の仕事内容や試験概要、難易度等について解説していきますので、労働基準監督官を目指している方は参考にしてください。
公務員を目指している方へ
- 国家一般職・専門職や地方公務員になりたいけど何から始めていいかわからない
- なるべく試験対策にかかる費用を抑えたい
- 学校や仕事と試験勉強を両立できるか不安
アガルートの公務員試験講座を
無料体験してみませんか?
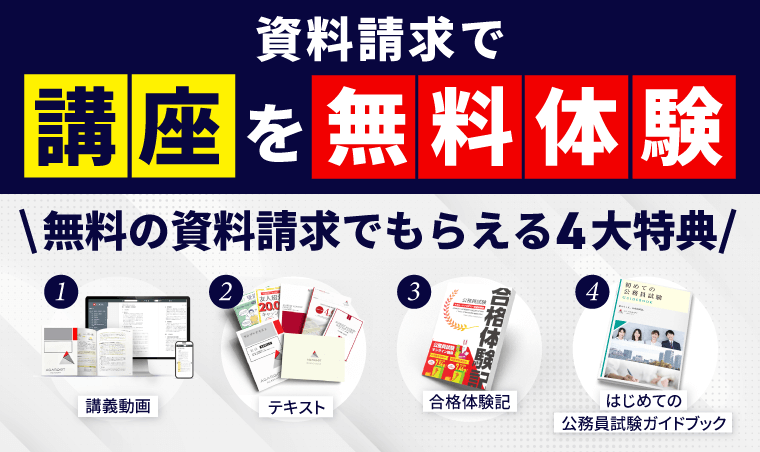
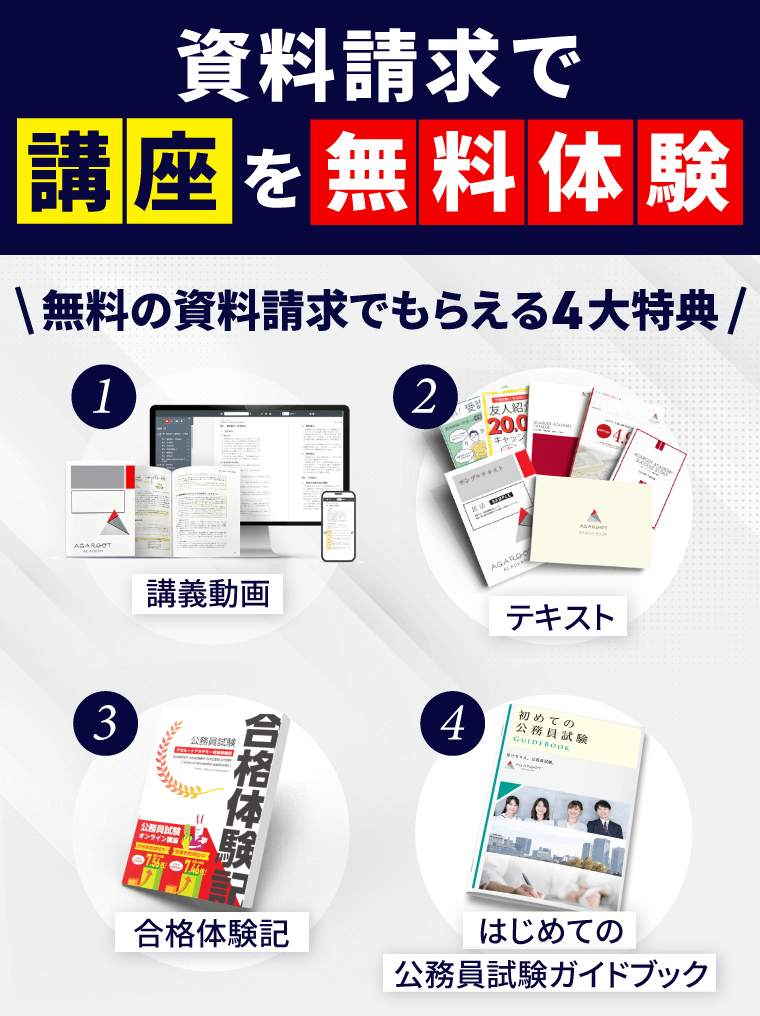
約3時間分のミクロ経済学・数的処理対策などの講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!公務員試験のフルカラーテキスト
公務員試験の全てがわかる!はじめての公務員試験ガイドブック
実際の試験問題が解ける!「実践ミニ問題集」がもらえる!
地方上級・一般職合格者の「面接再現レポート」がもらえる!
1分で簡単!無料!
▶資料請求して特典を受け取る目次
労働基準監督官とは
労働基準監督官は、厚生労働省に属し、労働行政を支える役割を果たす国家公務員です。
労働基準法、労働安全衛生法などに基づいて、工場、事業場などに立ち入り、事業主に法に定める基準を遵守させることにより、労働条件の確保・向上、労働者の安全や健康の確保を図り、労働災害にあわれた方に対する労災補償の業務のほか、刑事訴訟法に規定する特別司法警察職員としての職務を行います。
厚生労働省に勤務する他の公務員との大きな違いは、労働政策の立案よりも、労働者と事業者のトラブルの解決、労働災害の予防、労働災害の調査など、現場での仕事がメインであることです。
労働行政における警察官、労働Gメンをイメージしていただくといいかもしれません。
労働基準監督官の仕事内容
労働基準監督官の業務は大きく分けて、「司法警察業務」、「安全衛生業務」、「労災保障業務」に分類できます。
司法警察業務
「司法警察業務」は、法令違反の労働行為に対して、捜査、逮捕、差し押さえなどのほか、事件捜査を行ったあとの送検といった業務です。
この労働基準監督官が有する権限は、特別司法警察職員と呼ばれ、一般司法警察職員(いわゆる警察官)よりも専門の犯罪分野に詳しい警察官という位置付けですが、権限は一般の警察官と変わりません。
安全衛生業務
「安全衛生業務」は、労働災害が発生した際に災害の現場で、発生状況や原因を調査する業務です。
労災補償業務
「労災補償業務」は、業務・通勤中に不幸にも労働災害(負傷、傷害、疾病など)に遭った労働者に対し、保険給付のために必要な事実関係の調査を行う業務です。
ブラック企業、ブラックバイトという言葉が使われて久しい日本の労働事情からすると、労働基準監督官の活躍への期待は高まる一方です。
労働基準監督官の待遇
労働基準監督官の給料・福利厚生
労働基準監督官は国家公務員なので、行政職俸給表(一)に則って給料が決定します。
人事院の令和5年度国家公務員給与等実態調査によると、労働基準監督官の平均給与月額は404,015円、俸給は322,487円で、ここにボーナスが加わり平均年収は約666万円(約6,666,248円)でした。
※平均給与月額…俸給及び諸手当の合計
※平均年収は平均給与月額×12ヶ月+平均給与月額×4.5ヶ月(ボーナス)で算出
※出典:令和5年度国家公務員給与等実態調査
初任給は1級26俸で224,280円です。(地域手当なし:186,900円)
| 概要 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 俸給 | 186,900円 | 行政(一)1-26の場合 |
| 地域手当 | 37,380円 | 東京都特別区に勤務する場合 |
| 扶養手当 | 子月額10,000円 | 扶養親族のある者 |
| 住居手当 | 月額最高28,000円 | 借家(賃貸のアパート等)に住んでいる者 |
| 通勤手当 | 1箇月当たり最高55,000円 | 交通機関を利用している者 |
| 期末・勤勉手当 | 1年間に俸給等の約4.40月分 | 6月、12月に出るボーナス |
残業は時期によってまちまちですが、6~7月にかけての年度更新の時期や大規模な労災事故が発生した場合などは残業を覚悟しなければなりません。
とはいえ、労働行政としての性格を持っている特性上、ワークライフバランスの実現には積極的で、有給休暇が取れないという心配はありません。
労働基準監督官も国家公務員である以上、身分保障や福利厚生の充実は言うまでもありません。
労働基準監督官の勤務先・転勤
主な勤務先は厚生労働本省又は全国各地の労働局、労働基準監督署です。
数年に一度転勤のある全国型の勤務となります。
労働基準監督官のキャリア
転勤を繰り返し、さまざまな地域特性や産業構造の中で実務を経験できます。
実績が認められれば都道府県労働局長、労働基準監督署長へキャリアアップされる方もいます。
また、一定以上の経験によって国家資格である社会保険労務士の一部科目免除がされます。
なので、中には、勤務経験を積んだ後、社労士として民間への転職や、独立開業する方もいます。
労働基準監督官としての実務経験を有することは、社会保険労務士としても非常なアドバンテージとなりますので、将来の選択肢としても有望です。
労働基準監督官の試験制度
それでは、労働基準監督官試験の試験制度の概要について解説していきます。
令和5年度(2023年度)国家専門職(大卒程度)試験日程
| 試験内容 | 日程 |
|---|---|
| 受付期間 | 2024年2月22日(木)9:00~3月25日(月)※受信有効 ※申込みはインターネットにより行ってください。 |
| 第1次試験日 | 2024年5月26日(日) |
| 第1次試験合格者発表日 | 2024年6月18日(火)9:00 |
| 第2次試験日 | 2024年7月9日(火)~7月12日(金) |
| 最終合格者発表日 | 2024年8月13日(火)9:00 |
※第2次試験日の日程は、第1次試験合格通知書で指定する日時です。
※第2次試験日の日時の変更は原則として認められません
※出典:労働基準監督官採用試験|国家公務員試験採用情報NAVI
労働基準監督官の受験資格
労働基準監督官試験の受験資格、は下記の通りです。
- 受験年度の4月1日の時点の年齢が21歳以上30歳未満の者
1994(平成6)年4月1日~2003(平成15)年4月1日生まれの者 - 受験年度の4月1日の時点の年齢が21歳未満の者で、次に掲げる者
2003(平成15)年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
(1)大学を卒業した者および受験年度の3月までに卒業する見込みのある者
(2)人事院が(1)と同等の資格があると認める者
基本的に日本国籍を有し、年齢要件さえ満たしていれば受験資格はクリアできます。
学歴制限はありません。試験で問われる内容は大学卒業レベルですが、中卒でも高卒でも受験できます。
学習方法さえ間違えなければ、学歴・学部に関係なく筆記試験の突破は不可能ではありません。
興味と意欲のある方はぜひ、チャレンジしてください。
試験科目・出題数
| 試験 科目 |
内容 | 配点 比率 |
解答 時間 |
|
| 1次試験 | 基礎能力試験 | 40題 知能分野 27題(文章理解⑪、判断推理⑧、数的推理⑤、資料解釈③) 知識分野 13題(自然・人文・社会⑬(時事を含む。)) |
2/7 | 2時間20分 |
| 専門試験 (択一) |
《労働基準監督A》 48題出題、40題解答 ■必須 12題 労働法⑦ 労働事情(就業構造、労働需給、労働時間・賃金、労使関係)⑤ ■選択 次の36題から28題選択 憲法、行政法、民法、刑法⑯ 経済学、労働経済・社会保障、社会学⑳ 《労働基準監督B》 46題出題、40題解答 ■必須 8題 労働事情(就業構造、労働需給、労働時間・賃金、労使関係、労働安全衛生)⑧ ■選択 次の38題から32題選択 工学に関する基礎(工学系に共通な基礎としての数学、物理、化学)㊳ |
3/7 | 2時間20分 | |
| 専門試験 (記述) |
《労働基準監督A》 2出題、2題解答 労働法① 労働事情(就業構造、労働需給、労働時間・賃金、労使関係)① 《労働基準監督B》 4~6題出題、2題解答 ■必須 工業事情1題 ■選択 工学に関する専門基礎(機械系、電気系、土木系、建築系、衛生・環境系、応用化学系、応用数学系、応用物理系等の工学系の専門工学に関する専門基礎分野)から3~5題出題し、うち1題選択 |
2/7 | 2時間 | |
| 2次試験 | 人物試験 | 人柄、対人的能力などについての個別面接 | * | − |
| 身体検査 | 主として胸部疾患(胸部エックス線撮影を含む。)、血圧、尿、その他一般内科系検査 | * | − |
・第1次試験合格者は、「基礎能力試験(多肢選択式)」と「専門試験(多肢選択式)」の成績を総合して決定します。「専門試験(記述式)」は、第1次試験合格者を対象に評定した上で、最終合格者決定に当たり、他の試験種目の成績と総合します。
・第2次試験の際、人物試験の参考とするため、性格検査を行います。
・「配点比率」欄に*が表示されている試験種目は、合否の判定のみを行います。
労働基準監督の採用倍率は2.4~3.8倍程度【2023年】
| 区分 | 受験者数 | 第二次試験 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 労働基準監督A (法文系) | 1,146 | 776 | 298 | 3.8倍 |
| 労働基準監督B (理工系) | 273 | 136 | 115 | 2.4倍 |
| 計 | 1,419 | 912 | 413 | 3.4倍 |
難易度・試験の特徴
労働基準監督官試験は、第一次試験と第二次試験に分かれています。
第一次試験は
- 基礎能力試験(多肢選択式)
- 専門試験(多肢選択式)
- 専門試験(記述式)
に分かれており、いずれもは大学卒業レベルです。
労働法や労働事情に関する問題が必須解答となっている点が、他の公務員試験との大きな違いと言えるでしょう。
法文系である「労働基準監督A」では専門試験の中で労働法・労働事情が必須解答となっており、理工系である「労働基準監督B」では専門試験の中で労働事情・工学に関する問題が必須解答となっています。
試験そのものの難易度が高いことに加えて、専門性の高い内容が問われることを考えても、難易度はかなり高いことが分かります。
面接について
面接対策は、他の公務員試験と同様に、
- 「なぜ労働基準監督官を目指したのか」
- 「労働基準監督官の仕事内容は知っているか」
などの志望動機に関しては必ず聞かれると思ってください。
その上で、
- 「専攻科目は何か」
- 「労働基準監督官としてどのような仕事をしていきたいか」
などが問われることを想定しておくと良いでしょう。
労働法や労働事情に関心を持っていることはもちろん、労働基準監督官に求められる資質である「責任感を持って仕事に取り組めるか」「正義感を持って人と接することができるか」がチェックされます。
これまでの経験を振り返りながら、上手に志望動機と絡ませることで魅力的で説得力のある受け答えができるようになるはずです。
※関連コラム:国家公務員「専門職」とは?種類一覧・試験制度・日程・難易度を解説
最後に
労働基準監督官は一般的な公務員試験よりも難易度が高いので、興味がある方は一歩踏み込んだ努力が求められます。
しかし、労働法を勉強した経験がある方や労働事情に詳しい方にとっては大きなアドバンテージとなるので、興味がある方は紹介した内容を参考にしながら、ぜひチャレンジしてみてください。
公務員を目指している方へ
- 国家一般職・専門職や地方公務員試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの公務員試験講座を
無料体験してみませんか?

令和5年度公務員試験内定者210名!国家一般職専門職・地方上級の合格者を多く輩出!
フルカラーのオリジナルテキストがスマホやタブレットで閲覧可能!
学習の相談や質問が気軽にできる充実したフォロー制度!
内定特典でお祝い金贈呈or全額返金!
9月8日までの申込で20%OFF!
▶公務員試験講座を見る※2024年合格目標
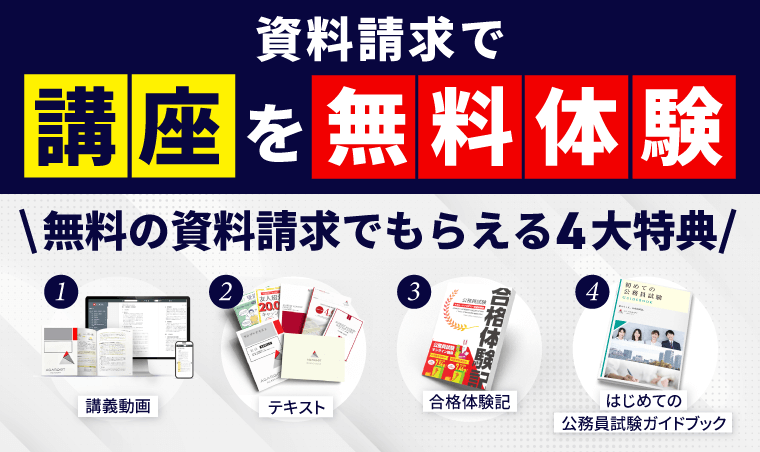
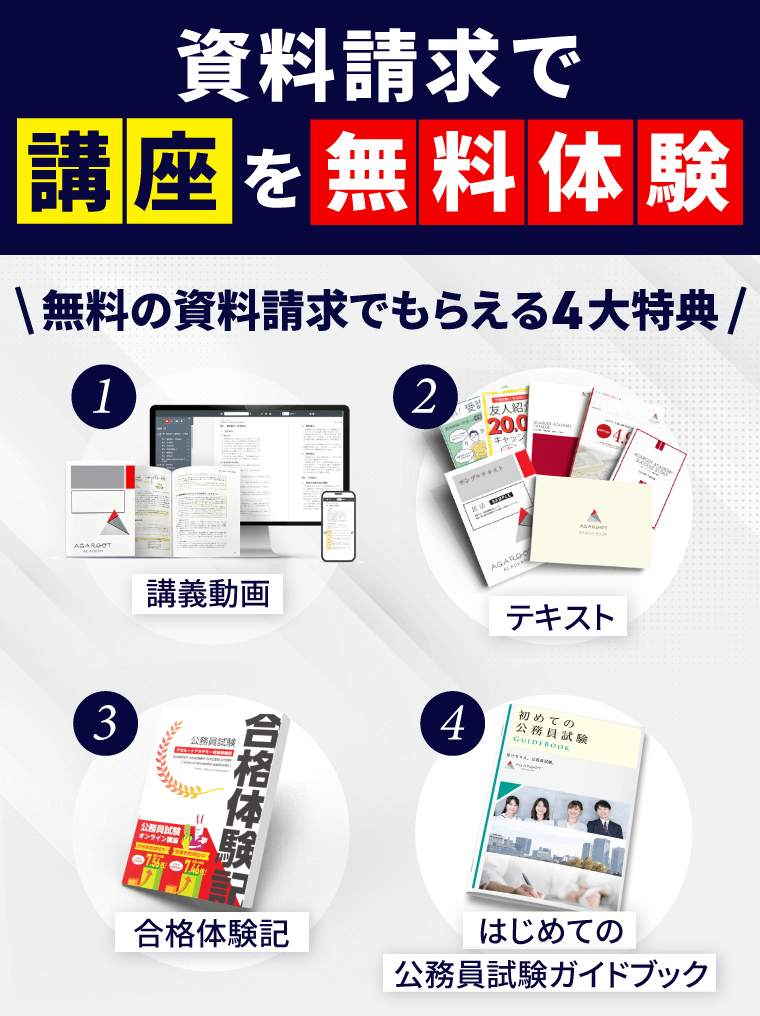
約3時間分のミクロ経済学・数的処理対策などの講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!公務員試験のフルカラーテキスト
公務員試験の全てがわかる!はじめての公務員試験ガイドブック
実際の試験問題が解ける!「実践ミニ問題集」がもらえる!
地方上級・一般職合格者の「面接再現レポート」がもらえる!
1分で簡単!無料!
▶資料請求して特典を受け取る




