土地家屋調査士試験の免除とは?測量士補試験合格で「午前の部」を避けるべき理由
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

土地家屋調査士の受験生の大多数は午前免除を受けています。
これから土地家屋調査士を目指そうとしている人の中には、「午前免除って何?」と疑問に思っている方がいると思います。
なぜ午前免除を受けているのか、その理由とどの資格を持っていたら午前免除を受けることができ、またその中でどの資格を取得するのがオススメなのかをご紹介していきます。
土地家屋調査士・測量士補試験合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 土地家屋調査士・測量士補試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの土地家屋調査士・測量士補試験講座を
無料体験してみませんか?


約10.5時間分の土地家屋調査士&約2時間分の測量士補の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!土地家屋調査士・測量士補試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
土地家屋調査士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
『合格総合講義 民法テキスト』をまるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る土地調査士試験「午前の部」とは?
土地家屋調査士試験の試験科目には、午前の部と午後の部があります。
一日かけて試験して大変そうだなと思ったかもしれません。
しかし、実はある特定の資格を持っていたら、午前の部の試験は科目免除されます。
実質的に午後の部のみになります。
では、そもそも午前の部とはどういった試験なのか、情報を以下にまとめていきます。
午前の部は、
・試験時間:2時間(午前9時30分から午前11時30分まで)
・試験内容:土地及び家屋調査の調査及び測量に関する知識及び技能であって、次に掲げる事項
ア 平面測量(トランシット及び平板を用いる図根測量を含む。)
イ 作図(トランシット及び平面を用いる図根測量を含む。)
となってます。
試験問題としては択一問題が10問と図面作成が1問出題されます。
多くの受験生が「午前免除」を受ける理由
最初に説明しましたが、多くの受験生が午前免除を受けています。
私もそうでしたが、測量士補という資格を持っていたので午前免除を利用していました。
逆に午前の部を受けている人はわずかです。
土地家屋調査士試験を管轄している法務省で試験の結果が公表されており、得点別員数表(何点の人が何人いるのか、平均点、受験者数)を誰でも確認することができます。
令和6年度の午前の部受験者は85人です。4500人近くの受験者数がいるのに。
ではなぜ午前免除がセオリーになっているのか?その理由を以下に説明していきます。
理由1 午前の部の試験内容が難しい
あとでも説明しますが、午前免除の資格でおすすめな測量士補より午前の部における択一問題のレベルは高く、図面作成も求められます(測量士補は択一問題のみ)。
さらに午前の部を勉強しようにも、それに関するテキストや問題集というものがほとんどなく、勉強する環境が整っていません。
理由2 体力・精神力的に不利
大多数の人が午前中、体調を整えて、万全の態勢で午後の部を受験します。
一方、午前免除していない受験生は朝の2時間を集中してエネルギーを使った後に、午後の部に臨みますので大きなハンデを生んでしまうことになります。
土地家屋調査士試験にとって、午前免除をするのが定石だということが分かって頂けたかと思います。
午前の部が免除される資格
では、どういった資格を持っていれば、午前の部が免除されるのか?
その資格とは測量士、測量士補、一級建築士もしくは二級建築士となります。
その中でもどの資格を取得するのがオススメかというと、測量士補の一択です。
ではそれはなぜかを以下にまとめていきます。
測量士補がオススメな理由1 試験の難易度が一番易しい
単純に合格率から見ても分かります。
測量士補は受験資格はなく、合格率は40パーセント前後です。
なお、アガルートアカデミーの測量士補講座の受講生は、毎年90パーセント後半の合格率となっております。
二級建築士では受験資格もあり、合格率は20パーセント前後です。
さらに二級建築士試験には学科と製図があり、学習する範囲も明らかに多いです。
測量士補がオススメな理由2 勉強した内容が活きる
測量士補と土地家屋調査士の試験内容は比較的近いところにあります。
実務においても測量というのはトータルステーションなどの測量機器で距離と角度を測定し、座標を計算します。
そして、土地の広さがどれくらいあるのかなどを算出します。
土地家屋調査士としての実務において測量の知識と技術は大変重要です。
測量士補は5月に土地家屋調査士は10月に試験が実施されるので1年でのタブル合格も目指せます。
「えっ、二つの資格も取得するのは大変そう」と思うかもしれませんが、しっかりとスケジュール調整ができれば、十分可能です。
具体的なダブル合格の秘訣は、以下の動画で解説しているため、ぜひご視聴ください。
学習の軸とするのは土地家屋調査士の勉強で、測量士補は3~4ヶ月の学習期間で間に合います。
例えば、年内まで土地家屋調査士の基礎的部分を学習して、年が明けてから、測量士補との勉強を並行して行い、5月の試験が終わったら、10月の本試験に向かってラストスパートです。
皆さん、ダブル合格目指してみませんか。
測量士補と土地家屋調査士の勉強スケジュール2パターン
測量士、測量士補、1級建築士、2級建築士のいずれかの試験に合格していると、土地家屋調査士試験の午前試験の免除を受けることができます。
特に、難易度の点からも、測量士補試験を取ってから土地家屋調査士試験の受験をすることが一般的です。
測量士補試験の受験日が5月、土地家屋調査士試験の受験日が10月となっていますので、1年間を通じて両方の資格の取得を目指すことができます。
もちろん、両方の資格を取得するためには、両方の資格の学習をしなければなりません。
学習のスケジュール調整が重要になってきます。
それでは、お勧めする学習スケジュールを2つ挙げます。
(1)測量士補の学習を一旦行い、全体を把握した後、土地家屋調査士試験の学習を始める
まずは、(1)「測量士補の学習を一旦行い、全体を把握した後、土地家屋調査士試験の学習を始める」というものです。
アガルートのホームページにあるスケジュールですね。

アガルートの測量士補総合講義では、テキストのページごとに過去問の肢別索引がついています。
そのため、学習の進捗に合わせてすぐに過去問によるアウトプットをすることができます。
この索引は、すべての年度の全ての問、全ての肢が入っているため、インプットをすべて終えると同時に、すべての過去問のすべての肢を1度解くことができます。
講義を聞いた直後ならば楽に過去問を解くことができるため、低い労力で「すべての過去問を解いたという経験」を得ることができます。
1度解いていますから、あとは、本試験まで「忘れない程度」に過去問を続けていきます。忘れない程度でよいので、土地家屋調査士のインプットに十分力を注ぐことができます。
土地家屋調査士のインプットをしつつ、測量士補試験の本番を迎え、その後は土地家屋調査士試験の学習に集中します。
(2)土地家屋調査士試験の学習を中心に、測量士補試験の学習は本試験直前にまとめる
次にお勧めする学習スケジュールは、(2)「土地家屋調査士試験の学習を中心に、測量士補試験の学習は本試験直前にまとめる」というものです。
学習スタートからずっと土地家屋調査士試験の学習を続け、測量士補の願書を出す前に、土地家屋調査士試験のインプットを終わらせます。
それぞれの学習経験や学習環境によって差はありますが、だいたい11月頃に学習を始める方にはこちらをお勧めしています。
測量士補を学習する前に土地家屋調査士のインプットが終わっているため、測量士補の学習をしながらでも土地家屋調査士のアウトプットをすることができます。
測量士補は願書を出した後、少しやってみて適正を見ます。
「できそう」だったら土地家屋調査士の分量を多くし、「無理そう」だったら測量士補の分量を多くしていきます。
このあたりは定期カウンセリングなどで中山と一緒に調整していきます。
いずれにせよ、測量士補を合格しないと土地家屋調査士試験に合格することが難しくなってしまうため、十分に安全にやっていきますが、なるべく土地家屋調査士試験の学習量を確保するという意識が重要です。
この2つのスケジュールはあくまでもモデルです。
皆さん、お1人お1人で「やれること」「やるべきこと」は異なるので、その辺りは測量士補試験・土地家屋調査士試験ダブル合格カリキュラムに無料でついてくる「定期カウンセリング」を使って、一緒に最適な学習スケジュールを考え、実行していきましょう。
午前の部の免除に関するよくある質問
以下は土地家屋調査士試験の午前の部の免除に関するよくある質問です。
- 科目免除を受けたあとの試験科目は?
- 免除を受けるために必要な手続きは?
- 免除が適用される他の資格の難易度は?
それでは、各質問について解説していきましょう
科目免除を受けたあとの試験科目は?
午前の部の免除を受けた場合、試験は午後の部の試験のみとなります。
午後の部の試験内容は以下のとおりです。
- 択一式:不動産登記法・民法他から20問出題
- 書式問題:土地・建物から各1問、計2問が出題
午後の部の試験時間は2時間30分です。
免除を受けるために必要な手続きは?
土地家屋調査士試験の午前の試験免除を受けるためには、以下のいずれかの証明書類が必要です。
【測量士・測量士補の証明書類】
- 測量士または測量士補の試験合格証書
- 登録通知書
- 登録証書
【1級・2級建築士の証明書類】
- 1級/2級建築士の試験合格証書(令和2年3月1日以降の試験に合格した方は資格証明書も必須)
- 免許証明書
なお、これらの証明書類の原本とコピー1枚を受験申請書に添付する必要があるため、忘れずに準備しましょう。
そのほかの証明書類については、最新の受験案内書で詳細をご確認ください。
申請方法は大きく分けて「持参(法務局または地方法務局)」「郵送」の2パターン。
時間がない場合は、目の前で不備を修正できるため、持参をおすすめします。
郵送で申請する場合は、証明書類の原本返信用封筒の用意が必要です。
自分の郵便番号・住所・氏名を記載し、書留料金を含んだ郵便切手を貼った封筒を申請書類と一緒に提出しましょう。
免除が適用される他の資格の難易度は?
土地家屋調査士試験の午前の部の免除が適用される資格は測量士補・測量士・一級建築士・二級建築士です。
各資格の平均合格率から難易度を比較しましょう。
| 資格 | 平均合格率 |
| 測量士補 | 21~47% |
| 測量士 | 5~15% |
| 一級建築士 | 8~11% |
| 二級建築士 | 22~26% |
上記の表から分かる通り、測量士補は、ほかの資格と比較して最も高い合格率を示しており、最も取得しやすい資格であるといえます。
なお、令和7年度試験の測量士補試験の合格率は51.2%でした。
測量士補は、測量業務において測量士の指導のもと、測量作業を補助する国家資格。
受験資格に制限はなく、誰でも受験可能です。
まとめ
なぜ土地家屋調査士試験を受験する多くの受験生が午前免除を受けているのか、その理由を解説してきました。
本コラムの要点は以下の通りです。
・午前の部は試験内容が難しく教材も少ないため対策が困難
・午前の部を免除できる資格は、測量士、測量士補、一級建築士、二級建築士
・特に測量士補は合格率が高く、受験資格も不要で取得しやすい
・測量士補の学習内容は土地家屋調査士試験にも活かせる
・測量士補試験は5月、土地家屋調査士試験は10月に実施されるため、1年でのダブル合格も可能
測量士補の資格を取得し午前の部の免除を活用することで、効率的に土地家屋調査士試験の合格を目指せます。
ダブル合格を目指すことも可能なので、事前に学習スケジュールを立て、計画的に進めていきましょう。
土地家屋調査士・測量士補試験の合格を
目指している方へ
- 土地家屋調査士・測量士補試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの土地家屋調査士・測量士補試験講座を
無料体験してみませんか?


約10.5時間分の土地家屋調査士&約2時間分の測量士補の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!土地家屋調査士・測量士補試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
土地家屋調査士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
『合格総合講義 民法テキスト』をまるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る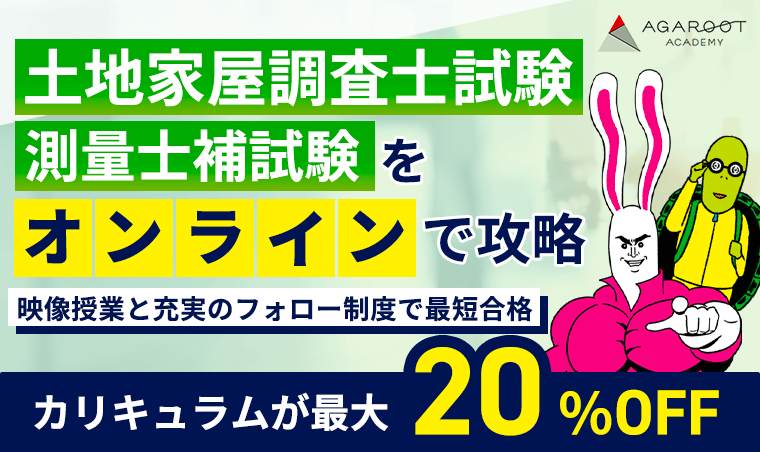
4年連続1位合格者輩出!
令和6年土地家屋調査士講座の
アガルート受講生の合格率63.64%!全国平均の約6倍!
追加購入不要!これだけで合格できる
カリキュラム
充実のサポート体制だから安心
合格特典付き!
会員20万人突破記念!
全商品5%OFF!

この記事の監修者 中山 祐介 講師
2008年 法政大学 文学部地理学科 卒業
2010年 東京都立大学 大学院 都市環境科学研究科 修了
2012年 土地家屋調査士試験を全国1位で合格(択一1位・書式2位)
2013年 測量士 登録
2014年 行政書士試験 合格
2015年 特定行政書士考査 合格
独学で土地家屋調査士試験全国総合1位合格の同試験を知り尽くした講師。
「すべての受験生は独学である」の考えのもと、講義外での学習の効率を上げ、サポートするための指導をモットーに、高度な知識だけでなく、自身の代名詞でもある複素数による測量計算([中山式]複素数計算)など、最新テクニックもカバーする講義が特徴。日々、学問と指導の研鑽を積む。
中山 祐介講師の紹介はこちら



