宅建の試験日や申し込みについて!2024年(令和6年)最新
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

宅建試験は国土交通省が試験主体となり、一般財団法人不動産適正取引推進機構を指定試験機関として実施するもので、2024年(令和6年)は10月20日(日)に試験が行われます。
当コラムでは、2024年度(令和6年度)の宅建の試験日のみならず申し込み方法やその際の注意点などについても見ていきます。
宅建試験合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 宅建試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの宅建試験講座を
無料体験してみませんか?
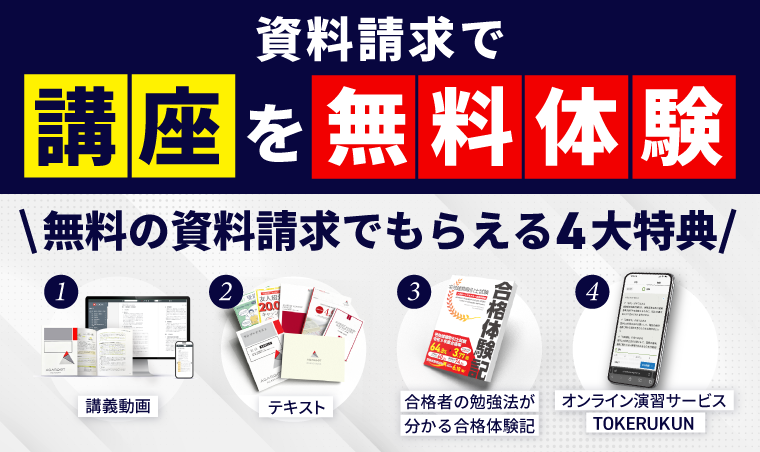
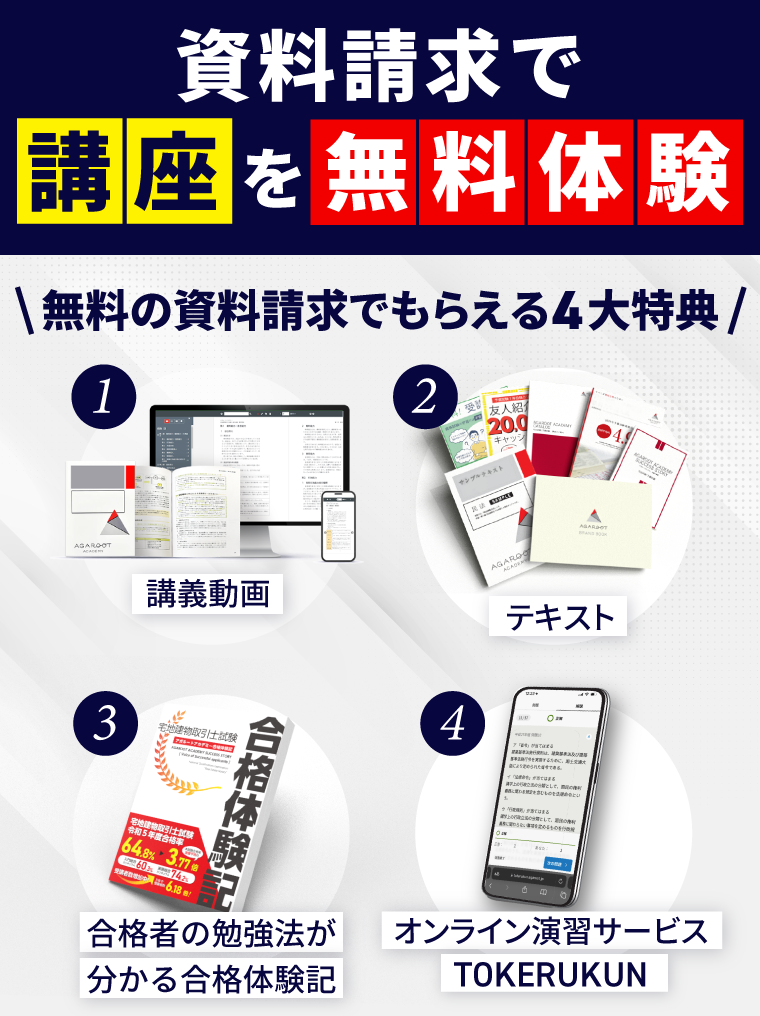
約3.5時間分の宅建業法&権利関係の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!宅建試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
2024年度 宅建試験は2024年10月20日(日)開催(令和6年)

宅建試験は国土交通省が試験主体となり、一般財団法人不動産適正取引推進機構を指定試験機関として実施するもので、2024年(令和6年)は10月20日(日)に試験が行われます。
なお、試験日を含めた全体的なスケジュール・流れについては次の項目で見ていきます。
試験の詳細については、「宅建試験の内容や科目」のコラムをご覧ください。
2024年度宅建試験のスケジュール・流れについて(令和6年)

ここでは2024年度宅建試験のスケジュール・流れについて見ていきます。
- 6月7日(金) 官報公告
- 7月1日(月) 試験案内の配布・申し込み受付開始
- 8月下旬 試験会場の通知
- 10月2日(水) 受験票発送
- 10月20日(日) 宅建試験日
- 11月26日(火) 合格発表
それでは以下で詳しく見ていきましょう。
1. 6月7日(金) 官報公告
例年6月の第1金曜日には、宅建試験の試験日や受験申込期限、受験料などが官報に掲載され、試験の概要を知ることができます。
2024年度については、2024年6月7日(金)に官報広告が行われました。
2. 7月1日(月) 試験案内の配布・申し込み受付開始
例年7月1日から、受験の申込方法などが記載された試験案内の配布が開始されます。
試験案内は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページにも掲載されるため、インターネット申込みの方は、試験案内を入手しなくてもホームページで確認すれば問題ありません。
ただし、郵送で申込みを希望している場合は、試験案内の中に受験申込書が入っているので、試験案内を入手する必要があります。
なお、2024年度試験について、インターネット申し込みは令和6年7月1日(月)9時30分から7月31日(水)23時59分までとなっています。
郵送申込み及び試験案内(郵送申込み用)の配布については、共に令和6年7月1日(月)から7月16日(火)までとなっています。
また、宅建の受験資格は存在しないため、誰でも申し込むことができます。
3. 8月下旬 試験会場の通知
8月下旬以降、10月の受験票発送前に試験会場を知りたい場合
①インターネット申し込みの場合、ウェブサイト「宅建試験マイページ」にて自分の試験会場を確認
②郵送申し込みの場合、専用のお問い合わせダイアル(電話番号は試験案内に記載)にて電話をする
という対応を取ることになります。
なお、令和5年以前は例年8月下旬には試験日の通知をしたハガキが発送されていましたが、令和6年からはハガキによる試験会場通知は行われないこととなっています。
4. 10月2日(水) 受験票発送受験票発送
例年9月下旬~10月上旬から、宅建試験の受験票が発送されます。
2024年度試験については、令和6年10月2日(水)からの発送となっています。
※郵送申込みの方で受験票が10月9日(水)までに届かない場合は各都道府県の協力機関又は不動産適正取引推進機構に必ずお問合せください。インターネット申込みの方はマイページをご確認ください。
5. 10月20日(日) 宅建試験日
例年10月の第3金曜日が宅建試験日です。
2024年度試験は10月20日(日)の13時から15時まで(2時間)*となっています。
*登録講習修了者は、13時10分から15時まで(1時間50分)
当日は、受験に際しての注意事項の説明がありますので、12時30分(登録講習修了者は12時40分)までに自席に着席してください。
6. 11月26日(火) 合格発表
例年11月下旬に合格発表がされます。
2024年度試験においては、11月26日(火)に宅建試験の合格発表が行われます。
宅建試験の申し込み方法(2024年度)

ここでは、宅建試験の申し込み方法について詳しく解説していきます。
なお、正確な情報については必ず公式HPをご確認ください。
まず、宅建試験の申し込みは、
①郵送での申し込み
②インターネットでの申し込み
2つの方法があります。
この2つでは出願方法や期限が異なるので、それぞれの場合に分けて出願方法を見ていきましょう。
郵送での申し込み方法
まずは郵送での申し込みについて解説します。
①試験案内及び受験申込書を入手する
郵送申し込みの場合は、まず試験案内を入手する必要があります。
試験案内は各都道府県の宅地建物取引業協会や全国の大型書店にあります。
不動産推進機構のホームページに配布場所が記載されているので参照してください。
色のついた封筒の中に試験案内と受験申込書が同封されています。
この2点が入っているか確認しましょう。
②提出書類を準備する
必要な内容を記載した受験申込書と顔写真、受験手数料を払い込んだ証明書が必要になります。
これに加えて、5問免除の登録講習を修了した方は登録講習修了者証明書の原本を、身体に障がいなどがあり配慮を希望する方は障がい等の状況と希望する内容を記載した書面及び障がい者手帳などのコピー又は医師の診断書が必要になります。
宅建試験の顔写真は、パスポート申請用の規格と同じ縦4.5cm×横3.5cmで頭頂からあごまで3.2cm以上3.6cm以下のものが必要です。
写真の裏面に都道府県名と氏名を記入し、受験申し込み書の所定欄に張り付けてください。
受験手数料と払込手数料が必要となっています。
指定の用紙を使い、郵便局又は銀行の窓口で7月30日の営業時間までに支払う必要があります。
支払いを行ったあと、受付証明書又はご利用明細表を申し込み書に添付して下さい。
③封筒記載の提出先に郵送で提出する
宅建は持参受付は行っていないため、郵送での提出となります。
試験案内が入っていた封筒に受験申し込み書を入れ郵便窓口から簡易書留で郵送してください。
7月1日から7月29日までが提出可能期間となっており、29日の当日消印有効です。
送付先は試験案内1ページに記載された各都道府県の協力機関(問い合わせ先)となっています。
試験案内が入った封筒で提出する場合には印刷されています。
インターネットでの申し込み方法
次にインターネットでの申し込み方法です。
①顔写真ファイルを用意する
インターネットで申し込む場合、デジタルカメラやスマートフォンなどで撮影した顔写真データを送信することになります。
ファイル形式はJPEG(ファイル名.jpg)にしてください。
②機構のホームページにアクセスし、必要事項を入力
不動産適正取引推進機構のホームページで必要事項を入力してください。
期間は7月19日の21時59分までとなっています。
郵送に比べ期間が短いので注意してください。
インターネットによる申し込みは24時間利用可能です。
また、複数の試験会場がある場合、試験会場を選択することもできます。
もっとも、選択は先着順となっているため、必ずしも希望する試験会場を選択できるとは限りません。
身体に障がいがあり配慮を希望する方はインターネット申し込みの前に協力機関に相談しましょう。
③受験手数料の支払い
受験手数料は8,200円です。
宅建試験申し込み時の注意点

以上で申し込みは完了ですが、いくつか注意が必要なことがあります。なお、正確な情報については必ず公式HPをご確認ください。
①郵送申し込みはインターネットに比べ申し込み期間や払込期間が短い
インターネットによる申し込み方法が7月31日(水)までになっているのに対し、郵送による申し込み方法は7月16日(火)と短くなっています。
インターネット申込みの方が原則24時間利用可能であるなど利便性は高いですが、インターネット申し込みに苦手意識のある人などは郵送にて早めの申し込みをした方が良いでしょう。
②登録講習修了者のなかにはインターネットでの申し込み方法が利用できない人がいる
登録講習者のうち、「インターネット申し込みができない講習」の修了者又は登録講習修了者証明書の氏名と現在の氏名が異なる方はインターネットでの申し込みができません。
これらの方は郵送による申し込みにしましょう。
③受験地は原則として申し込み時点で住民登録をしている都道府県
受験地は申し込みの時点で住民登録をしている都道府県となります。
ただし、進学や単身赴任などで別のところに住んでいる場合には、例外的に、現に居住している都道府県で受験することができます。
宅建の試験概要
宅建試験問題の出題形式は全てマークシート方式で、4つの選択肢から正答を一つ選択する四肢択一式。
問題数は全50問で、科目の内訳としては「民法等」が14問、「宅建業法」が20問、「法令上の制限」が8問、「その他関連知識」が8問となっています。
なお、相対評価方式であるため合格点は毎年異なります(例年35点前後)。
宅建の合格率は例年15%〜17%であり、難易度は決して低くありません。
挑戦する際にはしっかりと学習計画を立てて挑みましょう。
宅建試験の合格を
目指している方へ
- 宅建試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの宅建試験講座を
無料体験してみませんか?

豊富な合格実績!
令和5年度のアガルート受講生の合格率64.8%!全国平均の3.77倍!
追加購入不要!これだけで合格できる
カリキュラム
充実のサポート体制だから安心
合格特典付き!
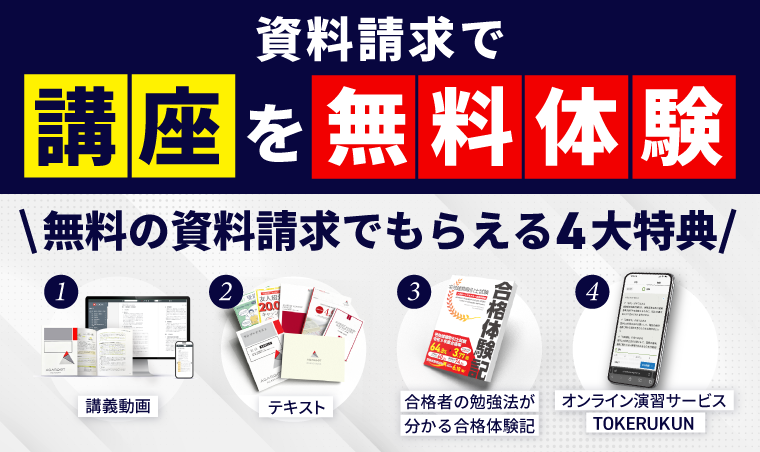
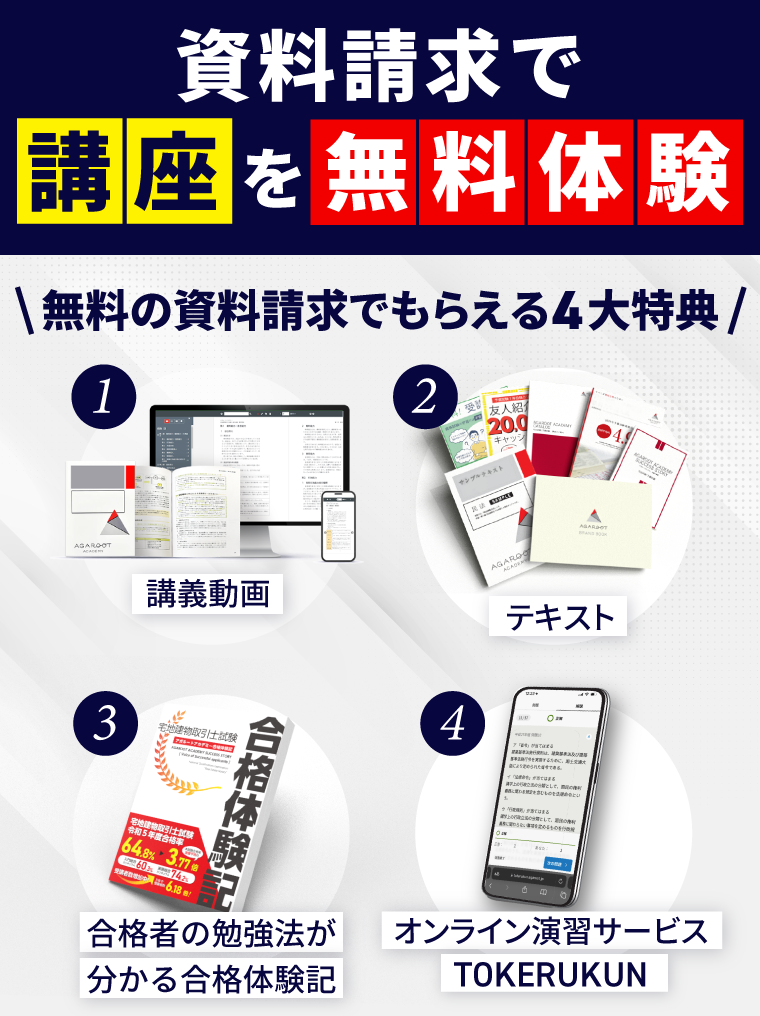
約3.5時間分の宅建業法&権利関係の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!宅建試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る


