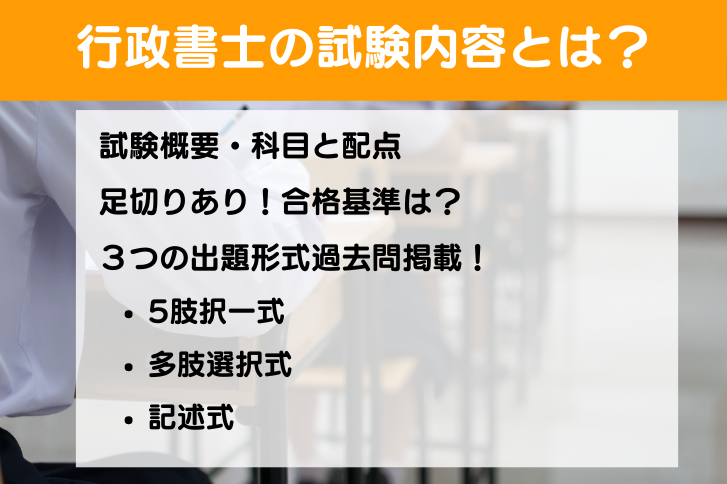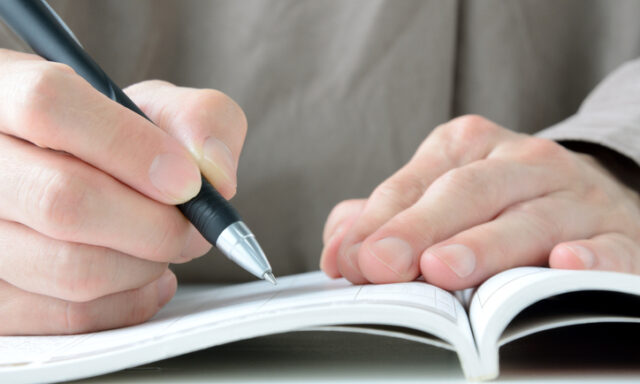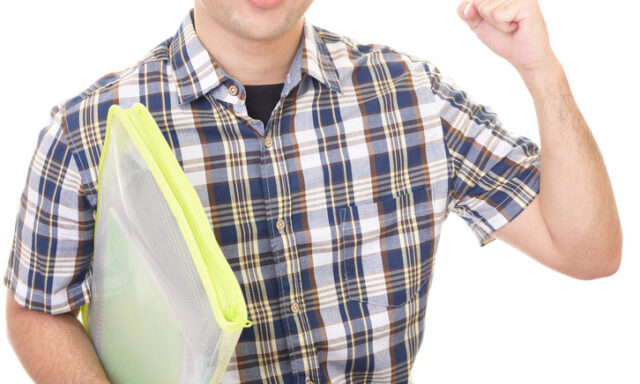行政書士法改正の主要ポイント【2026年1月施行】実務・試験への影響と対策
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります
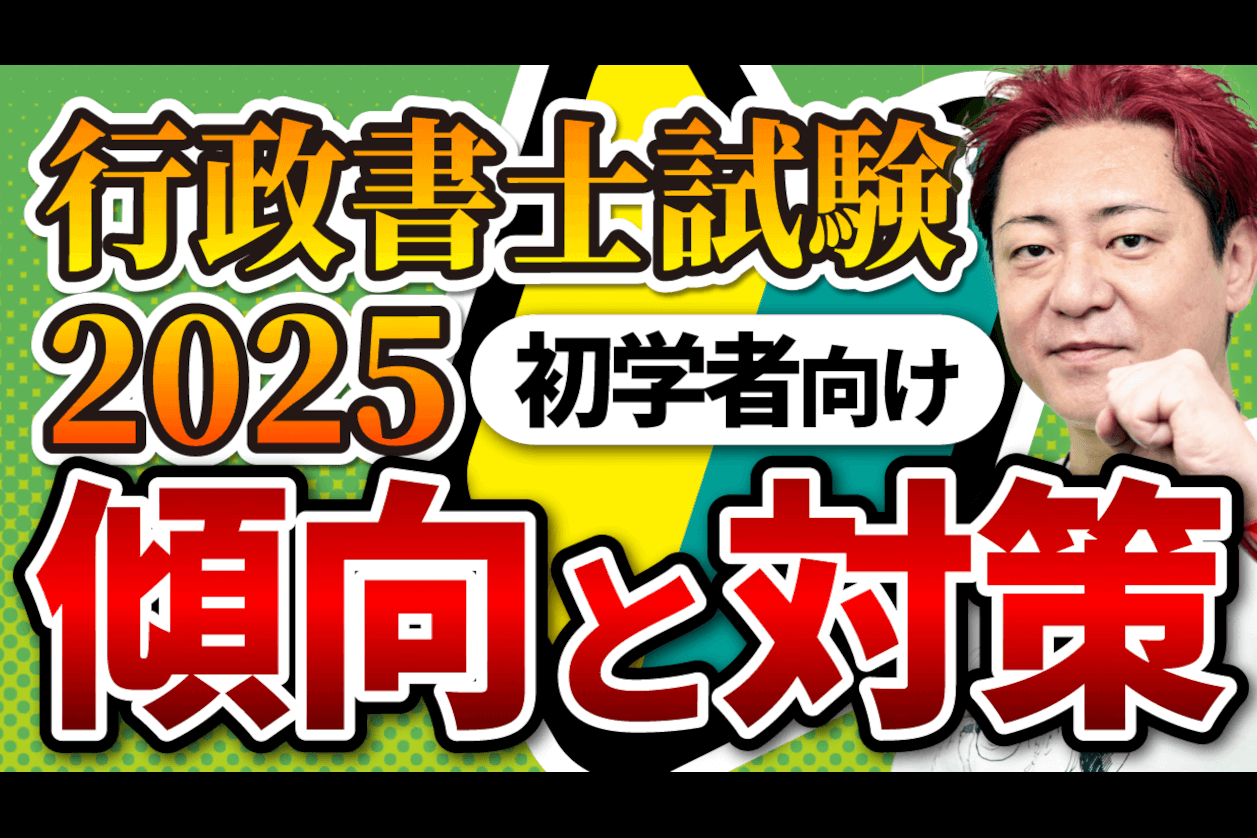
2025年6月に「行政書士法の一部を改正する法律案」が成立しました。この改正法は2026年1月1日から施行される予定です。
今回は、行政書士の法改正のポイントをまとめました。施工後の実務や試験への影響、対策方法についても解説するため、ぜひ最後までご覧ください。
行政書士試験合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 行政書士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの行政書士試験講座を
無料体験してみませんか?


15時間45分の民法総則&個人情報保護の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!行政書士試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
割引クーポンやセール情報が届く!
1分で簡単!無料!
▶資料請求して特典を受け取る目次
【2026年1月施行】行政書士の法改正の主要ポイント
それでは早速、2026年1月に施行される行政書士の法改正のポイントを解説します。
- 行政書士の「使命」の明確化
- 「職責」の新設とデジタル社会への対応
- 特定行政書士の業務範囲のに拡大
- 業務の制限規定の趣旨明確化
- 両罰規定の整備による罰則強化
行政書士の「使命」の明確化
改正法では、これまでの「目的」という表現から「使命」へと変更され、行政書士が果たすべき役割がより明確にされました。
行政書士は、行政に関する手続きを円滑に実施し、国民の利便性を向上させることを通じて、国民の権利利益の実現に貢献する仕事です。
「行政書士法の目的」が「行政書士の使命」に変更されたことは、専門職としての行政書士が社会に対して負う責任の重さを強調するものといえるでしょう。
「職責」の新設とデジタル社会への対応
行政書士の「職責」の規定が第1条の2に新設されました。
内容としては、まず行政書士は常に品位を保持し、業務に関する法令と実務に精通し、公正かつ誠実に業務を行わなければなりません。
そして業務を行うにあたり、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用などにより国民の利便向上と業務改善を図る努力義務を負うというものです。
士業法の中で初めて「デジタル社会への対応」が努力義務として規定されたもので、現代社会の急速なデジタル化に対応する姿勢を示しています。
特定行政書士の業務範囲のに拡大
特定行政書士の業務範囲も、今回の改正で拡大されます。
これまでは「行政書士が作成した書類」しか不服申立ての代理ができませんでしたが、改正後は「行政書士が作成できる書類」の不服申立ての手続きを代理することが可能に。
そのため、たとえば申請者本人が作成した書類に関する不服申立てであっても、特定行政書士が代理できることになり、特定行政書士の業務範囲は大幅に広がります。
行政書士が紛争対応により深く関与できることで、活躍の場がさらに広がったといえるでしょう。
業務の制限規定の趣旨明確化
行政書士または行政書士法人でない者が業務を行うことへの制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。
書類作成という役務提供に対する対価が、「会費」などどのような名目であっても「報酬」に該当することを明確にするものです。
これにより、無資格者が報酬を得て行政書士業務を行うことへの規制が強化され、いわゆる「闇コンサル」の存在を抑制する狙いがあります。
両罰規定の整備による罰則強化
両罰規定とは、社員が法律違反をした場合、本人に加えて法人も責任を問われる規定のこと。
行政書士または行政書士法人でない者による業務の制限違反、名称使用制限違反、および行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定が整備されました。
この改正は、組織的な違反行為や法人としての義務違反に対する罰則を強化するものです。
具体的には、業務制限違反や名称使用制限違反を行った行為者だけでなく、その法人または個人に対しても罰金刑が科されることになります。
また、行政書士法人の帳簿備え付け・保存義務違反、依頼に応じる義務違反、都道府県知事による立ち入り検査の拒否・妨害・忌避といった行為も罰則の対象となります。
無資格者による業務代行や名義貸しに対して、より厳しい法的措置が適用される可能性が高まるでしょう。
行政書士の法改正はいつから?改正の背景とは?
行政書士法の改正は、現代社会の多岐にわたる課題に対応するために行われます。
改正の施行日と、その背景にある社会的な要請について理解することは、今回の法改正の意義を深く把握するために不可欠です。
行政書士法改正はいつから施行される?
「行政書士法の一部を改正する法律案」は、2026年1月1日から施行されます。
2025年5月30日に衆議院で可決され、その後2025年6月6日に参議院でも可決・成立しました。
行政書士法が改正される背景・社会的課題
行政書士法が改正される背景には、いくつかの重要な社会的課題が存在します。
まず、社会全体のデジタル化が急速に進み、制度が複雑化したことで、行政に関する手続きにおいて専門的な支援のニーズが著しく高まりました。
また、資格を持たない者がSNSやセミナー、コンサルティングといった名目で無責任な業務介入を行う、いわゆる「闇コンサル」の増加が問題視されていた背景もあります。
このような無資格者による業務は、依頼主の不利益につながる可能性があり、行政書士業界の健全な発展を阻害する要因となっていました。
そして、他士業やコンサルタントとの間で業務範囲の線引きが曖昧であり、現場での混乱を招いていたことも改正の大きな理由です。
今回の法改正は、これらの課題に対応し、行政書士業務の適正化と国民の利便性向上を図ることを目的としています。
法改正が実務に与える影響と今後の展望
行政書士法の改正は、行政書士の実務に直接的な影響を及ぼし、今後の業界のあり方や専門職間の関係性にも大きな変化をもたらすでしょう。
特に、特定行政書士の役割拡大と無資格者への規制強化は、実務の質と信頼性を高める上で重要な要素となります。
特定行政書士の不服申立て代理業務拡大の影響
今回の法改正により、特定行政書士の業務範囲が「行政書士が作成できる書類」の不服申立て手続に拡大されたことは、実務に大きな影響を与えます。
先述のとおり、これまでは自身が事前に作成した書類に関する不服申立てに限定されていましたが、今後は申請者本人が作成した書類に関する不服申立ても代理可能となったわけです。
この拡大は、行政書士が行政処分に関する紛争対応にこれまで以上に深く関与できることを意味し、国民の権利利益の実現に対する貢献度が高まることが期待されます。
実務においては、より多様な案件に対応できるようになるため、特定行政書士の専門性と需要が高まる可能性があるでしょう。
無資格者による補助金代行業務へのプレッシャー
補助金や認可申請書類の作成業務に関して、報酬を得て行う場合は行政書士に限ると法律で明確に定められました。
これは、以前から総務省の見解や国会答弁で「行政書士の独占業務である」と明確に示されてきた方針を、今回の改正で法的に明文化したものです。
この明確化により、無資格者が補助金申請支援業務を請け負った場合、違法行為とみなされる可能性が高まります。
総務省は2022年2月16日に「グレーゾーン解消制度」の照会に対し、補助金申請に係る官公署提出文書の作成は、報酬を得て業として行う場合には行政書士である必要があると回答しています。
この回答は、行政書士の補助金申請書作成業務が独占業務であるという政府見解の明確な根拠となりました。
今回の改正によって、無資格者による補助金代行業務の取り締まりがしやすくなります。
どこまで摘発されるかは行政側の運用姿勢にもよりますが、たとえ厳しい取り締まりがなくても、無資格者が関与した補助金申請が採択された後にそれが判明した場合、採択が取り消される可能性も否定できません。
このような事態に直面した場合、無資格者の代行業務は違法であると明文化された以上、依頼主はそれに従わざるを得なくなります。
この法改正は、「闇コンサル」と呼ばれる無資格業者に対し、業務への参入を抑制する一定の牽制効果を持つと期待されています。
他士業との業務線引き
中小企業支援の現場では、これまで中小企業診断士や税理士などが補助金申請に関与することが少なくありませんでした。
しかし、今回の行政書士法改正で、行政書士の業務独占規定が明確化されたことにより、今後、中小企業診断士、税理士、弁理士など、各専門職の間で業務範囲の線引きがより明確に進む考えられます。
それぞれの専門性を活かしつつ、定められた業務範囲を遵守することが一層求められるでしょう。
この動きは、各専門職がそれぞれの専門分野に特化し、質の高いサービスを提供することにつながる可能性があります。
法改正が行政書士試験へ与える影響は?
続いて、今回の法改正が行政書士試験に与える影響について解説します。
2025年度試験には反映されない
2025年法改正の内容は、2025年の行政書士試験に出題されません。
行政書士試験の法改正の問題は、試験年度の4月1日時点で施行されているものが対象です。
2025年法改正の施行日は2026年1月1日となるため、2025年度は試験範囲外となります。
2026年度試験からは対策が必要
2026年度の行政書士試験からは、2025年法改正も試験範囲となります。
特に「行政書士の目的(第1条)」は平成17年以前の試験でも頻出だった条文なため、改正後の「行政書士の使命(第1条)」について出題される可能性は十分にあるでしょう。
新しい法改正は過去問で出題されないため、模試や答練で対策することが重要です。
近年の法改正による試験への影響
なお2024年度より法改正に伴い、これまで「一般知識等」とされていた科目は「基礎知識」へ名称が変更され、出題内容も一部見直されました。
従来は基準点を落とさないための科目と位置づけられていましたが、現在では行政書士として必要な基礎を問う「得点源」としての重要性が高まっています。
この変化により、基礎知識科目の学習は単なる足切り対策ではなく、合否を大きく左右する中心的な準備領域となっている点に注意が必要です。
法改正の対策は通信講座でするのがおすすめ
行政書士試験の法改正の対策をするなら、通信講座を活用するのがおすすめです。
独学で知識を身につけるのも不可能ではありませんが、法律は改正が多くひとりでカバーするのは困難な分野。古い知識のまま試験に臨んでは、せっかくの学習が無駄になります。
とはいえ、常に最新の法改正をチェックするのは、学習を進めるうえで非効率的です。
その点、通信講座を活用すれば、常に最新情報をキャッチアップできます。もちろん他の分野を効率的に学んだり、わからない部分を講師に質問したりすることも可能です。
現在、アガルートでは行政書士試験の対策講座を無料体験できます。講座選びにおいて重要な「講師との相性」も確かめられるため、興味のある方はぜひ試してみてください。
まとめ
今回は、2026年1月1日に施行される法改正のポイントや影響について解説しました。
改めて、今回の法改正のポイントをまとめると以下のとおりです。
- 行政書士の「使命」の明確化
- 「職責」の新設とデジタル社会への対応
- 特定行政書士の業務範囲のに拡大
- 業務の制限規定の趣旨明確化
- 両罰規定の整備による罰則強化
行政書士試験に合格するには、最新の法知識を身につけることが不可欠です。「過去問を解けたからいいや」と妥協すると、古い知識のまま試験に臨むことになりかねません。
定期的に日本行政書士会連合会のHPを確認するか、不安のある方は通信講座を活用するなどして、最新情報をキャッチアップできるような体制をつくりましょう。
行政書士試験合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 行政書士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの行政書士試験講座を
無料体験してみませんか?


15時間45分の民法総則&個人情報保護の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!行政書士試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
割引クーポンやセール情報が届く!
1分で簡単!無料!
▶資料請求して特典を受け取る
豊富な合格実績!令和6年度のアガルート受講生の合格率46.82%!全国平均の3.63倍!
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
全額返金など合格特典付き!
会員20万人突破記念!
全商品5%OFF!
3月1日までの申込で10%OFF!
▶行政書士試験講座を見る※2026年合格目標 行政書士試験/入門カリキュラム/総合講座