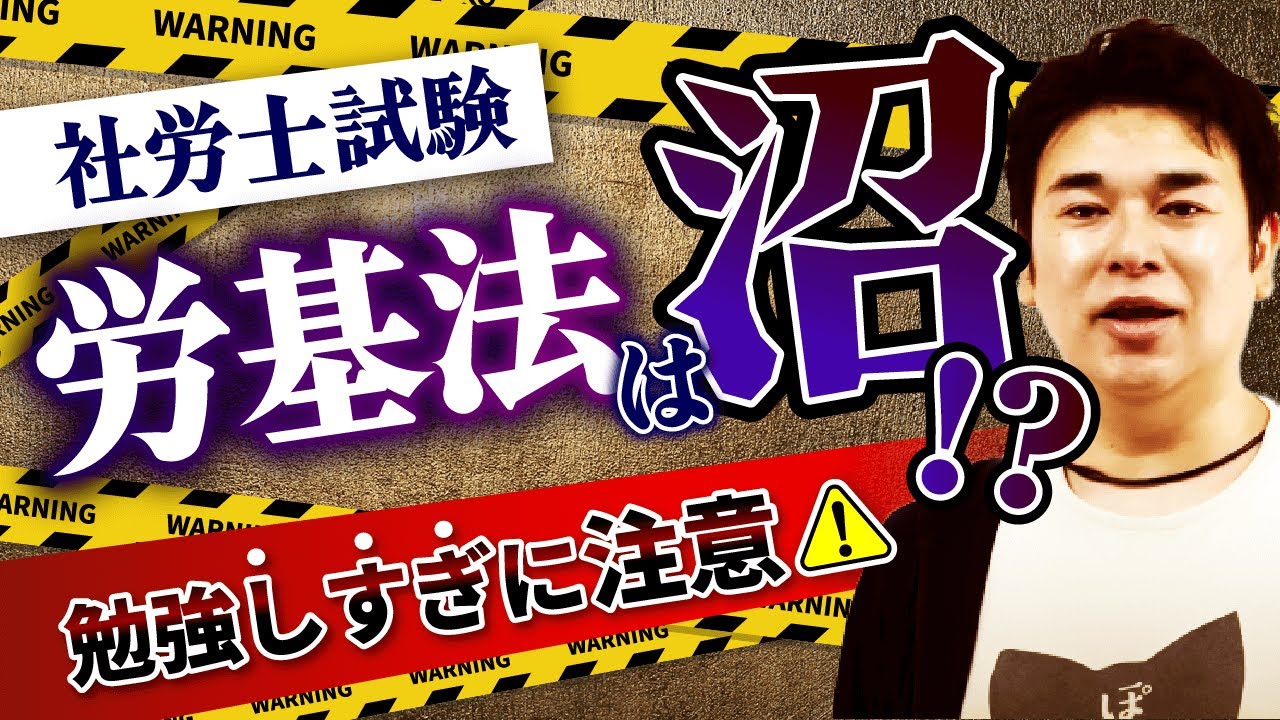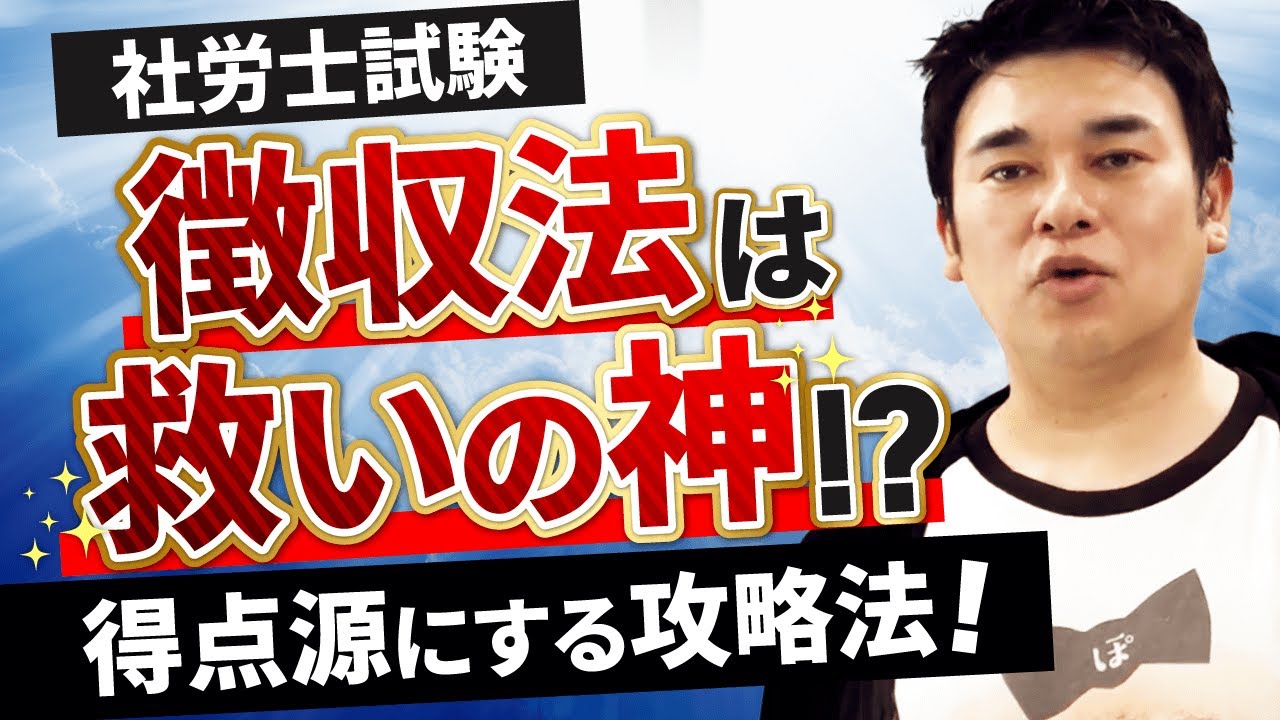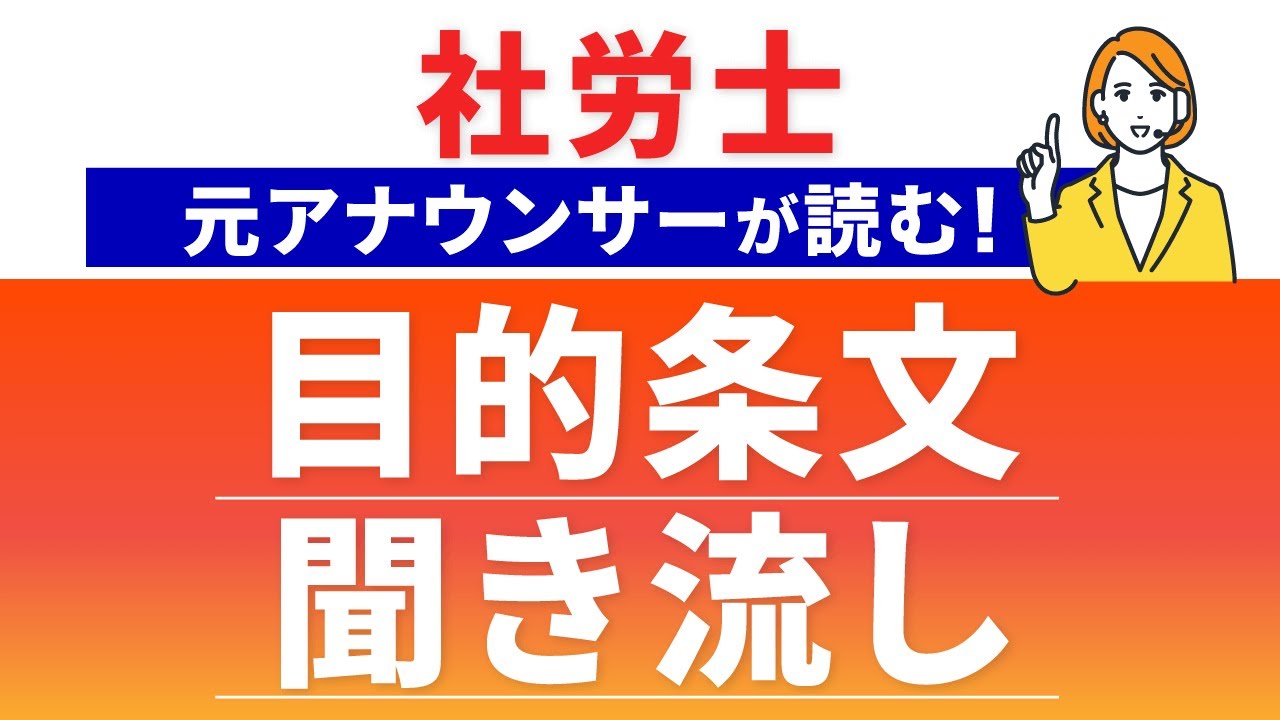社労士の登録料はいくら?開業・勤務で変わる費用内訳と更新について解説
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

社会保険労務士(社労士)は、「資格取得後にお金がかかる資格」です。
登録料や入会金、年会費など費用の種類も細分化されており、金額も地域によってさまざま。
「具体的にいくら必要なの?」「更新料は必要?」など、気になっている方もいるでしょう。
当コラムでは、社労士の登録料をはじめ、必要な費用について詳しく解説します。
社労士取得を目指している方・登録を検討している方はぜひ参考にしてください。
社会保険労務士試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 合格者の共通点や特徴を知りたい
アガルートの社会保険労務士試験講座を
無料体験してみませんか?


約8時間分の労働基準法講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!
割引クーポンやセール情報が届く!
1分で簡単お申込み
▶資料請求して特典を受け取る目次
【種類別】社会保険労務士の登録料

ここからは社会保険労務士登録に必要な登録費用について説明します。
社会保険労務士登録の登録料は、東京の場合約72,000円~約146,000円必要になります。
社労士の登録費用は、各都道府県の社労士会によって異なるため留意しましょう。社会保険労務士資格を維持するための維持費(年会費)も必要になります。
社労士の年会費・維持費は、東京の場合、開業登録は96,000円、勤務等登録は42,000円必要です。
| 項目 | 開業登録 | 勤務等登録 | |
| 連合会加入 | 登録手数料 | 30,000円 | 30,000円 |
| 登録免許税 | 30,000円 | 30,000円 | |
| 社労士会加入 (東京都の場合) |
入会金 | 50,000円 | 30,000円 |
| 年会費 | 96,000円 | 42,000円 | |
| 合計 | 206,000円 | 132,000円 | |
※上記金額はあくまでも目安としてお考え下さい。
社労士登録に必要な費用には以下の2つがあります。
1.連合会加入の登録手数料、登録免許税
2.社労士会加入の入会金、年会費
以下、それぞれ説明します。
1.連合会加入の登録手数料、登録免許税
全国社会保険労務士連合会に加入するためには登録手数料、登録免許税を支払う必要があります。
開業登録の場合も勤務等登録の場合も、登録手数料、登録免許税は全国一律でそれぞれ3万円です。
これら登録手数料、登録免許税は都道府県社会保険労務士会の入会費・年会費とは異なり、全国共通の費用です。
これらは初回の登録時にのみ必要な費用です。
2.社労士会加入の入会金、年会費
社労士会加入の入会金、年会費は、開業登録の場合と勤務等登録の場合では異なります。
また、登録する都道府県によっても費用は異なります。
東京都社会保険労務士会の場合の社労士登録にかかる費用は以下となります。
| 種類 | 入会金 | 年会費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 開業登録 | 50,000円 | 96,000円 | 146,000円 |
| 勤務等登録 | 30,000円 | 42,000円 | 72,000円 |
地域別の入会金・年会費
| 地域 | 会員区分 | 入会金 | 年会費 |
| 神奈川県 | 開業 | 70,000円 | 90,000円 |
| 勤務・その他 | 40,000円 | 45,000円 | |
| 千葉県 | 開業会員(法人社員含む) | 80,000円 | 84,000円 |
| 上記以外の社労士 | 80,000円 | 60,000円 | |
| 埼玉県 | 開業会員 | 100,000円 | 120,000円 |
| 非開業会員 | 50,000円 | 60,000円 | |
| 山梨県 | 開業会員(法人社員含む) | 80,000円 | 84,000円 |
| 上記以外 | 80,000円 | 60,000円 | |
| 愛知県 | 開業会員(法人社員含む) | 100,000円 | 84,000円 |
| 勤務会員等 | 80,000円 | 50,400円 | |
| 大阪府 | 開業会員(法人社員含む) | 150,000円 | 84,000円 |
| 勤務等会員 | 100,000円 | 42,000円 | |
| 滋賀県 | 開業・社員 | 120,000円 | 50,000円/半年 |
| 勤務・その他 | 80,000円 | 50,000円/半年 |
実務経験がない場合は事務指定講習費用も必要
社労士に登録するには、2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験があることが条件です。
2年間の実務経験での登録要件を満たせない場合は事務指定講習を受講する必要があります。
事務指定講習の受講料は77,000円(税込)です。
事務指定講習とは?
事務指定講習は正式名称を「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」といい、社労士になるために必要な実務経験に代えることができる講習のことです。
社労士として登録するためには本来2年以上の実務経験が必要ですが、事務指定講習を受講することで、実務経験がない方でも社労士登録が可能になります。
事務指定講習は4か月間の「通信指導過程」と7〜9月の間に実施される「面接指導過程」に分かれて実施され、二過程は同一年度に受講する必要があります。
「通信指導過程」は期間内に数十件の課題を提出して添削を受ける指導。
「面接指導過程」は講義形式の授業として実施されます。
通信指導過程の課題を提出できなかった場合、事務指定講習を受講しなかったと判定されるため注意が必要です。
講習の受講は合格の翌年以降でも可能。
また、登録に必要な実務経験に代わる講習として実施されるため、すぐに社労士として就業する予定がない場合は受講を焦る必要はありません。
社労士として登録する6つのメリット
社労士登録することのメリットには以下の6つがあります。
- 社労士と名乗ることができる
- 社労士としてのキャリアをスタートすることができる
- 社労士の独占業務を行うことができる
- 研修や法改正情報を得ることができる
- 人脈づくりができる
- 仕事の紹介がもらえる
1.社労士と名乗ることができる
一つめは社労士と名乗ることができるという点です。
社労士試験に合格するとだれかに伝えたくなりますが、社労士登録していない状態では名刺に社会保険労務士と記載することもできません。
あくまで社労士試験の合格者であり、社労士ではありません。
2.社労士としてのキャリアをスタートすることができる
社労士としてのキャリアは登録した時からスタートします。
開業10年目の人と開業1年目の人、社労士でない人とでは信頼の得られやすさが全く異なります。
いつかタイミングが来たら登録しようと考えている人も、将来社労士として働く気持ちが本当にあるのであれば、すぐに登録することをおすすめします。
3.社労士の独占業務を行うことができる
社労士登録の大きなメリットの一つは独占業務を行うことができるようになるという点です。
法律で守られた社労士にしかできない業務は、社労士登録しなければ行うことができません。
社労士でなくても、従業員として雇用されている会社の手続きを行うことは可能ですが、これは、社労士試験に合格していない人も同様です。
4.研修や法改正情報を得ることができる
労働法、社会保険分野は法改正が多く、最新の情報のインプットをし続けない限り、社労士試験の受験勉強で学んだ知識もすぐに古くなってしまいます。
社労士登録をし社会保険労務士県会に所属することで重要な法改正情報や実務に関する様々な研修を受けることが可能となります。
5.人脈づくりができる
社労士登録を行うと、県会の定例会議や研修などで先輩社労士の方とのつながりも生まれます。
始めは勤務登録やその他登録を行っていた人であっても、実際に開業して活躍している人と関わり刺激を受ける中で独立開業を目指す人も少なくありません。
同じ社労士であっても働き方や業務内容は様々なので、いろんな人と出会うことでロールモデルとなる人を見つけるのもよいでしょう。
6.仕事の紹介がもらえる
社労士県会に登録すると、研修の講師の仕事や窓口での労働相談の業務などの仕事の募集が定期的に行われます。
実際に社労士として働くことは、スキルアップにつながるだけでなく、社労士として働くことの大きな喜びを感じることが可能です。
社労士登録に更新は必要?更新料と有効期限
社労士の資格には更新がないため、更新料はありません。
社労士登録に関して有効期限などもありません。
しかし、各都道府県の社労士会が定める年会費は2年目以降であっても毎年支払う必要があります。
所属する社労士会毎に年会費は異なるので、自分の所属する社労士会の年会費はいくらなのか把握しておくことが大切です。
また社労士登録を抹消した場合は、再登録の手続きが必要となります。
この社労士の再登録についても無期限でいつでも再登録できますが、連合会の登録費用と社労士会の入会費が再度必要となります。
そのため、一旦社労士業務を休業する場合にも社労士登録を抹消するのではなく、勤務等登録(特に「その他」登録)にしておく方が良い場合もあります。
社会保険労務士登録時によくある質問
ここからは、社会保険労務士登録時によくある質問について説明します。
・登録関係書類の入手方法は?
社労士試験の合格者には、全国社会保険労務士連合会より登録申請書一式が郵送されてきます。
なお、登録関係書類は入会予定の都道府県社会保険労務士会によって異なる可能性があります。
したがって、入会予定の都道府県社会保険労務士会に確認するようにしましょう。
・登録に期限はあるのか?
社会保険労務士試験合格後、登録申請までの有効期限はありません。
したがって、希望するタイミングでいつでも登録申請を行うことが可能です。
事務指定講習や従事期間証明書についても同様です。
・入会及び手続きのタイミングは?
入会及び手続きのタイミングについては、毎月25日までに都道府県社会保険労務士会で受付された場合は、翌月1日付での登録となります。
なお、都道府県社会保険労務士会によっては、15日付での登録を行っているケースもあるため事前に確認するようにしましょう。
入会及び手続きのタイミングについての問合せ先は都道府県社会保険労務士会になります。
・入会金・年会費の納付方法は?
都道府県社会保険労務士会ごとに、入会金・年会費の金額や納付方法は異なります。
したがって、入会金・年会費の納付方法の詳細については入会を予定する都道府県社会保険労務士会への確認をお願いいたします。
・登録抹消後に再登録はできる?
登録抹消の場合も社会保険労務士となる資格を失うことはありません。
再登録はいつでも可能です。
・登録に更新は必要?
入会手続き後は、更新の手続きは不要です。
まとめ
当コラムでは、登録料や年会費など、社労士関連の費用をメインに以下の内容で解説しました。
- 社労士の登録料は地域によって異なり、東京では72,000円〜146,000円ほど。全国一律で各30,000円の登録料・登録免許料のほか、入会金や年会費が必要となる。
- 入会金・年会費は、開業や勤務など就業形態によっても異なる。
- 実務経験に代えて事務指定講習を受講する場合は、受講料として77,000円も必要。
社労士は生涯資格のため他資格でよくある更新料などはかかりませんが、年会費として毎年数万円を払わなくてはなりません。ほかにも、講習の受講や登録時・入会時など、都度お金が必要な資格です。
仕事を始めるだけでもかなりのコストがかかる一方、社労士登録には人脈形成や案件受注などメリットもたくさんあります。登録期限などは特にないため、十分な費用を用意できてから登録に進むことも可能です。
社会保険労務士試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 合格者の共通点や特徴を知りたい
アガルートの社会保険労務士試験講座を
無料体験してみませんか?


約8時間分の労働基準法講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!
割引クーポンやセール情報が届く!
1分で簡単お申込み
▶資料請求して特典を受け取る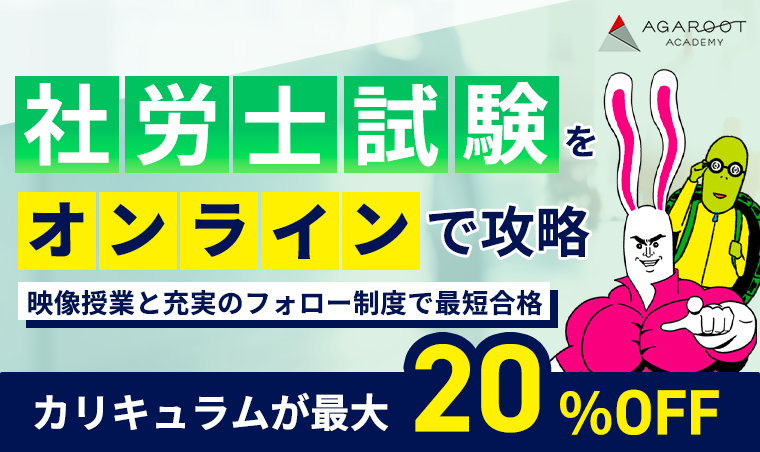
令和6年度のアガルート受講生の合格率35.82%!全国平均の5.19倍
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!
会員20万人突破記念!
全商品5%OFF!