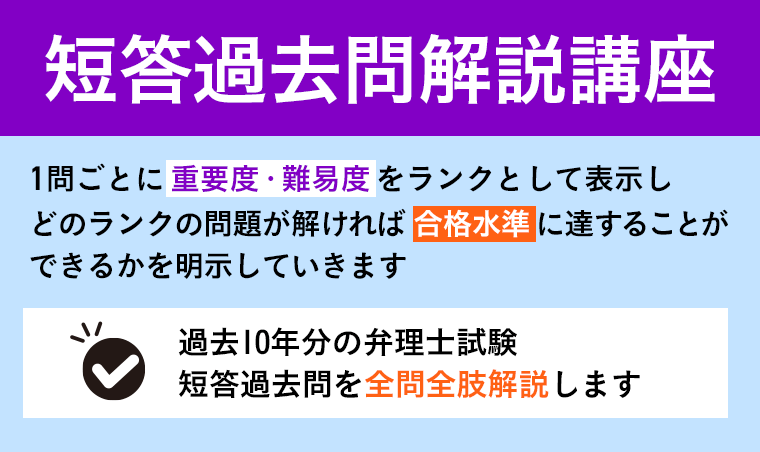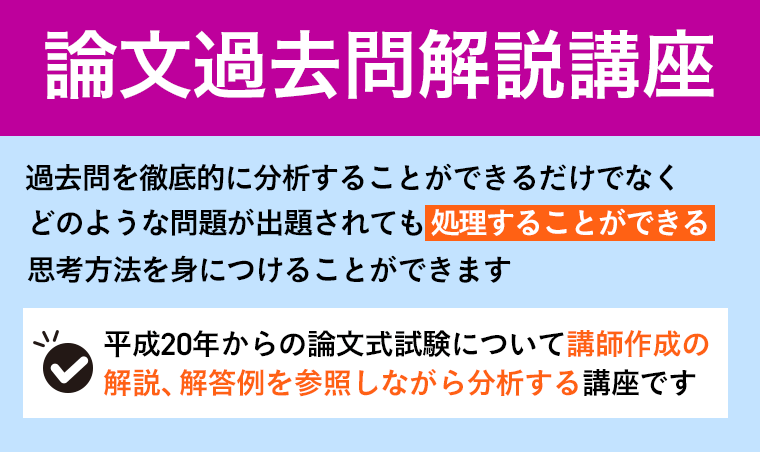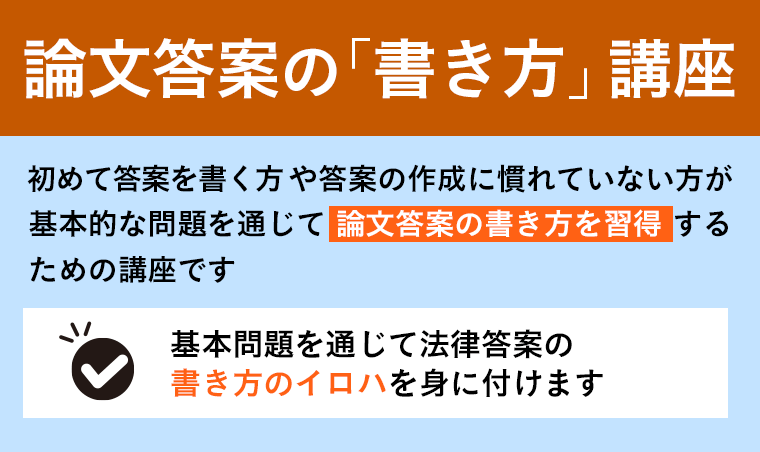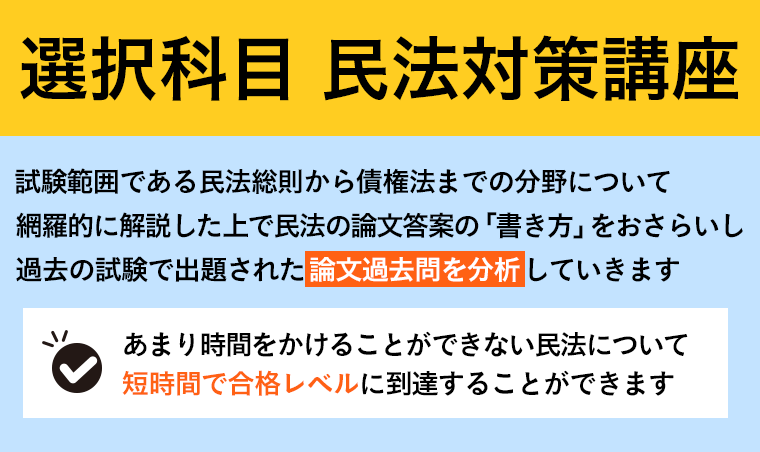弁理士試験の過去問(短答・論文必須・選択科目)一覧!短答・論文の解説と模範解答も
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

弁理士は理系の中でも最高峰の資格であり、平均合格率が10%に満たない難関資格でもあります。
そんな弁理士試験対策に必須の過去問ですが、過去10年以上の過去問を探している方も多いと思います。
この記事では弁理士試験の短答式・論文の必須科目および選択科目・口述試験の過去問を掲載しています。
また、過去問の解説や模範解答は必要な方におすすめの講座も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
弁理士試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
アガルートの弁理士試験講座を
無料体験してみませんか?


約17時間分の法律の基礎知識と特許法講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!弁理士試験講座のフルカラーテキスト!
アガルート弁理士試験講座のすべてがわかる!パンフレット&ブランドブック
割引クーポンやsale情報が届く!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
弁理士試験 短答式の過去問と解答
はじめに、弁理士試験 短答式の過去問と解答です。
| 年度 | 短答式筆記試験 過去問題 | 短答式筆記試験 過去問解答 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 問題 | 解答 |
| 令和6年度 | 問題 | 解答 |
| 令和5年度 | 問題 | 解答 |
| 令和4年度 | 問題 | 解答 |
| 令和3年度 | 問題 | 解答 |
| 令和2年度 | 問題 | 解答 |
| 令和元年度 | 問題 | 解答 |
| 平成30年度 | 問題 | 解答 |
| 平成29年度 | 問題 | 解答 |
| 平成28年度 | 問題 | 解答 |
| 平成27年度 | 問題 | 解答 |
| 平成26年度 | 問題 | 解答 |
| 平成25年度 | 問題 | 解答 |
| 平成24年度 | 問題 | 解答 |
| 平成23年度 | 問題 | 解答 |
| 平成22年度 | 問題 | 解答 |
| 平成21年度 | 問題 | 解答 |
| 平成20年度 | 問題 | 解答 |
| 平成19年度 | 問題 | 解答 |
| 平成18年度 | 問題 | 解答 |
| 平成17年度 | 問題 | 解答 |
| 平成16年度 | 問題 | 解答 |
| 平成15年度 | 問題 | 解答 |
| 平成14年度 | 問題 | 解答 |
なお、特許庁で公表されている解答には原則解説はついていません。
短答式試験の解説が必要な場合は、アガルートの短答過去問解説講座がおすすめです。
短答過去問解説講座は、弁理士試験の短答式試験の過去10年分の「全問全肢」解説する内容となっています。
1問ごとに重要度・難易度がランクとして表示されており、どのランクの問題が解ければ合格水準に達することができるのかを分かりやすく明示している優れた講座となっています。
ポイントをしっかり押さえ、この講座だけで短答式試験の過去問対策は万全です。
弁理士試験 論文式必須科目の過去問と解答
続いて、弁理士試験 論文式(必須科目)の過去問と論点です。
論文式試験ではいわゆる「模範解答」は公開されておらず、代わりに「論点」が公表されています。
「解答例」を見たい場合は、アガルートの論文過去問解説講座がおすすめです。
こちらは論文式試験の過去問について、講師作成の「解説・解答例」を参照しながら分析する講座となっています。
また、初めて答案を書く場合や答案作成に慣れていない場合、アガルートの論文答案の「書き方」講座でまずは答案の「お作法」を学ぶことも可能です。
特許・実用新案
| 年度 | 論文式筆記試験 (必須科目)過去問題 | 論点 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 問題 | 論点 |
| 令和6年度 | 問題 | 論点 |
| 令和5年度 | 問題 | 論点 |
| 令和4年度 | 問題 | 論点 |
| 令和3年度 | 問題 | 論点 |
| 令和2年度 | 問題 | 論点 |
| 令和元年度 | 問題 | 論点 |
| 平成30年度 | 問題 | 論点 |
| 平成29年度 | 問題 | 論点 |
| 平成28年度 | 問題 | 論点 |
| 平成27年度 | 問題 | 論点 |
| 平成26年度 | 問題 | 論点 |
| 平成25年度 | 問題 | 論点 |
| 平成24年度 | 問題 | 論点 |
| 平成23年度 | 問題 | 論点 |
| 平成22年度 | 問題 | 論点 |
| 平成21年度 | 問題 | 論点 |
| 平成20年度 | 問題 | 論点 |
| 平成19年度 | 問題 | 論点 |
| 平成18年度 | 問題 | 論点 |
| 平成17年度 | 問題 | 論点 |
| 平成16年度 | 問題 | 論点 |
| 平成15年度 | 問題 | ー |
| 平成14年度 | 問題 | ー |
意匠
| 年度 | 論文式筆記試験 (必須科目)過去問題 | 論点 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 問題 | 論点 |
| 令和6年度 | 問題 | 論点 |
| 令和5年度 | 問題 | 論点 |
| 令和4年度 | 問題 | 論点 |
| 令和3年度 | 問題 | 論点 |
| 令和2年度 | 問題 | 論点 |
| 令和元年度 | 問題 | 論点 |
| 平成30年度 | 問題 | 論点 |
| 平成29年度 | 問題 | 論点 |
| 平成28年度 | 問題 | 論点 |
| 平成27年度 | 問題 | 論点 |
| 平成26年度 | 問題 | 論点 |
| 平成25年度 | 問題 | 論点 |
| 平成24年度 | 問題 | 論点 |
| 平成23年度 | 問題 | 論点 |
| 平成22年度 | 問題 | 論点 |
| 平成21年度 | 問題 | 論点 |
| 平成20年度 | 問題 | 論点 |
| 平成19年度 | 問題 | 論点 |
| 平成18年度 | 問題 | 論点 |
| 平成17年度 | 問題 | 論点 |
| 平成16年度 | 問題 | 論点 |
| 平成15年度 | 問題 | ー |
| 平成14年度 | 問題 | ー |
商標
| 年度 | 論文式筆記試験 (必須科目)過去問題 | 論点 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 問題 | 論点 |
| 令和6年度 | 問題 | 論点 |
| 令和5年度 | 問題 | 論点 |
| 令和4年度 | 問題 | 論点 |
| 令和3年度 | 問題 | 論点 |
| 令和2年度 | 問題 | 論点 |
| 令和元年度 | 問題 | 論点 |
| 平成30年度 | 問題 | 論点 |
| 平成29年度 | 問題 | 論点 |
| 平成28年度 | 問題 | 論点 |
| 平成27年度 | 問題 | 論点 |
| 平成26年度 | 問題 | 論点 |
| 平成25年度 | 問題 | 論点 |
| 平成24年度 | 問題 | 論点 |
| 平成23年度 | 問題 | 論点 |
| 平成22年度 | 問題 | 論点 |
| 平成21年度 | 問題 | 論点 |
| 平成20年度 | 問題 | 論点 |
| 平成19年度 | 問題 | 論点 |
| 平成18年度 | 問題 | 論点 |
| 平成17年度 | 問題 | 論点 |
| 平成16年度 | 問題 | 論点 |
| 平成15年度 | 問題 | |
| 平成14年度 | 問題 |
論文式試験ではいわゆる「模範解答」は公開されていません。その代わりに、試験の「論点」が公表されています。
試験の「解説」が知りたい場合は、アガルートの論文過去問解説講座がおすすめです。
論文過去問解説講座は、論文式試験の過去問について、講師が作成した「解説・解答例」を参照しながら分析していくといった内容になっています。
また、初めて答案を書く場合や、まだ答案作成に慣れていない場合は、論文答案の「書き方」講座でまずは答案の「お作法」を学ぶのも良いでしょう。
論文答案の「書き方」講座は、初めて答案を書く方や答案の作成に慣れていない方が、基本的な問題を通じて、弁理士試験の論文答案の書き方を習得するための講座です。
弁理士試験 論文式選択科目の過去問と解答
続いて、弁理士試験 論文式(選択科目)の過去問と論点です。
選択科目では法律科目だけでなく、理工系の科目を選択することも可能。
科目は理工I・理工II・理工III・理工IV・理工V・法律の6種類あります。
ちなみに選択科目の「民法」に関しては、法律の専門家である弁護士資格保有者の講師によるアガルートの選択科目 民法対策講座がおすすめです。
「選択科目 民法対策講座」は、弁理士試験受験生にとってあまり時間をかけることができない民法について、短時間で合格レベルに到達させる講座です。
理工Ⅰ (機械・応用力学)
| 年度 | 論文式筆記試験 (選択科目)過去問題 | 論点 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 材料力学 | 論点 |
| 流体力学 | 論点 | |
| 熱力学 | 論点 | |
| 令和6年度 | 材料力学 | 論点 |
| 流体力学 | 論点 | |
| 熱力学 | 論点 | |
| 令和5年度 | 材料力学 | 論点 |
| 流体力学 | 論点 | |
| 熱力学 | 論点 | |
| 令和4年度 | 材料力学 | 論点 |
| 流体力学 | 論点 | |
| 熱力学 | 論点 | |
| 令和3年度 | 材料力学 | 論点 |
| 流体力学 | 論点 | |
| 熱力学 | 論点 | |
| 令和2年度 | 材料力学 | 論点 |
| 流体力学 | 論点 | |
| 熱力学 | 論点 | |
| 令和元年度 | 材料力学 | 論点 |
| 熱力学 | 論点 | |
| 平成30年度 | 材料力学 | 論点 |
| 流体力学 | 論点 | |
| 熱力学 | 論点 | |
| 平成29年度 | 材料力学 | 論点 |
| 流体力学 | 論点 | |
| 熱力学 | 論点 | |
| 平成28年度 | 材料力学 | 論点 |
| 流体力学 | 論点 | |
| 熱力学 | 論点 |
理工Ⅱ (数学・物理)
| 年度 | 論文式筆記試験 (選択科目)過去問題 | 論点 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 基礎物理学 | 論点 |
| 電磁気学 | 論点 | |
| 回路理論 | 論点 | |
| 令和6年度 | 基礎物理学 | 論点 |
| 電磁気学 | 論点 | |
| 回路理論 | 論点 | |
| 令和5年度 | 基礎物理学 | 論点 |
| 電磁気学 | 論点 | |
| 回路理論 | 論点 | |
| 令和4年度 | 基礎物理学 | 論点 |
| 電磁気学 | 論点 | |
| 令和3年度 | 基礎物理学 | 論点 |
| 電磁気学 | 論点 | |
| 回路理論 | 論点 | |
| 令和2年度 | 基礎物理学 | 論点 |
| 電磁気学 | 論点 | |
| 回路理論 | 論点 | |
| 令和元年度 | 基礎物理学 | 論点 |
| 電磁気学 | 論点 | |
| 回路理論 | 論点 | |
| 平成30年度 | 基礎物理学 | 論点 |
| 電磁気学 | 論点 | |
| 回路理論 | 論点 | |
| 平成29年度 | 基礎物理学 | 論点 |
| 電磁気学 | 論点 | |
| 回路理論 | 論点 | |
| 平成28年度 | 基礎物理学 | 論点 |
| 電磁気学 | 論点 | |
| 回路理論 | 論点 |
※令和4年度の回路理論は受験者がいなかったため過去問がありません。
理工Ⅲ (化学)
| 年度 | 論文式筆記試験 (選択科目)過去問題 | 論点 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 物理化学 | 論点 |
| 有機化学 | 論点 | |
| 無機化学 | 論点 | |
| 令和6年度 | 物理化学 | 論点 |
| 有機化学 | 論点 | |
| 無機化学 | 論点 | |
| 令和5年度 | 物理化学 | 論点 |
| 有機化学 | 論点 | |
| 無機化学 | 論点 | |
| 令和4年度 | 物理化学 | 論点 |
| 有機化学 | 論点 | |
| 無機化学 | 論点 | |
| 令和3年度 | 物理化学 | 論点 |
| 有機化学 | 論点 | |
| 無機化学 | 論点 | |
| 令和2年度 | 物理化学 | 論点 |
| 有機化学 | 論点 | |
| 無機化学 | 論点 | |
| 令和元年度 | 物理化学 | 論点 |
| 有機化学 | 論点 | |
| 無機化学 | 論点 | |
| 平成30年度 | 物理化学 | 論点 |
| 有機化学 | 論点 | |
| 無機化学 | 論点 | |
| 平成29年度 | 物理化学 | 論点 |
| 有機化学 | 論点 | |
| 無機化学 | 論点 | |
| 平成28年度 | 物理化学 | 論点 |
| 有機化学 | 論点 | |
| 無機化学 | 論点 |
理工Ⅳ (生物)
| 年度 | 論文式筆記試験 (選択科目)過去問題 | 論点 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 生物学一般 | 論点 |
| 生物化学 | 論点 | |
| 令和6年度 | 生物学一般 | 論点 |
| 生物化学 | 論点 | |
| 令和5年度 | 生物学一般 | 論点 |
| 生物化学 | 論点 | |
| 令和4年度 | 生物学一般 | 論点 |
| 生物化学 | 論点 | |
| 令和3年度 | 生物学一般 | 論点 |
| 生物化学 | 論点 | |
| 令和2年度 | 生物学一般 | 論点 |
| 生物化学 | 論点 | |
| 令和元年度 | 生物学一般 | 論点 |
| 生物化学 | 論点 | |
| 平成30年度 | 生物学一般 | 論点 |
| 生物化学 | 論点 | |
| 平成29年度 | 生物学一般 | 論点 |
| 生物化学 | 論点 | |
| 平成28年度 | 生物学一般 | 論点 |
| 生物化学 | 論点 |
理工Ⅴ (情報)
| 年度 | 論文式筆記試験 (選択科目)過去問題 | 論点 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 情報理論 | 論点 |
| 計算機工学 | 論点 | |
| 令和6年度 | 情報理論 | 論点 |
| 計算機工学 | 論点 | |
| 令和5年度 | 情報理論 | 論点 |
| 令和4年度 | 情報理論 | 論点 |
| 計算機工学 | 論点 | |
| 令和3年度 | 情報理論 | 論点 |
| 令和2年度 | 情報理論 | 論点 |
| 計算機工学 | 論点 | |
| 令和元年度 | 情報理論 | 論点 |
| 計算機工学 | 論点 | |
| 平成30年度 | 情報理論 | 論点 |
| 計算機工学 | 論点 | |
| 平成29年度 | 情報理論 | 論点 |
| 計算機工学 | 論点 | |
| 平成28年度 | 情報理論 | 論点 |
| 計算機工学 | 論点 |
法律 (弁理士の業務に関する法律)
| 年度 | 論文式筆記試験 (選択科目)過去問題 | 論点 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 民法 | 論点 |
| 令和6年度 | 民法 | 論点 |
| 令和5年度 | 民法 | 論点 |
| 令和4年度 | 民法 | 論点 |
| 令和3年度 | 民法 | 論点 |
| 令和2年度 | 民法 | 論点 |
| 令和元年度 | 民法 | 論点 |
| 平成30年度 | 民法 | 論点 |
| 平成29年度 | 民法 | 論点 |
| 平成28年度 | 民法 | 論点 |
なお法律の選択問題である「民法」の受験対策については、実際に法律の専門家である弁護士資格を保有している講師によるアガルートの選択科目 民法対策講座を活用するのがおすすめです。
選択科目 民法対策講座は、弁理士試験受験生にとってあまり時間をかけることができない民法について、短時間で合格レベルに到達することができる内容となっています。
弁理士試験口述試験の過去問と解答
口述試験では過去問も解答も公表されていません。
しかし、「出題テーマ」は公表されているので、ここからはそちらをチェックしていきましょう。
| 年度 | 日 | 特許・実用新案 | 意匠 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 1日目 | 外国語書面出願 | 意匠公報・秘密意匠制度・先使用・建築物の意匠 | 設定の登録前の金銭的請求権 |
| 2日目 | 差止請求、損害賠償請求 | 国際登録に係る意匠の実施と補償金請求権 | 地域団体商標等 | |
| 令和6年度 | 1日目 | 方法の発明の効力等 | 関連意匠制度 | 色彩のみからなる商標 |
| 2日目 | 代理権・手続の補正 | 一意匠、組物の意匠、内装の意匠 | 商標法第52条の2の審判 | |
| 令和5年度 | 1日目 | 明細書等の補正 | 意匠に係る物品、意匠権の効力、意匠の登録要件 | 商標の保護 |
| 2日目 | 訂正審判と訂正の請求 | 意匠の公示、他の権利との関係 | 不使用取消審判 | |
| 令和4年度 | 1日目 | 特許無効審判の請求等の取下げ | 意匠登録を受けることができない意匠 | 商標権の効力・侵害 |
| 2日目 | 明細書等の記載要件と特許発明の技術的範囲 | 職務創作・関連意匠 | 登録要件 | |
| 令和3年度 | 1日目 | 出願公開、補償金請求権 | 意匠権、実施権 | 商標権全般 |
| 2日目 | 拒絶査定不服審判、前置審査 | 新規性、新規性喪失の例外、先願、関連、分割 | マドリッド協定の議定書及びそれに基づく特例 | |
| 令和2年度 | 1日目 | 特許権侵害、損害賠償額 | 補正と補正却下、拒絶理由 | 商標登録の要件 |
| 2日目 | 先願、拡大された先願 | 意匠の類似等、利用、裁定 | 異議申立て、無効審判 | |
| 令和元年度 | 1日目 | 特許を受ける権利の帰属と職務発明 | 形状の変化する意匠 | 無効審判、不使用取消審判 |
| 2日目 | 均等侵害 | 権利侵害、無効審判 | 商標登録出願に関する手続 | |
| 平成30年度 | 1日目 | 分割出願 | 関連意匠 | 商標権侵害 |
| 2日目 | 特許権侵害訴訟 | 意匠権の抵触、意匠権の効力 | 地域団体商標 | |
| 平成29年度 | 1日目 | 新規性 | 侵害、部分意匠 | 審判・登録異議の申立て |
| 2日目 | 直接侵害と間接侵害 | 新規性喪失の例外 | 商標登録出願手続 | |
| 平成28年度 | 1日目 | 明細書等の補正 | 組物の意匠と部分意匠 | 商標権の効力 |
| 2日目 | 審決取消訴訟 | 補正と補正却下 | 商標権の設定、更新、消滅 |
なお、口述試験の対策につきましては、実際に口述試験に合格した現役弁理士が解説している関連記事が参考になります。
関連記事:弁理士の口述試験とは?模試・過去問の対策方法や落ちた人の特徴は?
弁理士試験における過去問の効果的な使い方・勉強法
弁理士資格は、平均合格率が10%に満たない難関資格です。
合格のためには、特に過去問の使い方が重要となります。
では、過去問を使ってどのように勉強を進めていけば良いのでしょうか。
過去問に取りかかる前に、基本書で試験範囲全体の内容をざっと把握しておくことをおすすめします。
基本書を使った勉強と過去問を使った勉強を並行して進めていくことで、知識が徐々に定着していくはずです。
短答式試験の過去問の使い方
使用するものは、体系別(分野別)過去問題集と法文集です。過去問は問題ごとではなく、問題に含まれている一つひとつを見ていきます。
具体的な方法としては、最初に問題文と解説を読むことです。解説には、問題のポイントと条文番号が記載されています。
法文集の該当条文に過去問の年度、問題番号をメモします。
問題で問われているポイントをその条文の中から、重要なキーワードにマーカーを引きましょう。単語レベルまで落とし込むことが大事なポイントです。
法文集は、メモを書き込みやすい余白の大きいものを選びましょう。筆者は青本にすべて書き込んでいましたが、四法対照法文集も良いかもしれません。
著作権法や不正競争防止法、条約等については、法文集に書き込むのが難しければ、基本書の該当箇所に書き込んでも問題ありません。
論文式試験の過去問の使い方
論文式試験の過去問対策を進めるうえでポイントとなるのが、問題の意味を的確に把握すること。
そのために一番おすすめなのが、過去問と模範解答を見比べることです。どのような問題文に対して、どのような模範解答が書かれているかを分析します。
具体的には、問題文に書かれている言葉が模範解答でどのように使われているのかをチェックするというものです。
次は問題文だけを見て、何を答えるべきなのかを自分で考えてみましょう。いきなり解答を書くのではなく、盛り込みたい内容を箇条書きにして「構成」を作ると書きやすくなります。
口述試験の過去問の使い方
過去問題集には問題文と解答が交互に記載されています。
はじめのうちは、問題文と解答を繰り返し読むことが大切です。声に出して読むと理解が深まります。
解答は一字一句そのまま覚える必要はありません。解答の内容を理解することに努め、自分の言葉で表現できるようにしておきましょう。
弁理士試験の過去問対策におすすめの解説講座
前述の通り、特許庁では、短答式試験の過去問には解説がなく、また論文式試験には模範解答や解説が公開されていません。
弁理士試験の過去問対策をしたい人は、アガルートで提供している過去問解説や模範解答付きの講座で対策するのがおすすめです。
短答式試験の過去問解説講座
弁理士試験 短答式試験の過去問解説を探している人には、アガルートの短答過去問集をおすすめします。
過去10年分の「全問」について、解説をする講座がついているため、しっかりと理解しながら学習を進めることが可能です。
また、過去問集は年度別ではなく、テーマ(体系)ごとに分別されているので、系統立てて勉強を進めることができます。
講義では、重要度・難易度に基づいたランク付けを行っていますので、効率よく学習することが可能です。
論文式試験の過去問解説講座
弁理士試験 論文式試験の解説や解答例が知りたい方は、アガルートの論文過去問集がおすすめです。
平成20年度からの論文式試験について、講師作成の解説及び解答例を参照することができます。
法的な思考方法や論述のポイントを踏まえて解説しているので、正しい思考方法に沿って、問題文を分析する力が身につきます。
解答例を暗記するような勉強方法をとらずとも、合格レベルの論文答案を作成できるようになるのが魅力です。
まとめ
この記事では弁理士試験の短答式・論文の必須科目および選択科目・口述試験の過去問を紹介しました。
弁理士試験を突破する上で過去問対策は必須です。
合格可能性を上げるために、ぜひアガルートの過去問解説講座の受講も検討してみてください。
弁理士試験の合格を
目指している方へ
- 弁理士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの弁理士試験講座を
無料体験してみませんか?


約17時間分の法律の基礎知識と特許法講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!弁理士試験講座のフルカラーテキスト!
アガルート弁理士試験講座のすべてがわかる!パンフレット&ブランドブック
割引クーポンやsale情報が届く!
1分で簡単!無料!
▶資料請求して特典を受け取る
2021年~24年度のアガルート受講生の合格率27.08%!全国平均の4.51倍
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
お祝い金贈呈・全額返金など合格特典付き!
会員20万人突破記念!
全商品5%OFF!
12月25日までの申込で10%OFF!
▶弁理士試験講座を見る※2027年度合格目標