【測量士試験】多角測量とはどんな科目?わかりやすく解説!【トラバース測量】
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります
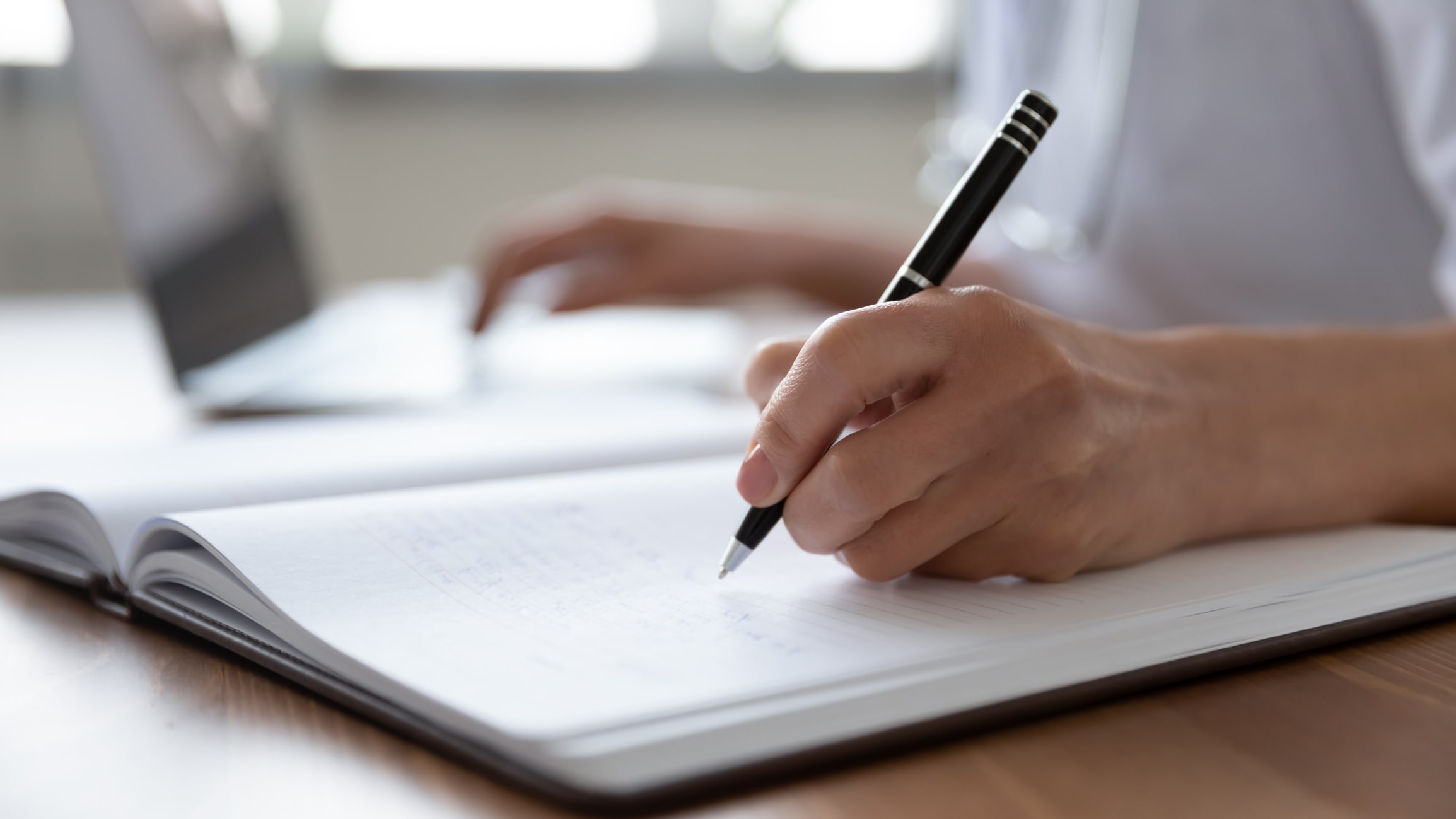
測量士資格試験の「多角測量」について、どのような科目か、その重要度また、どの程度の学習量が必要か悩まれる方がいらっしゃるのではないでしょうか。
これから測量士資格試験を勉強する方や、すでに勉強されている方むけに測量士資格試験科目の多角測量(トラバース測量)についての概要や、勉強法について紹介します。
また、その知識がどのように実務につながるのかについてまとめています。
測量士試験合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
アガルートの測量士試験講座を
無料体験してみませんか?


約4時間の多角測量を含めた講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!測量士試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記
割引クーポンやsale情報が届く!
1分で簡単お申込み
▶資料請求して特典を受け取る目次
「多角測量」科目とは?【トラバース測量】
「多角測量」とはトラバース測量ともいい、ひとつの既知点Aから出発し距離と夾角を計測して未知点の座標計算を行う測量です。
簡単にいうと、座標がわかっている基準点から測量器を使用して距離と夾角を計測した結果を三角関数などを使って座標を持っていない点に座標を持たせる作業です。
測量作業に携わる人であれば、外業で現場作業を行う人や内業でデータ処理を行う人の両者ともに必要不可欠な知識の一つであるため、しっかりとした学習が必要となります。
また、測量を行うにあたって基準となるデータを作成する作業となることから、毎年必ず科目のひとつとして出題されています。
問題数は、例年4~5問が出題され、そのうち2~3問が測量法や測量誤差、測量機器に関する知識を語句の組み合わせや、択一の中から選択する問題となります。
また、例年1~2問は観測データから角度や距離を計算で求める問題が出題されています。
そのため、測量士試験の勉強には必須である科目です。
現在アガルートの測量士試験講座では、無料の資料請求で「多角測量」を含む、約4時間分のサンプル講義やテキストをプレゼント中です。ぜひお試しください。
トラバース測量の種類とは?
トラバース測量には、「開放トラバース測量」「閉合トラバース測量」「結合トラバース測量」の3種類があります。
それぞれの違いをしっかり理解しておきましょう。
開放トラバース測量
基準点からスタートして、最後の点がどの基準点とも結合しない測量方法です。
簡易的なやり方のため、作業自体は早いですが精度としては劣るというデメリットがあります。
閉合トラバース測量
最初の基準点と最後の点を同じ場所に設定する測量方法です。
さまざまな場所を測量して元の点に戻るため、機械の誤差や人為的ミスなどの問題の原因が把握しやすくなります。
測量後した時に生じた最終的な誤差の値を閉合比といいます。
閉合比を計算して値が1/2500mmなどであれば、精度は十分といってよいでしょう。
結合トラバース測量
最初の基準点から始まり、最後は別の基準点に結合する測量方法です。
開放トラバース測量よりは高い精度ですが、閉合トラバース測量よりは精度は劣ります。
「多角測量」の勉強法
「多角測量」では、距離や角度を求める計算問題が出題されるため、三角関数などの数学的知識がすでに身についている方は、その分の学習を短縮できます。
こちらでは、以下の流れで勉強法を紹介します。
- まずは語句と意味を理解する
- 計算作業が無い選択問題は過去問を繰り返す
- 計算問題は三角関数などの数学的知識を修得するところから
1.まずは語句と意味を理解する
測量士試験では、TS(トータルステーション)、最確値、標準偏差、偏心補正、方向角、既知点など様々な語句がでてくるので、それぞれがどのような意味なのか理解できるようにしておくと学習がスムーズなります。
2.計算作業が無い選択問題は過去問を繰り返す
測量の基準、測量誤差、TS(トータルステーション)、GNSSなどについての知識を問う問題が出題されます。
基本的には、過去問を繰り返して問題に慣れる作業と素早く解答できるようになるよう学習を進めていきましょう。
はじめは、わからない言葉やイメージがしずらいと思いますので、問題に慣れるまでは言葉の意味を調べることや図解が載っている参考書などで学習を行い、問題を見た時に頭にイメージができるようになると良いでしょう。
3.計算問題は三角関数などの数学的知識を修得するところから
例年1~2問が出題される計算問題では、三角関数などの数学的知識や計算方法を習得しているかによって学習時間が異なります。
数学の学習から行う方は、まずは測量に使用する数学について学習することとなりますので、多角測量で使用する数学の学習時間が必要となります。
はじめに過去問の解説書などを見ながら実際に問題を解いていくなどの学習をして、理解が定着できない問題については、測量に関する数学の書籍で学習することをオススメします。
数学の学習を終えている方は、過去問を解いてみて不正解だった問題やさらに理解を深めておきたい問題について学習しておくと良いでしょう。
多角測量の例題としては、方位角を計算する問題や、調整量を求める問題、 緯距と経距の標準偏差を求める問題などが計算問題として出題されます。
いずれも計算方法や求め方がパターンとなっており、似た問題が例年出題されますので、ここでも過去問を中心とした演習が重要です。
【試験科目ごとの勉強法はこちら】
・測量に関する法規及びこれに関連する国際条約
・多角測量
・汎地球測位システム測量
・水準測量
・地形測量
・写真測量
・地図編集
・応用測量
・地理情報システム
関連記事:【測量士の勉強法】午前試験(択一式)・午後試験(記述式)それぞれ解説
測量士試験合格を
目指している方へ
- 測量士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの測量士試験講座を
無料体験してみませんか?


約4時間の多角測量を含めた講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!測量士試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記
割引クーポンやsale情報が届く!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る
豊富な合格実績!
令和7年度のアガルート受講生の合格率87.64%!
追加購入不要!これだけで合格できる
カリキュラム
充実のサポート体制だから安心
合格特典付き!
会員20万人突破記念!
全商品5%OFF!

この記事の監修者 中山 祐介 講師
2008年 法政大学 文学部地理学科 卒業
2010年 東京都立大学 大学院 都市環境科学研究科 修了
2012年 土地家屋調査士試験を全国1位で合格(択一1位・書式2位)
2013年 測量士 登録
2014年 行政書士試験 合格
2015年 特定行政書士考査 合格
独学で土地家屋調査士試験全国総合1位合格の同試験を知り尽くした講師。
「すべての受験生は独学である」の考えのもと、講義外での学習の効率を上げ、サポートするための指導をモットーに、高度な知識だけでなく、自身の代名詞でもある複素数による測量計算([中山式]複素数計算)など、最新テクニックもカバーする講義が特徴。日々、学問と指導の研鑽を積む。



