社労士試験の試験科目や試験内容一覧!気になる合格基準点や出題範囲も解説
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

社会保険労務士試験(以降、社労士試験)を受験する・受験しようとしている方へ。
社労士試験の内容や科目、出題範囲などについてご紹介します。
また後半では、法改正の影響や救済措置、免除規定など、社労士試験を受験する方は抑えておきたい情報もご紹介しておりますので、是非ご覧ください。
社会保険労務士試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 社会保険労務士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの社会保険労務士試験講座を
無料体験してみませんか?
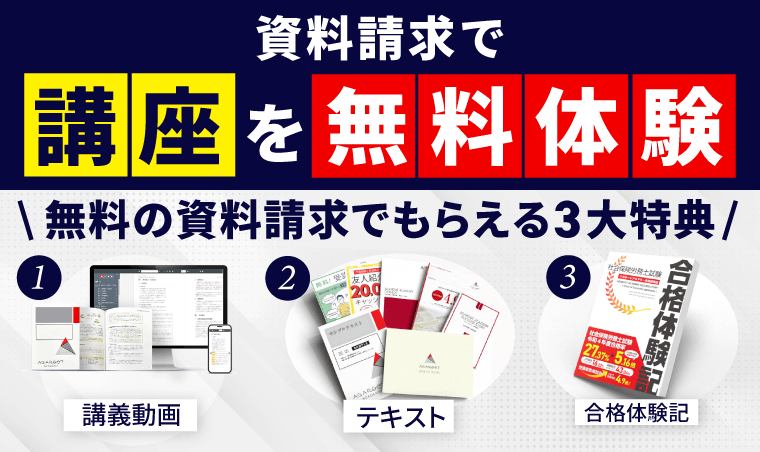

約6.5時間分の労働基準法講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト
一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!
1分で簡単お申込み
▶資料請求して特典を受け取る目次
社会保険労務士試験の試験内容
社会保険労務士の試験内容は、「択一式試験」「選択式試験」の2つの試験に分かれており、全10科目から出題されます。
労働関係科目と社会保険関係科目からそれぞれ選択式で4問、択一式で30問(労働・社会保険の一般常識から10問)出題されます。
- 選択式試験…条文などの文章中の空欄に当てはまる言葉や数字を複数の選択肢の中から選ぶ問題
- 択一式試験…5つの選択肢から適切なものを選ぶ問題
従って、社会保険労務士の試験内容では幅広い知識をバランスよく学んでいくことが重要です。
社会保険労務士試験の選択式試験とは
社会保険労務士試験の「選択式試験」とは、社会保険労務士試験の一部で、各問題に5つの空欄があり、20の選択肢から正しい語句や数値を4つ選んで解答する形式です。
選択式試験は計8科目出題され、空欄1つにつき1点で、合計8問(40点満点)です。また、選択式試験の試験時間は、10:30~11:50の約80分(1時間20分)です。
※関連記事:社会保険労務士試験の選択式とは?選択式の勉強法や対策、合格ラインを解説
社会保険労務士試験の択一式試験とは
社会保険労務士試験の択一式試験とは、社会保険労務士試験の一部で、各問題ごとに5つの選択肢から「正しいもの」または「誤っているもの」を1つ選んで解答する形式です。
択一式試験は計7科目出題され、1科目につき10問出題され、計70問(70点)です。また、択一式試験の試験時間は、13:20~16:50の約210時間(3時間30分)です。
※関連記事:社会保険労務士試験の択一式とは?択一式の勉強法や対策、合格ラインを解説
社会保険労務士試験の試験科目の特徴と対策
社会保険労務士試験の選択式試験の試験科目は、全8科目で、1科目に1問出題されます。
1問につき5つの空欄があり、空欄1つにつき1点の配点がされて計5点となるため、選択式全体では40点満点になります。
次に社会保険労務士試験の択一式試験の試験科目は、全7科目で、1科目につき10問出題されますから、計70問出題されます。
1問につき1点が配点されているため、択一式全体では70点満点になります。
| 社会保険労務士試験の試験科目 | 選択式試験(配点) | 択一式試験(配点) |
|---|---|---|
| 労働基準法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 労働安全衛生法 | ||
| 労働者災害補償保険法 | 1問(5点) | 7問(7点) |
| 雇用保険法 | 1問(5点) | 7問(7点) |
| 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 出題なし | 6問(6点) |
| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 社会保険に関する一般常識 | 1問(5点) | |
| 健康保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 厚生年金保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 国民年金法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 合計 | 8問(40点) | 70問(70点) |
労働基準法(科目名略称:労基)
労働基準法は、労使関係の基本的なルールや最低条件を定めた法律で、社労士にとっては必ず覚えておく必要のある科目です。
次の労働安全衛生法と合わせて出題され、出題範囲には労働契約や賃金の支払い、労働時間、変形労働時間制、年次有給休暇や就業規則などが含まれます。
基本的な条文の内容や文言はもちろん、判例や通達からも出題されます。さらに、長文で出題されるなど解きにくい問題が目立つ科目です。
労働基準法の対策として、基礎的な内容や法律の考え方をしっかりと理解しておくことで、試験本番で初めて見る判例が出たとしても回答の方向性が見えてきます。
労働安全衛生法(科目名略称:安衛)
労働安全衛生法は、労働者の健康と安全のために必要なルールを定めたものです。
労働基準法と合わせて出題され、安全衛生管理体制、機械や危険物・有害物に関する規制、安全衛生教育などが含まれます。
安全衛生管理体制や健康管理などの基本的な項目が高頻度で出題される一方で、かなり細かい規定からの出題も見られます。
労働安全衛生法の対策方法として、数多くある規定をすべて覚えようとするときりがないので、出題傾向を確認しながら確実に点数を取れる問題を落とさない学習をすることが大切です。
※関連記事:【社労士試験】労働基準法・労働安全衛生法の勉強法と攻略ポイント
労働者災害補償保険法(科目名略称:労災)
労働者災害補償保険法(労災保険法)は、仕事中や通勤中の事故などによるケガや死亡を補償するための保険制度です。
出題範囲には、業務災害、通勤災害、保険給付、特別加入などが含まれ、択一式では労働保険の保険料の徴収等に関する法律とともに出題されます。
保険給付を中心として過去に出題された内容が繰り返し問われる傾向があり、基礎的な内容をしっかりと頭に入れておけば得点しやすい科目です。
労働者災害補償保険法の対策方法として、判例や事例からの出題もありますので、ひと通りおさえておくと良いでしょう。
※関連記事:【社労士試験】労働者災害補償保険法(労災保険法,労災法)の勉強法
雇用保険法(科目名略称:雇用)
雇用保険法は、失業した時に職業安定所でもらう給付や安定した雇用確保のための制度を定めたものです。
失業者への基本手当などの求職者給付、教育訓練給付、育児休業給付金などの雇用継続給付などがあり、択一式では労働保険の保険料の徴収等に関する法律と合わせて出題されます。
基礎的な内容を問う問題が多い科目ですが、数字を暗記していなければ回答できない問題が多いのも特徴といえます。
雇用保険法の対策方法として、手当や給付金の種類が多く、条件や内容を混同してしまいやすいので、整理しながら覚えるようにしましょう。
※関連記事:【社労士試験】雇用保険法とは?対策・勉強法と3つの攻略ポイント
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(科目名略称:徴収)
労働者災害補償保険法(労災保険法)と雇用保険法を合わせて労働保険と呼び、その保険料の納付方法を定めた法律が労働保険の保険料の徴収等に関する法律です。
労働者災害補償保険法(労災保険法)と雇用保険法の択一式の中でそれぞれ3問ずつ出題され、選択式での出題はありません。内容としては、保険関係の成立・消滅、保険料の申告・納付などがあげられます。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律は出題範囲が限られているため、同じような問題が繰り返し出題されやすく、過去問で対策が取りやすい科目です。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の対策方法として、保険料額の計算問題が出されることもありますので、素早く正確に計算する練習をしておくと良いでしょう。
※関連記事:【社労士試験】労働保険徴収法とは?対策・勉強法と得点源にする方法
労務管理その他の労働に関する一般常識(科目名略称:労一)
上述した科目(労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律)を除く労働関連の諸法律や、給与体系や組織構成など労務管理にかかわる知識、厚生労働白書や統計の内容について出題されるのが、労務管理その他の労働に関する一般常識です。
出題範囲となる法令の中には労働組合法、パートタイム労働法、最低賃金法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働者派遣法などがあります。
出題範囲が広く、統計からの出題が多いため得点しづらい科目です。
労務管理その他の労働に関する一般常識の対策方法として、基本的な法律の内容をしっかりとおさえながら、統計のトレンドと大体の数字も頭に入れておくと良いでしょう。
※関連記事:【社労士試験】労働に関する一般常識(労一)の勉強法
健康保険法(科目名略称:健保)
労働者の病気やけが、出産や死亡などに対して給付を行うのが健康保険法です。
内容としては、適用事業所、被保険者、標準報酬、保険給付、高額療養費、費用の負担などがあり、我々に身近な法律ですのでイメージがつかみやすい科目です。
健康保険法の対策方法として、健康保険法は保険給付だけでなく、全体的に偏りなく出題される傾向がありますので、ひとつひとつの項目を丁寧に学習し、数字を暗記する必要があります。
また、保険給付の内容が労働者災害補償保険法(労災保険法)の給付と似ていて間違えやすいので注意しましょう。
※関連記事:【社労士試験】健康保険法(健保法)とは?対策・勉強法と2つの攻略ポイント
厚生年金保険法(科目名略称:厚年)
厚生年金保険法は、労働者の年金制度を定めた法律です。
出題範囲としては、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、年金額の調整などがあります。
保険給付が出題の中心となりますが、法改正が重ねられてきた経緯から複雑な制度になっており、覚える数字も多い科目です。しかし、一度覚えれば比較的試験では点数の取りやすい科目ともいえます。
厚生年金保険法の対策方法として、先に国民年金法を学習しておくことで理解がしやすくなります。
事例問題でも国民年金制度に絡めて出題されることがありますので、国民年金制度とのかかわりや同じ点、異なる点などを整理しながら勉強すると良いでしょう。
※関連記事:【社労士試験】厚生年金保険法(厚生年金法)の勉強法
国民年金法(科目名略称:国年)
日本国民に適用される年金制度が国民年金法です。
内容には被保険者、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、国民年金基金などの項目があります。
給付を中心として基礎的な問題が多く出されますが、法改正の影響などで複雑な内容も含まれます。
国民年金法は年金制度の基礎となる法律ですので、しっかりと勉強してよく理解することで厚生年金保険法の理解にもつながります。
配点も高く、社労士試験合格のためには欠かせない重要な科目といえるでしょう。
※関連記事:【社労士試験】国民年金法(国年法)の勉強法
社会保険に関する一般常識(科目名略称:社一)
健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法以外の社会保険に関連する法律や社会保障制度の沿革などが出題されるのが社会保険に関する一般常識です。
出題範囲となる法令には、国民健康保険法、介護保険法、児童手当法、確定拠出年金法、社会保険労務士法などがあります。
社会保険に関する一般常識は、労務管理その他の労働に関する一般常識と同じく出題範囲が多岐にわたり、厚生労働白書や統計資料からも出題されるため得点が難しい科目です。
そのため、社会保険に関する一般常識の対策方法としては、法令からの出題が多い傾向にあるため、法令の学習を怠らずに得点すべき問題で確実に点を稼ぐことが重要です。
※関連記事:【社労士試験】社会保険に関する一般常識(社一)の勉強法と3つの攻略ポイント
社会保険労務士試験の出題範囲
社会保険労務士試験は全部で10科目あり、大きく労働関係科目と社会保険関係の科目に分けられます。
主な出題範囲は下記となります。
- 「労働基準法」や「労働安全衛生法」といった労働環境に関して規律した法律
- 「労働者災害補償保険法」や「雇用保険法」といった労災や失業などの場合に備えた所得補償に関して規律した法律
- 「労務管理その他の労働に関する一般常識」や「社会保険に関する一般常識」に関する知識
- 「健康保険法」や「国民年金法」、「厚生年金保険法」といった社会保障に関して規律した法律
社会保険労務士試験の労働保険関係科目一覧
労働関係科目は、労働基準法を始め労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、そして、労働保険の徴収に関する法律、労働に関する一般常識の6つから構成されています。
| 試験科目 | 試験内容 |
|---|---|
| 労働保険関係科目 | 労働基準法 |
| 労働安全衛生法 | |
| 労働者災害補償保険法 | |
| 雇用保険法 | |
| 労働者の保険料の徴収等に関する法律 | |
| 労務管理その他の労働に関する一般常識 |
社会保険労務士試験の社会保険関係科目一覧
社会保険関係科目は、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、社会保険に関する一般常識の4つから構成されています。
| 試験科目 | 試験内容 |
|---|---|
| 社会保険関係科目 | 健康保険法 |
| 厚生年金保険法 | |
| 国民年金法 | |
| 社会保険に関する一般常識 |
社会保険労務士試験の試験時間
| 出題形式 | 着席時間 | 試験時間 |
|---|---|---|
| 選択式 | 10:00 | 10:30~11:50(1時間20分) |
| 択一式 | 12:50 | 13:20~16:50(3時間30分) |
※着席時刻から試験の説明が始まるため、上記時間までに試験室に入室し着席しましょう
社会保険労務士試験の合格基準点
社会保険労務士試験オフィシャルサイトによると、令和5年度の社会保険労務士試験の合格基準点は、選択式で40点中26点(各科目5点中3点以上)、択一式で70点中45点(各科目10点中4点以上)でした。
各科目ごとの基準点を守りつつ全体の7割正解することを目指しましょう。
① 選択式は、40点中26点以上かつ各科目3点以上
② 択一式は、70点中45点以上かつ各科目4点以上
「合格基準」とは、社労士試験に合格するのに満たさなければならない条件のことで、科目ごとに設定されており、さらに「選択式」全体と「択一式」全体に設定されています。
合格基準点は、「選択式」全体と「択一式」全体にだけでなく、各科目にも合格基準が設定されていることから、社労士試験に合格するためには苦手な科目・弱点となる科目を作ることができません。
社労士試験は全科目まんべんなくしっかりと学習する必要があり、バランスが求められる試験であるといえます。
なお、「合格基準」は受験生全体の出来によって毎年変わります。
そのため、その年の合格基準がどのようなものになるのかは、ベテランの社労士試験講師でも予想が難しいものです。
もっとも過去の社労士試験の結果をみると、各科目ごとの基準点を超えていることが前提ですが「選択式:40点満点中28点、択一式:70点満点中48点」を取ることができれば、ほぼ確実に合格することができます。
そのため、社労士試験の勉強を始めるにあたっては、とりあえず「7割合格」を目指してください。
【直近5年】社会保険労務士試験の合格基準点と科目最低点一覧
| 年度 | 択一式 合格基準点 | 択一式 科目最低点 | 選択式 合格基準点 | 選択式 科目最低点 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年 | 45点 | 4点 | 26点 | 3点 |
| 令和4年 | 44点 | 4点 | 27点 | 3点 |
| 令和3年 | 45点 | 4点 | 24点 | 3点 (労一→1点, 国年→2点) |
| 令和2年 | 44点 | 4点 | 25点 | 3点 (労一・社一・健保→2点) |
| 令和元年 | 43点 | 4点 | 26点 | 3点 (社一→2点) |
▼対策について知りたい方は『社労士試験の択一式・選択式対策』もご覧ください
社会保険労務士試験における救済措置とは?
2023(令和5)年度の社労士試験においては、救済科目(救済措置)はなしという結果でした。
社会保険労務士試験の救済措置・救済科目とは、合格基準を下げることを指します。
救済措置はその年の受験生全体の出来によって設定されるものです。
そのため救済措置は、実施する科目があらかじめ決まっているわけでなく、試験の結果が発表されて初めて明らかになるものです。
もっとも、例年の傾向をみる限り救済措置は多くの受験生の出来がよくなかった科目に関しては、かなりの確率で行われる措置です。
救済措置という制度があることからも、社労士試験では他の受験生ができない問題に関してできるようになる必要はありません。
むしろ他の受験生が確実に正解する問題は確実に正解できるように準備する必要がある試験なのです。
※関連記事:社労士試験の救済とは?基準や傾向を解説
社会保険労務士試験における法改正の影響はどこまで?
社会保険労務士試験の法改正の影響は、その年の4月までに改正された内容は試験で出題される可能性があります。
社労士試験は、あらゆる国家試験のなかで最も法改正の影響を受ける試験です。
他の資格試験だと改正された直後に出題されること自体大変珍しいことですが、社労士試験では法改正の内容が出題される可能性が比較的高い試験です。
そのため、4月からは法改正の内容をしっかりマスターすることも重要になってきます。
4月までに法改正が行われていない法令や制度についてしっかりマスターしておけば、他の受験生よりも有利に進めることができるでしょう。
近年は、特に社会保障分野において、毎年のように制度の見直し・改定が行われています。
それらの内容に関する情報を受験生自身の手で集めるというのは簡単ではありません。
まして、数多く存在する法改正の中から社労士試験に出題される可能性のある内容を取捨選択するのは至難の業です。
法改正に関する情報収集が大変だからといって、法改正の内容を勉強することなくその年の社労士試験を受験することはとても勿体ないことです。
多くの合格者は、予備校がまとめた法改正に関する講義や教材を活用して、効率的に勉強しています。
※関連記事:社労士試験の法改正対策はどうすれば良い?いつまでの法改正が対象?
社会保険労務士試験の科目免除とは?
社会保険労務士試験の科目免除制度とは、社会保険労務士試験の科目の免除を受ける資格を有する方(免除資格者)は、受験申込みの際に申請することによって科目の免除を受けることです。
資格を有する、または職歴によって該当する科目に関する知識が十分にあると思われることから、免除資格者は該当する科目が免除されます。
| 資格・職種例 | 免除科目 |
|---|---|
| 司法試験に合格した者で労働法を選択した者 | 労働基準法及び労働安全衛生法 |
| 労働基準監督官採用試験に合格した者 | 労働基準法及び労働安全衛生法 |
| 日本年金機構の役員(非常勤の方は除きます)又は 従業者として厚生年金保険法の実施事務に 従事した期間が10年以上になる者 | 厚生年金保険法 |
科目が免除されると他の科目に割り当てる勉強時間が増えるため、合格に向け有利になることは間違いないでしょう。
上記以外にも科目が免除されるケースがありますから、何か心当たりのある方は、一度確認してみましょう。
※関連記事:社労士試験の科目免除制度とは?条件やおすすめ科目を解説
社会保険労務士試験によくある質問
独学で社労士試験に受かりますか?
率直に申し上げて、社労士試験に独学で合格するのは、かなり難しいと思われます。
社労士試験は、会社員の方にとって身近な話を勉強するとはいえ、法律に関する専門的な知識を勉強することになります。
大学の法学部出身の方などを除くと、法律に関する勉強は、ほとんどの方がやったことがありません。
勉強経験のないことに独りで臨むというのは、荒波にコンパスも持たずに飛び込むようなものです。
また、社労士試験は直近の法改正に関して出題してくることもあり、法改正に関する情報をしっかりチェックしておく必要もあります。
未経験の法律の勉強に加え、それほど詳しくない法律の改正情報を集めることになります。
そういった作業をすべて自分でやることも考えると、社労士試験における独学というのは、とてもハードルが高いです。
▼更に詳しく知りたい方は「社労士は独学だと無理?その理由と独学合格が難しい人の3つの特徴」もご覧ください
試験に合格するにはどれくらいの勉強時間が必要か?
社労士試験に合格するにあたり、最低でもおおよそ1,000時間程度の勉強時間が必要だとされています。
社労士試験の合格者が一般的に勉強を開始するのは、受験する年の前年8~10月頃です。
仮に1,000時間として、10月から始めるとすると、翌年の社労士試験本番まで約11か月なので、1か月の勉強時間は約91時間(1か月4週で計算すると約22.7時間/週)になります。
例えば、平日5日が勤務日で土日2日が休日という方の場合「平日5日は1日2時間で、土日2日は5~6時間半」が目安になります。
▼更に詳しく知りたい方は『社労士試験の勉強時間』もご覧ください
社会保険労務士試験における過去の合格基準点
| 年度 | 択一式 合格基準点 | 択一式 科目最低点 | 選択式 合格基準点 | 選択式 科目最低点 |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 44点 | 4点 | 27点 | 3点 |
| 令和3年 | 45点 | 4点 | 24点 | 3点 (労一→1点, 国年→2点) |
| 令和2年 | 44点 | 4点 | 25点 | 3点 (労一・社一・健保→2点) |
| 令和元年 | 43点 | 4点 | 26点 | 3点 (社一→2点) |
| 平成30年 | 45点 | 4点 | 23点 | 3点 (社常・国年→2点) |
| 平成29年 | 45点 | 4点 (厚年→3点) | 24点 | 3点 (雇用・健保→2点) |
| 平成28年 | 42点 | 4点 (常識・厚年・国年→3点) | 23点 | 3点 (労常・健保→2点) |
| 平成27年 | 45点 | 4点 | 21点 | 3点 (労常・社常・健保・厚年→2点) |
| 平成26年 | 45点 | 4点 (常識→3点) | 26点 | 3点 (雇用・健保→2点) |
| 平成25年 | 46点 | 4点 | 21点 | 3点 (社常→1点, 労災・雇用・健保→2点) |
| 平成24年 | 46点 | 4点 | 26点 | 3点 (厚年→2点) |
| 平成23年 | 46点 | 4点 | 23点 | 3点 (労基安衛・労災・社常 厚年・国年→2点) |
| 平成22年 | 48点 | 4点 | 23点 | 3点 (国年→1点, 健保・厚年・社常→2点) |
| 平成21年 | 44点 | 4点 | 25点 | 3点 (労基安衛・労災・厚年→2点) |
| 平成20年 | 48点 | 4点 | 25点 | 3点 (健保→1点, 厚年・国年→2点) |
| 平成19年 | 44点 | 4点 | 28点 | 3点 |
まとめ
社労士試験の内容や科目、合格基準点や出題範囲などについて解説していきました。
試験の詳細については、「社会保険労務士(社労士)試験の概要」のコラムをご覧下さい。
社会保険労務士試験の合格を
目指している方へ
- 社会保険労務士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの社会保険労務士試験講座を
無料体験してみませんか?
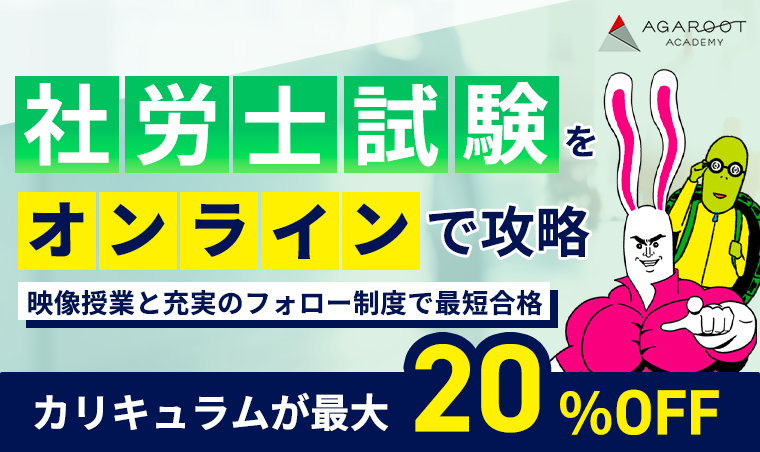
令和5年度のアガルート受講生の合格率28.57%!全国平均の4.46倍
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!
8月18日までの申込で20%OFF!
▶社会保険労務士試験講座を見る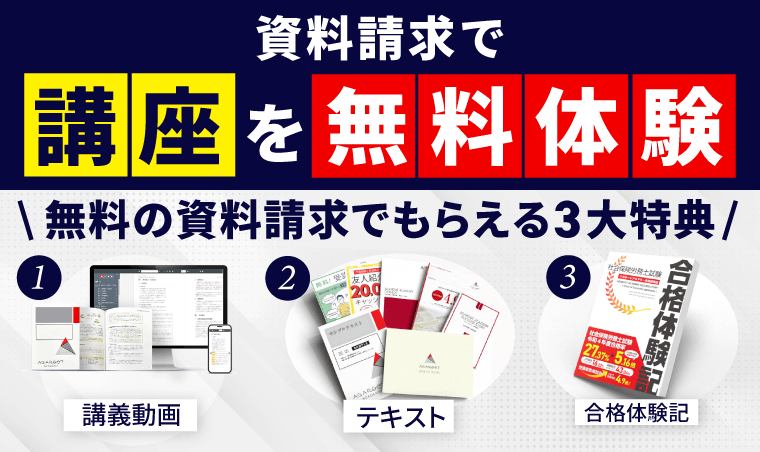

約6.5時間分の労働基準法講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!公務員試験のフルカラーテキスト
一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!
1分で簡単!無料!
▶資料請求して特典を受け取る
この記事の監修者 池田 光兵講師
広告代理店で、自らデザインやコピーも考えるマルチな営業を経験後、大手人材紹介会社で長年キャリアアドバイザーを経験、転職サポートを行う。
面接対策のノウハウや数々の自作資料は現在でも使用されている。
その後、研修講師や社外セミナーの講師などを数多く経験。
相手が何に困って何を聞きたがっているのかをすばやく察知し、ユニークに分かりやすく講義をすることが得意。
ほぼ独学で就業しながらも毎日コツコツと勉強し、三度目の社労士試験で合格した苦労談も面白く、また、三度やったからこそ教えられる「やっていいことと駄目なこと」も熟知している。
合格のノウハウをより多くの受講生に提供するため,株式会社アガルートへ入社。
自らの受験経験で培った合格のノウハウを余すところなく提供する。
池田講師の紹介はこちら



